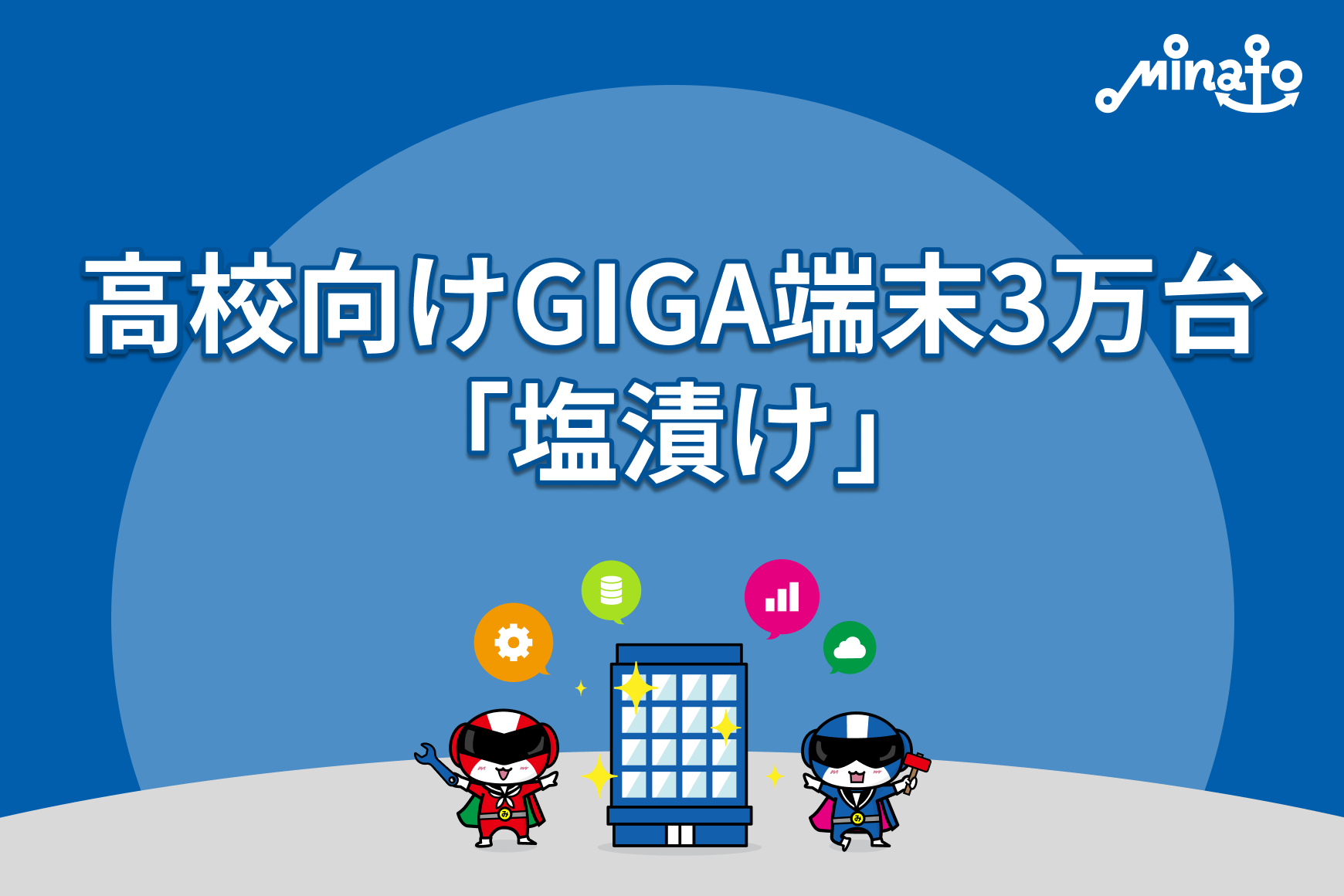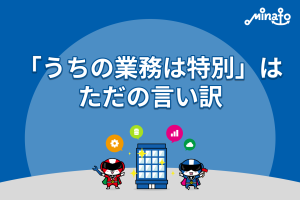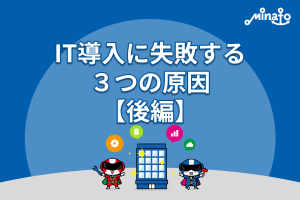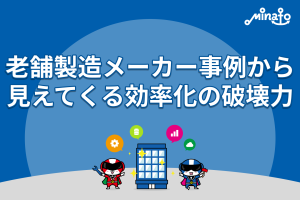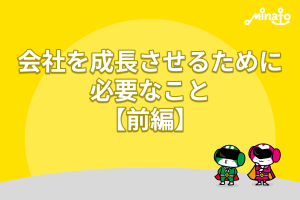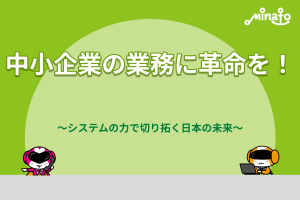COLUMN コラム
前途多難ぶりを発揮しているGIGAスクール構想
GIGAスクール構想とは、全国の児童・生徒1人に1台ずつのコンピューターを用意する文部科学省の取り組みのことである。
背景としては、世界的に見てデジタル機器の使用時間が低いことを問題視し、世界基準に持って行きたいと考えての取り組みである。
コロナ禍において日本の教育現場がいかにデジタル技術の活用を行っていないのかが露呈した。
このこともあって、日本を支える若者を早い内からデジタルに慣れさせようという動きである。
すごくよく聞こえる。
肝心の内容は不明だが、考えていることはとてもよく聞こえる。
だが、実に3万台を超えるコンピューターが「塩漬け」状態になっているのだ。
奨学給付金を受給する高校生向けの貸与端末が全くと言っていいほど活用されていないことが判明した。
国は1台当たり最大45,000円の補助金を用意し、各自治体に9万5,554台の貸与端末を用意させた。
約10万台あるのに、その3分の1以上の台数が「塩漬け」されているのだ。
また、徳島県の県立高校などに配備された端末が半数以上も故障したというニュースも流れた。
このように前途多難ぶりが発揮されている。
そもそも教育できるのか?
国がやりたいことは分かる。
しかし、そもそも今の日本教育の現場においてデジタル教育ができるのだろうか?
国の狙いに合致した教育ができるだろうか?
答えは「ノー」である。
そもそも教師側がデジタルスキルを保有していない。
そんな教師に何を学ぶのか?
私は元々教師になりたかった。
パワポを使った授業を行った先輩が先輩教師にパワポを使った授業をするなと注意されたと笑い話を聞いたことがある。
その先輩教師は、パソコンが使えないので明らかに差別化されて困るから紙で授業をするよう指摘したそうだ。
言ってしまうと、野球を見たこともないしルールも知らない人から野球を教わるようなものだ。
また、日本の教育は「個」の特性に合わせた教育を行っていない。
どちらかというと、画一的な教育を行っている。
個人個人に合わせた教育を行うのが苦手だ。
学習塾で「スクールIE」をご存知だろうか?
「やる気スイッチ」というCMで有名だ。
実はスクールIEさんは元々教育現場を変えたいと考えていたが、学校教育現場で「やる気スイッチ」を導入するのは難しいと断念して、学習塾を開くことにしたというエピソードがある。
やる気スイッチは「個」に着目して、その子その子に合わせた「やる気スイッチ」を探し出して押す教育スタイルだ。
だからこそ、日本の教育現場に合わないのだ。
GIGAスクールの構想として、「子共たち一人ひとりに個別最適化され、創造性を育む教育ICT」という発表があったが、日本教育現場においてはなかなかハードルの高い目標であると思う。
教育現場の抜本的な見直しが必要
そもそも学校教育の環境自体よくない。
デジタルスキルを有していないのも最新の教育が何かを理解していないのも問題だ。
昔の子どもと今の子どもでは特性が違う。
ゆとり世代とかZ世代とか言うくらい全然違う。
もし同じやり方をしていたら、問題である。
また、最新の教育プログラムが何かを把握し、実験することも大切だ。
プロである以上、常に最新の情報に触れ、実行できるようになるべきである。
特に「士」「師」という字が書かれている職業は、人の生死や人生に関わることが多い。
他の人を生かすも殺すも自分次第であるという覚悟と責任が必要である。
だが、そもそも教育現場が悪い。
教師一人に頼り過ぎだ。
教師が可哀そうになってくる。
- 授業の準備
- 授業
- 親への連絡
- 資料作成
- テレアポ
- 営業活動
- 問合せ窓口
- 謝罪
- イベント発案
- イベント準備
一人で何個兼務すればいいんだろうか。
こんなことでは新しいスキル・ノウハウの習得もできないし、デジタル教育も無理である。
子どもに向き合う時間より親に向き合う時間の方が多いのではないだろうか?
最早親向けのサービス業である。
塾と学校は違う。
教師は、授業を行うことに集中すべきである。
塾の方が授業に集中できているのは、本当に悲しい現状である。
たとえば家庭訪問を含むあらゆるコンサル業務や親からの電話対応など外出しすべきだ。
一般的な会社もそうしているのに、何故教育現場において教師の負担になるのだろうか?
また、社会に出たこともない教師が社会の厳しさを教えるのも変だと思う。
なので、教師は一定期間外部研修として社会活動をした方がいい。
社会に出ることで、いかに自分たちの仕事が「やらなくていい仕事」ばかりか分かるはずだ。
まとめ~デジタル教育をしたいなら、まず教育現場から~
教育できる体制ができていないのに、先走ってしまっているのが問題であると考える。
確かに素晴らしい取り組みであるとは思う。
しかし、対応する人材の不足や体制の欠如があると、十分な効果が発揮できない。
むしろ悪影響を及ぼす結果になる。
一番の被害者は子どもである。
「ええこと考えた!」
でやるのではなく、しっかり準備を整えて着実に実行できるプランを用意すべきである。
そのためにも、急がば回れ、である。
教育現場の抜本的な見直しを行うべきである。
教師にもっと子どもと向き合う時間を作るべきである。
ちなみに、デジタル教育の先進国と言われているスウェーデンが、アナログ教育に戻ると発表した。
このように教育も科学である。
よいと思ったことがそうでもないこともあるし、悪いと思っていたことが実はよかったということもある。
だからこそ、様々なエビデンスを元に実証実験を繰り返していく必要があるのだ。
IT先進国スウェーデン、学校で「紙と鉛筆のアナログ教育」に戻る計画を発表