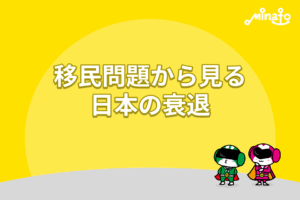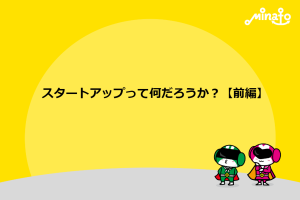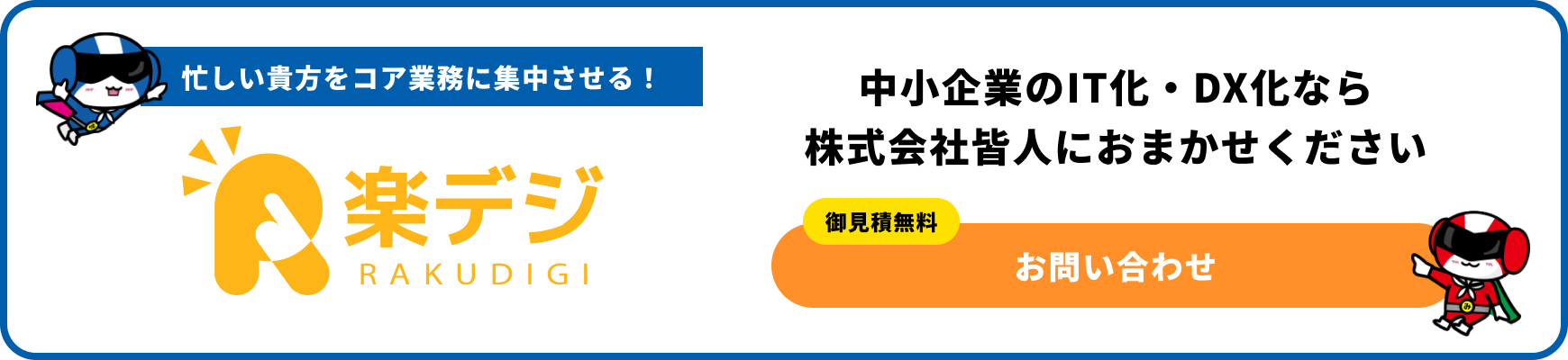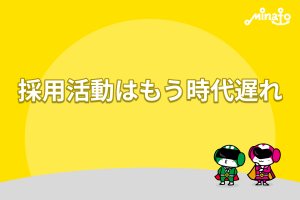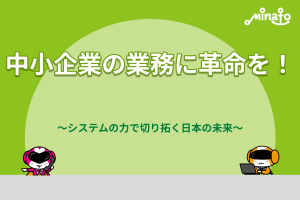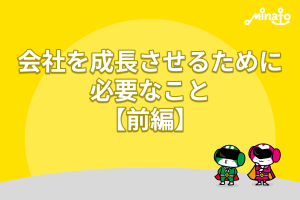COLUMN コラム
これまでベンチャーとスタートアップについて見てきた。
前編では、ベンチャーとスタートアップという言葉の定義について見てきた。
中編では、スタートアップの特徴とされる5項目を順番に見ていった。
前編・中編まで見てきた中で、どうやらベンチャーもスタートアップも違いがなさそうである。
スタートアップはシリコンバレーで立ち上がった創業間もないIT企業を指す言葉であった。
そして、ベンチャーはそもそも和製英語で立ち上げ間もない企業や社員数の少ない企業を指している。
つまり、スタートアップもベンチャーも実は同じことを指しているようなのだ。
だが、日本においては明確に違って用いられている。
スタートアップ企業をベンチャー企業と言わないし、ベンチャー企業をスタートアップ企業とは言わない。
とはいえ、各企業の実態や状況を見ていくと、スタートアップもベンチャーだし、ベンチャーもスタートアップのように思う。
そこで、後編である今回は言葉の用法を明確するため、私個人の見解をお伝えしていきたい。
目次
改めてスタートアップの特徴を見ていきたい
スタートアップとベンチャーの違いで特筆すべき特徴は3つであると考えている。
- スピード感
- 出口戦略
- 革新的なビジネスモデル
上記以外の「収益性」と「資金調達」は大した違いではないと考えている。
では、改めてこの3つについて見ていきたい。
スピード感は中小企業であればあって当然
スピード感の違いは、中小企業であれば大企業よりもあって当たり前である。
身軽というメリットが中小企業にある。
スピード感のない中小企業は中小企業のメリットがないが、日本においてはスピード感のない中小企業が非常に多い。
IT化の推進状況
DX化の推進状況
AIの活用状況
などどれも大手よりも低い。
世界的に見ても珍しい状況である。
本来であれば中小企業こそ大手に負けないように果敢に挑戦すべきであるのだ。
よってスピード感の有無がスタートアップを決定づける理由にはならない。
出口戦略は起業する前から考えるべきこと
目標を立てるべきである、とよく耳にする。
起業をする際に目標を立てるだろう。
何も目指す方向がないのに起業する人はいないだろう。
ゴールがあるから人は頑張れるのである。
甲子園も永遠に努力するとなれば、高校球児は発狂するだろう。
3年間とタイムリミットがあるから頑張れる。
また、商品のライフサイクルも3年と短くなっている。
そのため、近年ではビジネスの寿命は3年であり、ゴール設定を3年にしようと教えている人も多い。
昔はライフサイクルが50年と言われていた。
最早そんな時代は終わったのだ。
ゴール設定のないビジネスは頑張り切れないし、お客様や社会に貢献もできない。
よってゴール設定はして当たり前なのだ。
真新しいビジネスモデルはない
世の中に商品やサービスは溢れている。
もうお客様もお腹いっぱいなのだ。
お客様の抱えている課題を解決してくれるなら、その手段であるサービスや商品は別に何でもよいとさえ感じている。
「真新しい商品やサービスは正直すでに失敗しているから、世の中にない」と言っている方もいるくらいだ。
たとえばパソコン。
パーソナルになったコンピューターである。
別にコンピューター自体は新しくない。
ただパーソナルになったから目新しかったのだ。
iPhoneも電話とインターネットと音楽デバイスを合体したものであり、それぞれは別に真新しいわけではない。
目新しく、誰もが「そう!そういうのが欲しかった!」と思ったから爆発的に売れたのだ。
「革新的で真新しいビジネスモデル」と定義した瞬間、世の中にあるスタートアップは全て駆逐されるのだ。
今の世の中、商品・サービスはありふれている。
そんな中でお客様に選ばれ続けるためには、目新しいサービスや商品を開発し提供し続ける必要がある。
たとえ「ITコンサル」というありふれたサービスであっても、他と一緒では選ばれない。
何が違うのか
どう違うのか
どういうターゲット層を相手にしているのか
どういうベネフィットを得られるのか
そういったことを突き詰めていけば、自ずと目新しいサービスになっていく。
なので、目新しいかどうかも区別する条件にならない。
では、何が条件になるだろうか?
いろいろ調べた上での私なりの持論をここからは述べていきたい。
スタートアップの条件は2つ
そもそもベンチャーとスタートアップが同じ意味合いを持っているからややこしいのだ。
だが、最近日本において分けて使っていることが多い。
そこで明確に違いを付けるとしたら、どうなるか考えてみたい。
私が考える条件は2つになる。
社会課題を解決することを目的とするかどうか
一番大きな条件としては、この条件になるだろうと思う。
ビジネスの根本は、お客様や社会の課題を解決することである。
そういった意味では、これもまたベンチャーとスタートアップの区別に役に立たない。
しかし、より顕著に使命を持って取り組んでいるのがスタートアップであるように思う。
スタートアップ企業には、「私たちは社会の〇〇という課題に□□という手段で解決していく企業です」という熱い志を持っている。
自分たちが社会を変えていけると信じて止まない。
そういう気持ちがあるから人が動き、ビジネスが発展していくのだろう。
スタートアップ企業の代表がお話している内容をお聞きすると、その熱量に感化される。
この熱量があるかどうかがポイントであると思う。
一方で、ベンチャーの場合、「創立して間もない」「従業員数が少ない」「スモールビジネス」といった特徴を持つとされている。
この特徴を持つのであれば、社会課題を解決することに主眼を置いていなくても起業すれば「ベンチャー」と言えそうである。
簡単に言うと、自分のための夢なのか、誰かのための夢なのか、という区別だ。
とにかく人のため、社会のために、今ある課題を解決したいということを目的とするかどうかでスタートアップかどうかが決まるのではないだろうか。
この志がない企業はスタートアップと呼んではいけない。
そう私は考える。
「世界規模」か「日本規模」か
2つ目は規模感である。
1つ目の条件だけでは、相手本位のベンチャー企業も存在するので、ベンチャーとスタートアップを区別する明確な条件にならない。
では、その違いを明確にする基準、条件は何か?
それが「規模感」である。
解決したい社会課題が世界なのか日本なのか。
日本でも最初から世界を視野に入れているのか。
ここがポイントだと思う。
世界のスタートアップは当たり前だが、世界規模のビジネスモデルを展開している。
世界を意識しないスタートアップは存在しない。
韓国も台湾もスタートアップが勃興している。
それらの企業は当然世界とビジネスをしている。
こうした企業のビジネスモデルは世界に通用するビジネスモデルなので、投資家も集まりやすい。
世界中の投資家が、「自分たちの国にこのビジネスが入ってきたら、こうなるだろう」と未来を描く。
夢を描く。
だから、お金が動く。
一方で自国規模だと、自国の投資家しかお金を動かさない。
世界中の投資家がイメージできないのだ。
すると、集まる金額も少額で、ビジネスの発展スピードも遅い。
これが世界のスタートアップがどんどん出来ては成長する、というサイクルが起きている理由の1つであると考える。
今世界は本当に狭くなっている。
日本の課題しか解決しないビジネスモデルではスタートアップと言えない時代なのだと考える。
世界を相手にビジネスをしているかどうか。
この一点がスタートアップとベンチャーの違いを明確にする基準ではないだろうか。
まとめ~「ベンチャー」で統一した方が分かりやすい~
「ベンチャー」も「スタートアップ」も元々同じような言葉である。
ビジネスモデルが革新的かどうかとか出口戦略がどうか、とか当たり前すぎて区別の材料にならない。
これまで見てきた通り、「ベンチャー」はそもそも和製英語である。
創業間もない企業を指しているので、スタートアップとほとんど似ている。
そんな状況で突然スタートアップが流行したので、これまでのベンチャーと何が違うのか分からなくなった。
正直言うと、ベンチャーもスタートアップも関係なく、「ベンチャー」にまとめてしまうのがよいと思う。
そもそも日本のスタートアップ企業と言われている企業を見てみると、正しくスタートアップ企業と言える企業は少ないように思う。
それであれば、紛らわしい言葉を増やすよりも言葉を減らしてスッキリさせた方が利便性が高い。
クリスマスだのハロウィンだのバレンタインだの、そういうのと同じように言葉を増やしてお金を巻き取ろうとしているようにしか見えないのだ。
とはいえ、スタートアップ企業を作ろう!みたいな動きが年々強くなっているので、これからもベンチャーとスタートアップは混在するのだろう。
もしスタートアップを目指すのであれば、世界のスタートアップに基準を合わせないのであれば、ただの言葉遊びと同じである。
ただの言葉遊びは人を惑わすだけであると申し上げたい。
それであれば、やはり「ベンチャー」に統一して使った方が分かりやすい。
今回色々調べて思った所感である。
皆さんのお役に立てれば幸いである。