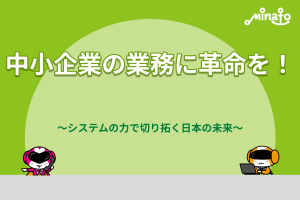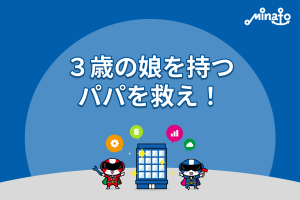COLUMN コラム
これまでも効率化がどれだけすごいかを伝えてきた。
今回は他社事例を紹介して、効率化がいかにどれだけすごい効果を発揮するかを伝えようと思う。
参考にする記事はこちらになる。
3年で「1万1000時間」の業務削減 創業103年の老舗メーカー、製造業特有の「DXの壁」をどう乗り越えた?
この記事を参考に効率化のすごさを伝えるとともに、効率化を行う上で重要な要素も伝えていこうと思う。
効率化の破壊力
営業部門の業務を対象にBIツールを導入したことにより、業務時間が15%(1万1000時間)も削減した事例である。
しかも、重要なのが売上が25%もUPしたということである。
効率が上がったので、営業ができる時間を確保することができ、営業成績も向上したのである。
至極当たり前ではあるが、なかなか効率化がこういう影響も与えることを知らない人がいる。
これは非常に悲しい。
読者の皆様には是非効率化をすることで業績も上がることがあるということを知っていただきたい。
現状は手作業まみれであった
さて、BIツールを導入する前はどうだったのだろうか?
営業マンは基幹システムにデータ入力をするが、実績集計はExcelを使って計算していたようだ。
その結果として、データ管理の属人化やブラックボックス化が進んでいたらしい。
各営業マンの実績を共有するためだけに会議を用意したり、その会議のための資料作成も必要で、営業に関係ない業務が発生していた。
月末になると、営業ではなく集計業務や報告資料作成業務が発生して長時間の残業が発生していた。
この文面だけでは、属人化やブラックボックス化の内容は不明である。
が、このように書くということは集計業務は各営業マンで計算方法が異なっているのかもしれない。
たとえば
田中さんはAという方式
山田さんはBという方式
鈴木さんはCという方式
といった感じで行っていたかもしれない。
このような状態だと各自が行っている集計方法が統一されていないために、属人的でありブラックボックス化している、とも言えるだろう。
この状態で最も怖いのは、集計方法が違えば本来は評価に値しないものも評価に値することになってしまうことである。
導入した結果どうなったか?
BIツールを導入する決め手は、リアルタイムの実績や全体状況の把握をすることが会社にとって利益になると判断したことだ。
このBIツールを導入したことにより
- 見積もり・受注件数や金額の進捗状況の把握
- 受注・売り上げ状況のレポート作成
- 他部門に開示する営業計画や週報の作成
- 各営業部員の能力の多角的評価
- 営業先のコンタクト分析
などを行うことができるようになったそうだ。
これにより報告のための会議が不要になったとのことだ。
集計業務を頑張らなくてもいいし、資料をわざわざ作らなくてもいい。
これまで一生懸命頑張っていた時間を本業に費やすことができるようになった。
さらに、データを見ることができるようになったため、より意思決定が円滑になった。
たとえば進捗が遅れている地域やクライアントがいれば、どのようにアプローチするべきかを検討し、実行に移すことができるのだ。
このようなアクションが重なることで、業績の向上に繋がったのだろう。
こうしたデータと情報は営業部だけではなく経営陣にも共有することが可能になり、経営陣の事業計画を策定する判断材料としても使える材料となったのも嬉しいところだ。
なぜ導入に成功したのか?
導入から定着までにかかった時間は3年である。
老舗であるため従業員数もそれなりにいる。
だからこそ、定着までの時間がかかるわけだ。
責任者の強い思いと意志があったからこそ実現できたと思う。
だが、記事の中で最もお伝えしたい成功要因がある。
それは「システムに運用を合わせる」ということである。
システムに業務を合わせていく考えが必要不可欠
今運用がこうなっているから、システムが我々に合わせてください。
このようなリクエストが多い。
これがまかり通るのは、自分たちでシステム開発をした場合のみである。
夢やロマンを詰め込むことができるのは、オーダーメイドだからこそである。
既製品に求めることではない。
そして、クラウドサービスは既製品である。
キントーンをはじめとしたノーコード・ローコードであっても同様である。
ある程度柔軟性を持ってはいるが、限界があることを知るべきである。
クラウドサービスは既製品として認識し、サービスに業務運用を合わせる意識を持たなければ失敗するのだ。
また、記事では
「私たちの業界でよく見られるのが、ナイフを使って切ることは自分の仕事だと思っていても、ナイフを研ぐことは自分の仕事だと考えていない──という姿勢です。言われた通りのやり方で仕事をしているけれど、もっと効率的にできる可能性があることに気づいていない。ナイフを研げばもっと早く切れるのに、今切れているからいいやと満足してしまう。そういう考え方が、製造業には多いのかもしれません」
と書いてある。
これは特に感じる。
効率化の話をしても、「今の業務運用で困っていないから特にいらない」と断ってくる。
だが、話を聞くと1つの業務に毎日5時間もかかっているという。
それ、10分になるけど、本当に不要ですか?
と聞くと、「別に5時間かけてやれば業務が終わるから、別に困っていない」と言ってくる。
意味が分からない。
今回の記事を読んで「すっきり」した。
なるほどと腑に落ちた。
錆びついたナイフでも切れるから別に研がなくてもいいし、新品にしなくてもいいと考える人が多いということなのだ。
愕然とする。
成功への道筋は「体験」
無理に推し進めても反発が出る。
すでに反対意見が出ているところに抵抗しても逆効果である。
そこで、採用した手順が「意欲的なところから始めて成果を出す」ということである。
成果が出ていて、便利さを事例として社内に共有する。
体験した人の口コミが反対しているところにも普及する。
すると、人は便利になりたい生き物なので、導入したいということになる。
この段階まで行くと、反対していた人たちが逆に「何故先にやってくれなかったのか」と文句を言ってきそうだ。
ともかく成功事例を示して便利さを実感してもらうというアプローチこそが遠回りのようでいて、成功への近道であるのだ。
まとめ
今回は他社事例を紹介した。
いかがだっただろうか?
ナイフの話があったが、今日常となっている業務が必ずしも最適解ではないのだ。
もしその業務を効率的に回したら、一気に目の前が晴れやかになる。
たとえば毎日3時間業務が10分になったら、3時間も時間を自由に使うことができる。
この3時間もの時間で会社の業績は上がる。
そんなはずないと思うだろうか?
毎日3時間である。
3時間×20日は果たして何時間か?
60時間である。
これを年にするとどうなるか?
720時間である。
こんなに時間を確保できるのに会社の成長をイメージできないなら、リーダーとしての素質がない。
ちなみに、記事ではExcelでの活用でブラックボックス化していたとあったが、実はそうではない。
BIツールを使わなくてもBIツールと同じ結果をExcelで作ることができる。
要は業務運用の仕組み化ができていないことと効率化をちゃんと行っていなかったことが原因で発生している事象である。
我々がもし依頼されたら、営業成績の集計と日次報告、月次報告などは簡単に指先1本でできる仕組みを作ることができる。
毎月160時間かけて作っていた経営会議資料がワンクリック10分で簡単作成
システムに運用を合わせることが難しいケースやBIツールの費用を捻出することができないケース、集計項目が変わることがあるケースなどは、システム側が企業に寄り添う必要がある。
こういった要望がある場合は、我々にお声がけいただけると嬉しい。
画面下部にフォームがあるので、そこからご連絡ください。
さて、今回のコラムはどうだっただろうか。
何か気づきや学びになれば幸いである。
最新情報はスタンドエフエムで投稿している。
もっと効率化について知りたい
ITニュースを簡単に知りたい
といった方は是非スタンドエフエムを覗いて欲しい。
加門の業務効率爆上げチャンネル
https://stand.fm/channels/6789dc300f71bf7aab885e79
それではまた次回のコラムでお会いしましょう。