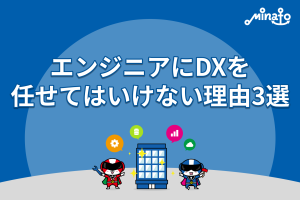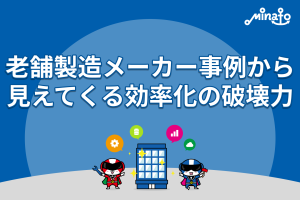COLUMN コラム
近年、IT領域において「内製化」をよく耳にする。
内製化こそが企業の競争力を底上げすることであるという主張だ。
確かに社内で要件定義・設計書作成・システム開発・テスト・保守運用という一連の流れを行うことができれば、自社内におけるシステムについては外部組織に頼らなくても済む。
こういう状況を作ることが先決である、という気持ちは分かる。
だが、こうした論調はノーコードやローコードを販売している企業が自らの商品を販売したいがためのセールストークである。
なぜなら内製化を行うことが大事であると伝えた上で、その難しさを伝え、その解決策としてノーコードやローコードを持ってくるという一連の「コンボ」が成立しているからだ。
IT企業の「あの手」「この手」の販売戦略に騙されてはいけない。
ノーコードやローコードで内製化できるのは夢のまた夢であり、実現するのはサービス提供者に依存する外注化でしかないのだ。
そこで、今回はノーコードやローコードを提供している企業の言い分に対して反論していきたい。
目次
内製化が抱える3つの現実的リスク
そもそも内製化は企業の力を損なう手法である。
先に紹介した通り要件定義から保守運用まで一貫して社内で行うことができるようになる、ということはシステム会社になるということだ。
システム会社になりたいのであれば、全然問題ない。
建築会社だけど、システム開発会社。
製造業だけど、システム開発会社。
人材派遣をやっているけど、システム開発会社。
違和感しかない。
じゃあ、広告はどうだろう?SNSは?ファイナンスは?営業は?
全部内製化するのか?
どれだけ大きな会社になるか、想像もつかない。
非現実的である。
それなのに、システム開発に関してのみ「内製化こそが正義である」と言ってくる。
そんなわけがないのだ。
では、内製化を行う上でどういったリスクがあるのかを見ていきたい。
大きく分けると3つのリスクがある。
- 人的リソースの限界
- スキル・知識の非対称性
- 技術進化への追従コスト
これら3つのリスクをそれぞれ見ていこう。
1:人的リソースの限界
中小企業やベンチャー企業は大手と違い、専門性に特化した企業である。
そのため、社員規模は少ないことが特徴である。
人材採用に課題を感じやすいのも中小零細企業の特徴だろう。
では、内製化を行うために採用活動に注力するだろうか?
エンジニアを1人採用するのに300万円投資しても0人なんて日常茶飯事である。
エンジニアの採用は本当に難しい。
となると、社内にいる人材を活用することになるが、非現実的である。
すでに多くの業務を担当している社員にエンジニアの教育をするとして、そんなことが可能だろうか?
既存の業務自体がなおざりになるだろう。
そもそもエンジニアとして活躍できるようになるのに、適正も必要だが3年くらいの期間が必要になる。
集中して3年も必要である。
生成AIが誕生して、その期間が短くなったかもしれないが、アウトプットされたソースコードが正しいかどうかの判断は人間がする必要がある。
エンジニアとしてのスキルがない人が行っても、それが正常かどうかを判断する術はない。
私は車について全然知らない。
もし生成AIと3Dプリンターを活用して車の部品を作ってもらったとしても、その部品がちゃんとした部品になるかどうかなんて判断できない。
これと同じである。
このように業務で手一杯なのに、内製化のために人を割く余裕はないのだ。
無理に内製化のために教育したとしても、そのコストはとんでもなく高くなる。
この非効率性を覚悟して飲むことができるのかがポイントとなる。
ちなみに、もしエンジニアになることができたら、私だったらその会社を辞めて、エンジニアとして勤務するだろう。
その方が収入も高くなるし、折角身に付けた手に職を無駄にすることはないからだ。
こうした危険性もある。
2:スキル・知識の非対称性
よく耳にする「内製化したらノウハウが社内に蓄積されます!」という言葉。
全くの無責任である。
一見正しいように見える。
しかし、そのノウハウを習得するのは難しい。
エンジニアのノウハウだからだ。
エンジニアでもない人がエンジニアのノウハウを提供されても分からない。
車がどう動くとか、マフラーがどうの、と言われてもよく分からない。
これと同じである。
セキュリティやシステム開発、AI開発などの専門的な知見が絶対的に必要になる分野において、プロと同じレベルで理解することができるだろうか?
非常にナンセンスだし、もしできるとしても何年かかるか分からない。
スピード感を出したいから内製化したい!と思っても、内製化した結果として停滞してしまうことになり、競争力の低下すらも招きかねないのが現実なのだ。
3:技術進化への追従コスト
そして、内製化で最も影響が大きいのは技術進化へ追従できないことである。
3か月前のAIと今のAIではできることが全然違う。
今日作った仕組みが半年後には時代遅れになることもある。
3年経つとセキュリティ的な問題が発生する。
このように都度都度キャッチアップして、改修やリプレイスを行うというのだろうか?
プロでもない限りそのキャッチアップは難しい。
エンジニアであれば、その価値を向上させるためにキャッチアップを行う。
企業側による協力もあるだろう。
しかし、システム開発会社でない企業がそのコストを肩代わりするだろうか?
その技術進化への追従コストを支払い続けるだろうか?
非現実的である。
となると、どうなるだろうか?
「レガシーシステム」の劣化版みたいなものが出来上がるのだ。
素人が作るレガシーなんて、目も当てられない。
内製化が正義であるというのは勘違い
内製化を進めたら、何でも自分たちでできるようになる。
そういう風に伝える記事やセミナーも多い。
しかし、何でもかんでも自分たちでやろうとすると、中途半端になる。
結果として非効率な状況に陥り、ライバルに競り負けてしまう状況を作りかねない。
確かに内製化ができたとしたら、その内製化した部分を事業として展開できるだろう。
広告なら広告会社
営業なら営業代行
SNSならSNS代行
といった形で新しいビジネスもできよう。
だが、それを求めているのか?
全然違う、経験もしたことのない分野に挑戦するのは果たして効果的だろうか?
挑戦した結果、失敗してしまうリスクの方が大きい。
内製化が正義であるとの考えは、弊害を巻き起こす
それならば、「外の知恵」を活用することは賢い戦略と言える。
そもそもDX領域で国が出している戦略として、中小企業は外部専門組織との連携が大事と主張している(デジタルガバナンス・コード)。
わざわざ社内で自分たちで頑張るのはナンセンスである。
内製化が絶対的な正義ではない。
冒頭でも伝えたが、何でもかんでも内製化してしまうにはキャッシュも人材も時間も必要だ。
そんな労力をかける暇があるならば、自らの専門性を特化していった方がいい。
ネジを作る会社がシステム開発を学ぶ時間を作るべきか?と聞かれたら、ネジを作ることに専念すべきだと回答する。
日本のネジは最高だ。
世界に誇ることができる。
システム開発なんて無駄なものに力と時間を費やさないでいただきたい。
もし使いたいと仰るなら、ぜひ弊社にお声がけいただきたい。
いくらでも協力する。
それくらい無駄なことなのだ。
自らの専門的な業務に関しては、自社で行うべきである。
それ以外の専門外の部分を自分たちでやろうとすると、調査だの学習だの時間がかかる。
それならば専門家に依頼した方が早い。
この視点を持っていただきたい。
最後に:内製化はただの幻想
今回のコラムはどうだっただろうか。
理想論を語るなら、確かに内製化した方がいいだろう。
社内でマーケティングできて、広告を打てて、開発もできて、WEB制作もできて、営業も強くて、セミナーもできて、何でもできる。
そんな状況が作ることができたら、最高だ。
それって大手じゃん、って思わないか?
全部自社で完結できる状態は確かに理想だが、理想だけで企業は動いているわけではない。
特に中小企業は大手と違って、リソース・人材・スキル・競争環境などに限界がある。
その制限された環境下の中で現実的であるかどうかを考えた時、内製化はいかに幻想的な話であるかが分かるだろう。
内製化に固執するのは、大きなリスクなのだ。
企業が目指すべきは、自らの専門性を高めつつ、外部組織をうまく活用することである。
外部組織の言いなりになるのではなく、ある程度の知識を持ち、うまく活用できる体制づくりが必要不可欠である。
この取り組みによって企業の競争力を高めることが可能になるのだ。
さて、今回のコラムが何か気づきや学びになれば幸いである。
最新情報はスタンドエフエムで投稿している。
IT関連の話題を別角度から見てみたい
ITニュースを簡単に知りたい
IT化やDX化の話題を学びたい
自分の会社が効率化ができるか知りたい
自分の時間を大事にしたい
といった方は是非スタンドエフエムを覗いて欲しい。
それではまた次回のコラムでお会いしましょう。