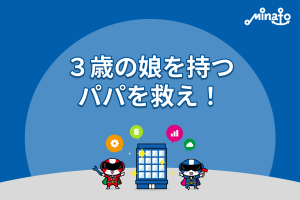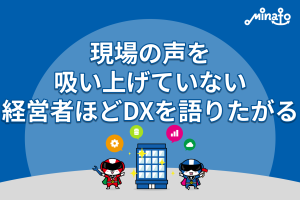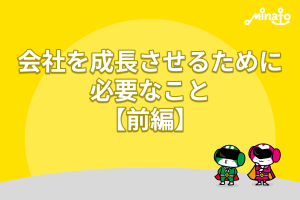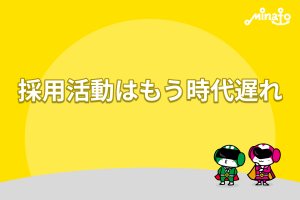COLUMN コラム
河北新報で「月1500時間業務を削減できた」 サイボウズ活用企業が仙台でDX先進例を報告という記事が公開された。
毎月1500時間も業務が減ったと聞けば、「すごい」と思う方もいるだろう。
だが、ここであえて申し上げたい。
その数字に騙されてはいけない。
こういった「インパクトのある数字」に騙された結果、ITに対して不信感を持ってしまった企業が少なくない。
これが、日本のDXの進展を妨げている大きな要因のひとつだ。
今回はこの事例を題材に、効率化の話題に触れるときの“読み方のイロハ”をお伝えしたい。
目次
1500時間は大した数字ではない
まず大前提として知っていただきたいのは、1500時間という削減時間は大した数字ではない。
効率化の現場であれば、これくらい実現して当然の数字である。
むしろ実現できないと恥ずかしいくらいだ。
その根拠として2つの事例から具体的に見ていきたい。
数字で見た方がより分かりやすいだろう。
パターン1:毎日3時間作業をゼロにした場合
たとえば毎日3時間の作業をしていた事例がある。
本件にかかる工数をゼロにしたら、月間でどれくらいの時間が削減されるだろうか?
答えは60時間だ(月20営業日換算)。
全然足りないと思うかもしれないが、組織は1人ではない。
これを10人がやれば600時間、100人だと6000時間だ。
1人3時間という小さな改善だったとしても積み重なると、非常に大きな数字になる。
本件だけでも容易く1500時間の削減は可能だということは、もうお分かりだろう。
パターン2:10人作業を効率化した場合
もう1つ別パターンを見よう。
ある業務を10人でやっていた事例だ。
本件は10人が8時間みっちり作業していた。
そのため、毎日80時間分の工数が発生していた。
さぁ、1人でできるようにしたら、どうなるだろうか?
8時間になる。
もしその8時間が10分になったら?
月間で換算すれば、その削減量は1600時間分の削減になる(実際は1597時間)。
効率化シーンではごく当たり前に起きることなのだ。
1500時間がすごいように思えること自体が危険
記事のような「1500時間」と聞くと、すごいと思ってしまうかもしれない。
確かに大きな数字に見えるかもしれない。
しかし、この程度の改善を「すごい」と思えてしまうこと自体が実は危険なのだ。
業務改善の世界では、9割削減なんて当たり前だ。
もはや「息をするように」実現してしまうのが効率化の世界であり、1500時間の削減なんて至極当たり前のことである。
これを非常識のように思うのは、裏を返せばどれだけ非効率な行動をしてきたのかを示している。
日本は世界的に見てITスキルがひぃくく、AI活用も遅れている。
この感覚のズレが現場の判断を狂わせてしまう。
だからこそ、「すごい」と思った時ほど一度立ち止まって冷静に判断すべきなのだ。
それは本当にすごいのか?
この視点を持つことが大事だ。
効率化はその後が大事
記事を読むポイントとは
では、こうした「効率化成果」を謳う記事を読んだ時に落ち着いて読むことができるようになるためには、どういったポイントに着目すべきだろうか?
ポイントは結構簡単である。
中身をしっかり論理的に判断することである。
- どの業務がどんな方法で、どれだけ削減されたのか?
- 削減された時間の有効活用は何か?
という2点で見るのがよい。
逆に言うと、この2点がはっきりしていない記事は信用できない。
もう少し詳しくお伝えしよう。
たとえば「10人でやっていた作業を1人でこなせるようにした」と書いてあったとしても、それがどんな業務であるか不明だと減って当たり前なのかどうかを判断できない。
もしかしたら手作業でやっていた紙への手入力を止めただけの効率化で実現しただけかもしれない。
数字だけを見れば「すごそう」かもしれないが、中身を見てみると拍子抜けレベルということも珍しくない。
だからこそ私は声を大にして言いたい。
「数字よりも実態が重要」である。
そこまでのデータが出て、ようやく「価値あるDX事例」と呼べる。
削減時間だけでは、空虚なる数字の羅列に過ぎない。
だが、実態はごまかすことができないのだ。
中小企業こそ数字に踊らされるな
こうした話に騙されるのは決まって中小企業である。
その結果、ITに対しての恐怖心や不信感が植えつけられる。
実態も背景も分からず、ただすごいと思った大したことのない数字に踊らされて導入したとして、うまくいくはずもない。
結局残るのは多額の導入コストだけである。
「DXって意味がない」と思うのは勝手だが、それはやり方が間違っているのに過ぎない。
だからこそ、中小企業はまず自らの立ち位置を把握することに努めるべきである。
- どの業務が非効率化?
- 人を入れ替えても対応可能な作業は何か?
- どこにITを入れるべきか?
- 社員教育を実施できているか?
これらを正しく把握してこそ効果的な改善ができる。
高額なシステムを入れる必要なんてない。
地道に、丁寧に、無駄をなくしていくだけでよいのだ。
この事実を今一度理解すべきである。
最後に
今回のコラムはどうだっただろうか。
もし「1500時間ってすごいかも!」って思っていた方が、記事を読む際の新たな視点を得ることができたとしたら嬉しい。
最新情報はスタンドエフエムで投稿している。
IT関連の話題を別角度から見てみたい
ITニュースを簡単に知りたい
IT化やDX化の話題を学びたい
自分の会社が効率化ができるか知りたい
自分の時間を大事にしたい
といった方は是非スタンドエフエムを覗いて欲しい。
それではまた次回のコラムでお会いしましょう。