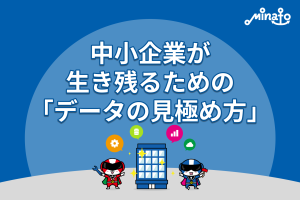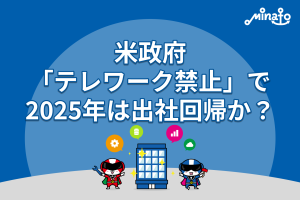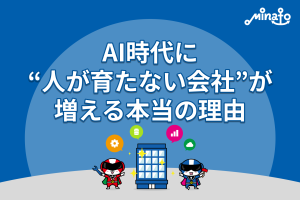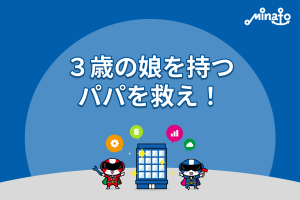COLUMN コラム
IT化、とりわけクラウドサービスの導入における失敗事例は枚挙にいとまがない。
クラウドサービスに特化した調査ではないものの、DX化の失敗確率を調査したレポートを見ると、その失敗確率は実に90%を超えるというのだ。
日本のDX化が実質的にIT化と同義であることを鑑みれば、IT化の成功確率は10%未満しかないと言わざるを得ない。
そして、失敗した企業にありがちな失敗理由として、決まって「サービスが業務に合わせられなかったから」というものが上位にランクインする。
クラウドサービス(DXサービス、あるいはITサービスとも呼ばれる)の導入失敗として他にも
- 「うちの業務は特別だから、IT化なんて無理だ」
- 「入れてみたが、サービスの方が業務に合わないから使い物にならない」
といった理由が、常に並んでくる。
しかし、こういった主張は、単なる言い訳に過ぎない。
言い訳以上でも以下でもないのだ。
今回のコラムでは、クラウドサービスの導入を成功させる秘訣について語っていこう。
現在、クラウドサービスの導入で苦しむ企業の参考になれば幸いである。
IT化とは何か?
そもそもだが、IT化とDX化の違いから見ていこう。
IT化とは、アナログ業務をデジタル製品に置き換えることによって、業務フローや管理体制を変更し、情報の共有難易度を低下させたり、業務効率を向上させたりする取り組みのことである。
IT化といっても多種多様であり、例えば以下のようなものが含まれる。
- システム開発
- ITサービス(またはDXサービス)の導入
- 業務効率化(自動化)
- デジタル化
その目的も多種多様だが、共通しているのはアナログをデジタルに変換することに他ならない。
一方で、DX化とは、デジタル技術を活用することでお客様に選んでもらえる企業になる取り組みのことだ。
例えば、
- お客様のニーズに合わせて企業そのものやサービスを進化させること
- 他社にはできない「自社」ならではの価値を強化すること
といったことをデジタルを活用して実行すること、それがデジタル・トランスフォーメーションである。
IT化はIT戦略における「守り」の対策と言え、DX化は経営戦略における「攻め」の対策と言えるだろう。
非常に勘違いされがちだが、DX化するためにIT製品を導入しなければならない、というのは大きな誤解だ。
DX化のためにわざわざITサービスを次々と導入する必要はない。
この点を勘違いすると、手痛い出費に苦しむことになるだろう。
もしDX化を目指してクラウドサービスの導入を検討しているのなら、そもそも方向性が違う可能性があることを理解すべきである。
クラウドサービスの導入によって得られるのは、基本的にIT化の恩恵に過ぎないのだ。
クラウドサービスの導入に失敗する理由
さて、IT化とDX化の違いを理解した上で、本題に入ろう。
クラウドサービスを導入する際、なぜ失敗するのか?
実は、根本的に二つの視点が欠けているからなのだ。
それぞれを解説していこう。
パソコンスキルの欠如が失敗に導く
当然のことだが、社員のパソコンスキルによって成否は決まる。
パソコンが使えない者に、高度なパソコンスキルを求めるサービスを使わせようとして、果たして上手く使えるだろうか?
ここで「YES」と答える者はいないはずだ。
フィギュアスケートでトリプルアクセルという大技がある。
では、アイススケートをしたことのない私が、いきなりその技を習得できるだろうか?
簡単な話だ。
絶対にできない。
おそらく、氷上で滑ることすらままならないだろう。
つまり、パソコンスキルがないにもかかわらず、導入しようと無謀な挑戦をするから失敗するのだ。
その前に、まずパソコンスキルの強化が不可欠である。
ちなみに、パソコンスキルの有無は人によって様々だ。
ネットサーフィンができることやYouTubeを視聴できることをもって「パソコンができる」と捉えている者もいるが、それはスマートフォンと同等の使い方に過ぎず、真にパソコンを使いこなしているとは言えない。
業務で触っているからといって、パソコンを使いこなせるとは限らない。
コピー&ペーストすら、満足にショートカットキーを使えない者も多いのが現実だ。
こうしたスキルの定義については、また別の機会に詳しく話そう。
ともあれ、パソコンスキルは、あらゆるIT導入の「前提」であることを決して忘れてはならない。
業務フローを見返さないと失敗する
そもそも、クラウドサービスは既製品である。
同じカテゴリのサービスであっても、それぞれが持つ「世界観」が違うのだ。
チャットツールだけでも、代表的なものを挙げてみよう。
- Chatwork
- LINE
- Slack
- Teams
- Google Chat
- Discord(最近では見かけるようになった)
これらはいずれも基本的な機能は同じでも、微妙な差異が存在する。
できること・できないことも異なり、通話の音質すら違う。
ショートカットキーも異なるため、ツールによって操作性も大きく変わってくる。
汎用的なものであればまだしも、専門性の高いサービスであればあるほど、この違いは顕著になる。
このサービスが持つ「世界観」に、自社の業務を合わせられるかどうかが、クラウドサービス導入の成否を握るカギなのだ。
少し話を変えよう。
既製品を使う際に、何に気を付ける必要があるだろうか?
分かりやすい例を出そう。
家具を購入したとしよう。
部屋に置こうとしたが、他の物があって置けない。
この時、あなたならどうするだろうか?
1.新しく買った商品を諦める
2.もともとあるアイテムを捨てる
3.新しく買った商品を置けるように、別の家具を購入してスペースを確保する
大抵の者は2か3を選ぶだろう。
クラウドサービスの導入で「うちの業務に合わない」と理由付けをする者は、1を選んでいるのと等しいのだ。
いかにそれがおかしなことであるか、ご理解いただけたはずだ。
主張の背景に何があるのか?
「サービスが業務に合わせられなかったから」
「うちの業務は特別だから、IT化なんて無理だ」
「入れてみたが、サービスの方が業務に合わないから使い物にならない」
これらの主張からは、「システムが俺たちの業務に合わせるべきだ」という傲慢な考えが見え隠れする。
だが、考えてみてほしい。
「製品が俺(私)に合わせるべきだ」と主張する顧客は、ただのクレーマーではないか?
この主張を、あたかも当然のように言えている時点で、もはや論外である。
そもそもITサービスは、パソコンの基本スキルを保有していることを前提としている。
この前提条件を満たしていない者が多すぎるということが、これらの主張の背景にあるのだ。
前提条件を満たす努力もせず、あたかも製品に欠陥があるかのように主張しているようにしか見えない。
これは、非常に恥ずかしいことである。
もし業界全体でそれが当たり前だというのなら、その業界全体が恥ずかしいと言わざるを得ない。
海外企業もできていないというなら、本当にそうだろう。
だが、大抵のケースで海外企業「は」それができているのだ。
そして、日本企業「だけ」ができていない。
これが恥でなくて一体何だろうか。
成功までの7ステップ
IT化は投資である。
投資である以上、その投資にレバレッジがあるかどうかを見極める必要がある。
このように考えた時、IT投資は経営者として行うべき投資なのだろうか?
答えは簡単で、「単独のIT投資は、投資すべきではない」となる。
しかし、視野を広く持つと、世界中の企業がIT化を推進しているのがわかる。
その先にDX化を見据え、さらにその先のAI戦略まで見据えているのだ。
ということは、日本の失敗率が高すぎること自体がおかしいのかもしれない。
では、どのようにすればクラウドサービスの導入を成功に導くことができるだろうか?
1つのアンサーをここに提示したい。
ステップとしては、非常にシンプルだ。
- パソコンスキルを強化する
- 既存業務を棚卸しする
- 導入サービスごとに、どのように業務を設計し直すのか検討する
- 小規模でのサービス実験導入を行う
- 導入結果を検証し、改善点を抽出する
- 問題がないことを確認し、改めて小規模でテストを実施する
- 小規模テストを繰り返し、最終的に社内全体の改革へと繋げる
上記のように、まずは小規模で実行するのが賢明だ。
そうすることで、最小限のリスクで試すことができる。
フィードバックが多すぎると対応しきれないが、少ない範囲であればある程度コントロールできる。
一気に全てを導入したい気持ちは分かるが、焦っても仕方がない。
少しずつ、段階的に実施することを強くお勧めする。
ただし、社員数が10名程度の小規模企業であれば、最初から全社的に実行するのも良いだろう。
最後に
今回のコラムはどうだっただろうか。
読者の皆様にとって、今回のコラムが何か気づきや学びになれば幸いである。
最新情報はスタンドエフエムで投稿している。
IT関連の話題を別角度から見てみたい
ITニュースを簡単に知りたい
IT化やDX化の話題を学びたい
自分の会社が効率化ができるか知りたい
自分の時間を大事にしたい
といった方は是非スタンドエフエムを覗いて欲しい。
それでは、また次回のコラムでお会いしよう。