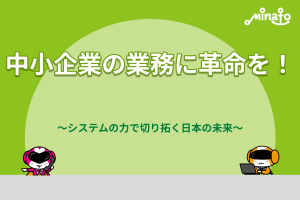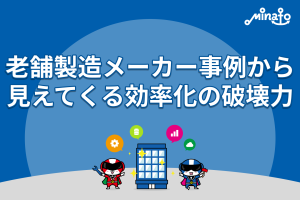COLUMN コラム
目次
「DX化」という言葉の違和感から探る、日本企業が本当に取り組むべきこと
昨今、あらゆるメディアで「DX化」という言葉が叫ばれている。
DXの成功体験をメディアが取り上げており、多くのIT企業が自らのサービスを「DXサービス」として提供している。
「DX化」の必要性を感じた
とても素晴らしいことだ。
だが、私はこの「DX化」という言葉そのものに、強い違和感を覚えるのだ。
その違和感の正体を探っていくと、日本企業が抱える根深い課題と、今本当に取り組むべきことが見えてきた。
本稿では、「DX化」と「IT化」の本質的な違いを解き明かし、言葉の誤解がもたらす弊害を指摘する。
そして、高価なツールに頼らずとも、明日から実践できる「真のDX」への具体的な道筋を示していこう。
なぜ「DX化」は不自然なのか?言葉に潜む根本的な誤解
まず、言葉の成り立ちから考えてみよう。
「IT化」とは、「IT(Information Technology)化」のことだ。
IT技術を導入し、アナログな業務プロセスをデジタルに「化け」させる。
これによって業務効率や生産性を向上させる。
非常にシンプルで、理屈が通っている。
では、「DX化」とは何か。
DXとは「Digital Transformation(デジタルトランスフォーメーション)」の略だ。
直訳すれば「デジタルによる変革」となる。
これを「DX化」とすると、「デジタルによる変革化」となる。
どことなく違和感があることがお分かりいただけただろうか。
もっと本質的な話をしよう。
私たちは「ボランティアをしましょう」とは言うが、「ボランティア化しましょう」とは言わない。
ボランティアはそれ自体が目的を持った「活動」であり、「化ける」ものではないからだ。
これと全く同じことがDXにも言える。
「デジタルトランスフォーメーションを推進しましょう」は正しい。
しかし、「デジタルトランスフォーメーション化をしましょう」には、強い違和感が伴う。
なぜなら、DXとは手段の導入ではなく、経営そのものの「取り組み」であり、「変革」を目指す経営戦略だからだ。
「変容する」という言葉はあっても、「変容化」という言葉はない。
DXは何から何に化けているのか。
DXは取り組みであるため、化ける要素がないのだ。
この言葉尻一つの違いに、DXの本質を理解しているか否かが表れていると私は考えている。
決定的に違う「DX」と「IT化」〜あなたはどちらを目指していますか?
この言葉の違和感は、多くの日本企業が「DX」と「IT化」を混同している現状の裏返しだ。
「DX」に取り組んでいるつもりが、その実態は単なる「IT化」に過ぎない。
このような悲劇的なケースが後を絶たない。
両者は目指す方向性が全く異なる事実をしっかり把握すべきだ。
IT化の目的:業務プロセスの「効率化」
IT化の主目的は、既存の業務プロセスをデジタル技術で置き換え、効率や生産性を高めることだ。
たとえば
- 紙の請求書を電子化して、印刷・郵送コストを削減する。
- 勤怠管理システムを導入して、手計算による集計作業をなくす。
- Web会議システムを導入して、移動時間を削減する。
これらはすべて、既存の業務を楽に、速く、正確にするための改善活動だ。
もちろん、これらは企業にとって重要であり、推進すべきものだ。
しかし、これはあくまで「守りのデジタル活用」であり、DXと全く違う。
コストダウンやリードタイムの短縮を実現することができるのが、IT化の特徴とも言えるかもしれない。
DXの目的:ビジネスモデルの「変革」と顧客価値の「創出」
一方、DXが目指すのは、デジタル技術とデータを活用して、これまでのビジネスのあり方そのものを変革し、新たな顧客価値を生み出し続けることだ。
それは、お客様に心から喜んでいただき、数ある選択肢の中から「あなた(の会社)がいい」と選んでいただける企業へと成長するための、攻めの経営戦略に他ならない。
世界を見渡せば、その本質を体現した企業がいくつもある。
たとえば
- 任天堂
元々は花札やトランプを製造する会社。
それが今や、世界中の人々を熱狂させるゲームとエンターテイメント体験を提供する企業に成長。彼らは単に商品をデジタル化したのではなく、「遊び」という普遍的な価値をデジタル技術で再定義し、新たな文化を創造した。 - Netflix
かつてはTSUTAYAと同じくDVDの郵送レンタルサービスが主力。
しかし、インターネットの可能性にいち早く着目し、動画ストリーミングサービスへと事業をピボット。
今ではオリジナルコンテンツを制作する巨大メディア企業へと変貌を遂げる。
彼らはレンタルという「手段」ではなく、面白い映画やドラマをいつでもどこでも楽しみたいという顧客の「欲求」に応え続けている。 - Tesla:
彼らの本質はバッテリー技術にあり、その技術力を体験してもらうためのショーケースとして電気自動車を製造。
今では、自動車保険やエネルギー事業まで手掛けている。
車を売るのではなく、「持続可能なエネルギー社会を実現する」という壮大なビジョンを、製品やサービスを通じて顧客に提供している。
これらの企業は、決して過去の事業に固執せず、顧客に新しい価値を提供するために、デジタルを武器に大胆な自己変革を断行した。
これは「化けた」のではなく、明確な経営戦略に基づく「変革」と言える。
IT化とは全く次元の違う話であることが、お分かりいただけるだろう。
日本のDXが進まない本当の理由
では、なぜ日本ではDXの本質的な取り組みが進まないのか。
私はその根源に、先述した「言葉の誤解」と、より深刻な「デジタル基盤の脆弱さ」があると考えている。
「自称DXサービス」に騙されてはいけない
「DX化」という言葉の曖昧さは、ビジネスの世界にも歪みを生んでいる。
多くのITベンダーが、自社のサービスを「DXサービス」と銘打って販売している。
しかし、その中身をよく見ると、そのほぼ100%が従来の「ITサービス」であると私は断言する。
業務効率化ツールや情報共有システムを導入しただけで、「我が社はDXを達成した」と満足してしまう。
これは、DXという壮大な目標を矮小化し、企業の変革の機会を奪う、非常にもったいない状況だ。
IT化すらおぼつかない日本のデジタル後進性
さらに深刻なのは、DXの前提となるIT化、そしてそれを支える国民のデジタルスキルが、世界的に見て非常に低い水準にあるという事実だ。
スイスのIMD(国際経営開発研究所)が発表した「世界デジタル競争力ランキング2023」において、日本は調査対象64カ国・地域の中で32位と、過去最低を更新した。
特に恐怖なのが、デジタルスキル・技術において最下位をマークしたことである。
モンゴルやバーレーン、トルコといった国々に日本は負けているのだ。
これは、DXを語る以前に、デジタル活用の土台そのものが揺らいでいることを示しています。
そもそもIT化すらおぼつかない企業が、その先のDXを実現できるはずがない。
デジタルという武器を使いこなすための基礎体力がないまま、いきなり高難易度の技に挑戦しようとしている。
これが、日本の多くの企業が直面している現実ではないだろうか。
IT企業ですら、このIT化とDXの違いを明確に顧客に説明できていないケースが散見されるのですから、事態は深刻だ。
中小企業のための「真のDX」入門〜Excel一本で世界は変わる〜
「DXには莫大な投資が必要だ」「デジタル人材がいなければ無理だ」。
そんな声をよく耳にするし、多くのレポートを見るとそう主張している人も多い。
しかし、日本の中小企業に、特別なIT投資は不要だ。
むしろ、IT投資は少なく行っていくことが大事だ。
そして、そのことを身をもって証明した企業がある。
それが、作業服の常識を覆し、アパレル業界に衝撃を与えたワークマンだ。
ワークマンが証明した「Excel経営」の威力
驚くべきことに、ワークマンの快進撃を支えたのは、高価なAIシステムや最新のSaaSではない。
ほとんどの企業に導入されているであろう、「Excel」だ。
彼らは「データ経営」を掲げ、全社員がExcelを駆使してデータを分析することを徹底したのだ。
たとえば
- 需要予測
各店舗の店長や社員が、自ら天候や地域のイベント、過去の販売実績といったデータをExcelで分析し、発注量を決定。
これにより、欠品や過剰在庫を劇的に削減。 - 製品開発
全国から集まってくる顧客の声(データ)をExcelで集計・分析し、「どの機能が求められているか」「どんな色が人気か」を徹底的に洗い出す。
そのデータに基づいて開発された製品が、次々とヒット商品となっている。
彼らがやったことは、高価なツールの導入ではなく、Excelを共通言語として活用する文化風習を築き上げたことだ。
Excelを単なる表やWordの代わりに使っているだけでは、Excelの真価を実感できない。
Excelは、データを蓄積し、分析し、経営の意思決定に活かすための、極めて強力な「変革ツール」なのだ。
最初の一歩は「人材教育」と「データ活用」
ワークマンの事例が示すように、真のDXの第一歩は、ツール導入ではなく「人材教育」だ。
社員一人ひとりを「データを読み解き、仕事に活かせる人材」へと育てること。
デジタル人材の不在を嘆き外に求めるのではなく、社内にいる人材を育て上げることが肝要である(ちなみに、デジタル人材は不可能である。IT活用できる人材で十分だ)。
社員がデータ読み、考え、次のアクションに繋げるスキルを持つ。
何と素敵なことだろうか。
そんな未来を作ることができれば、どんな会社でもDXを実行することができる。
「DX」という魔法のような言葉に踊らされる必要はない。
実態のないDXなんてする必要がない。
だいたいIT化とDXの違いを理解していない記事なんて参考にもならない。
足元を見てみよう。
あなたの会社にお客様に貢献できるデータはないだろうか。
まずはそういったデータを掘り起こし、経営に活かす地道な取り組みこそが、DXの本質だ。
最後に
今回のコラムはどうだっただろうか。
今回は「DX化」という言葉に違和感があると伝えたいと思って、書き始めた。
DXとは、経営戦略の1つであり、経営努力の1つだ。
どの企業も行うべき取り組みであって、「化ける」ものではない。
このことを少しでも多くの方に伝われば幸いである。
さて、最新情報はスタンドエフエムで投稿している。
IT関連の話題を別角度から見てみたい
ITニュースを簡単に知りたい
IT化やDX化の話題を学びたい
自分の会社が効率化ができるか知りたい
自分の時間を大事にしたい
といった方は是非スタンドエフエムを覗いて欲しい。
それでは、また次回のコラムでお会いしよう。