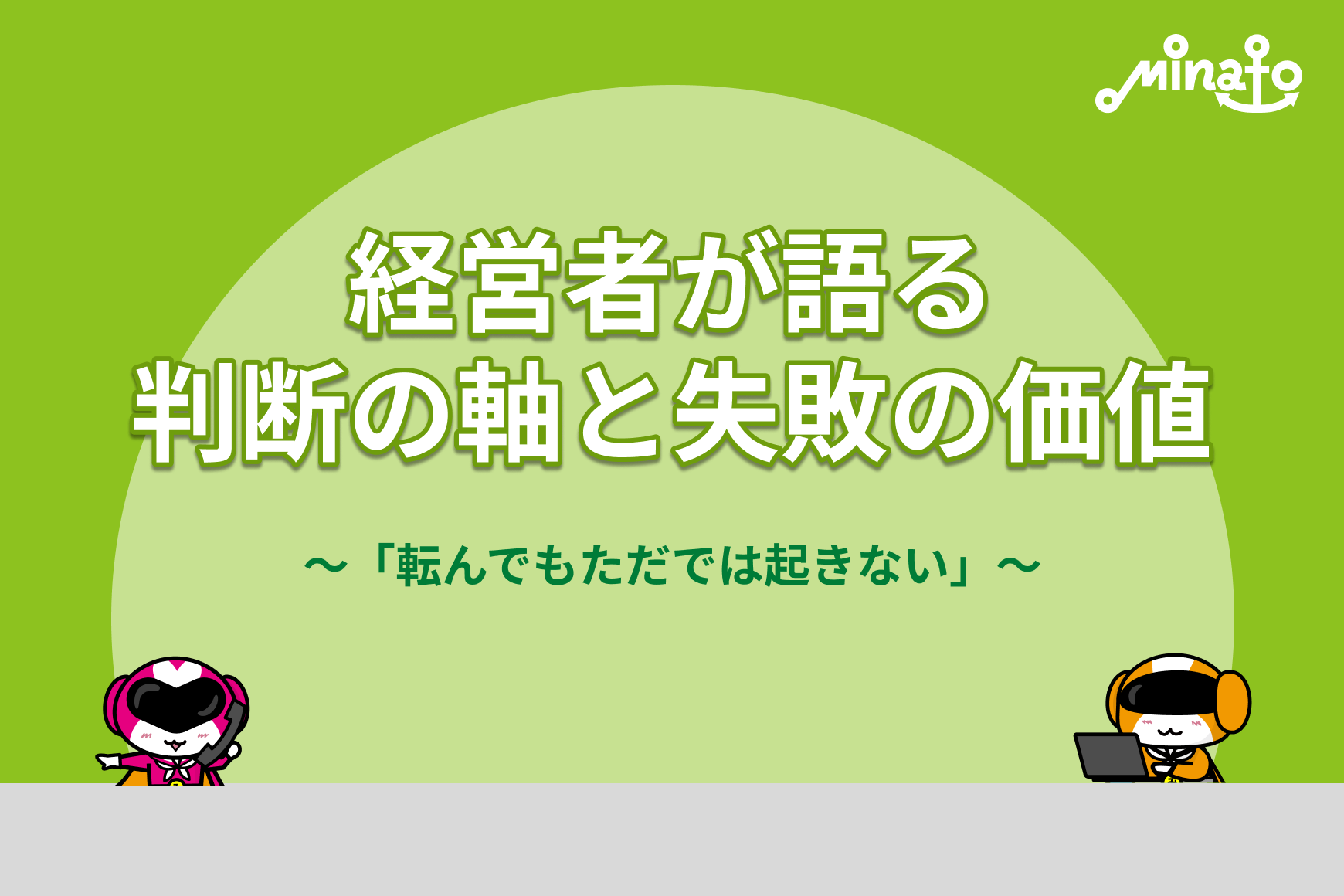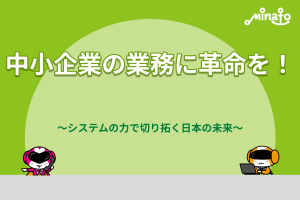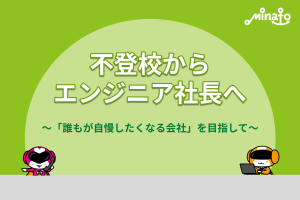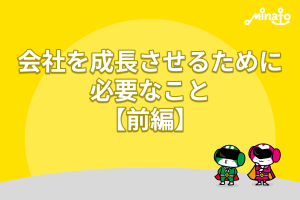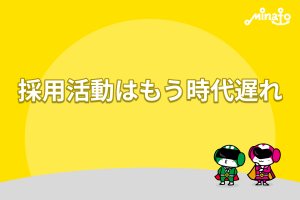COLUMN コラム
経営判断に迷ったとき、あなたは何を基準に選んでいますか? 目先の利益?コスト?直感?それとも「なんとなく」?
株式会社皆人の加門社長に、迷ったときの判断軸や”失敗”との向き合い方、そして経験をどう”投資”に変えていくかについて語っていただきました。
ひとつひとつの言葉に、ビジネスや人生に活きるヒントが詰まっています。
判断軸は「投資」か「消費」か?未来を見据える視点
迷ったときの判断基準を教えてください
最近本当に意識しているのは、「会社の成長につながるのかどうか」ということですね。
もう少し具体的に言うと、「投資なのか消費なのか」という視点で見極めるようにしています。つまり、今ここにお金や時間、労力をかけたときに、将来的に何か得られるものがあるのかどうか、という判断です。
たとえば、新しいことを始める、講座に参加する、採用をかける時に「これはリターンがあるのか?」と考えています。正直、それが100%成功するかなんて分からないですけど、意識しているかどうかで、だいぶ違うと思うんですよね。
投資と消費は、どのように見極めているのですか?
正直、めちゃくちゃ難しいです。つい最近も、ある講座を受講して完全に「消費」だったなって思ったんで(笑)。
ただ、判断のポイントは明確にしています。「その中で、何か得られたかどうか」なんですよね。お金でもスキルでも、行動の変化でもいいんですけど、「何か持って帰れたか?」がすごく大事。
甘いものを食べるという単純な例で言うと、それがただの間食なら「消費」だけど、それを食べたことで集中力が上がって仕事が捗ったら「投資」になる。そのくらい、判断の基準は結果ではなく、意図と活用の仕方なんです。
経験を「投資」に変える力
そういう考え方ができるようになったきっかけはありますか?
大きなきっかけがあるわけではないですが、ある意味「転んでもただでは起きたくない」という考えが根っこにあります。
失敗しても、「何かひとつでも拾って帰る」という感覚というか。
つらい経験や、一見マイナスに見える出来事でも、「ここから何を学べるか?」という視点に立てば、長い目で見て必要な経験だったと思えるんです。
僕自身、まだ完璧にできているわけじゃないけど、そういう視点を持てるようになってから、物事の受け止め方も変わってきたなと思っています。
その視点があると、「消費」をあとから「投資」に変えることもできそうですね。
本当にその通りだと思います。
その瞬間では「あ、これ失敗したな」「ただの消費だったな」って思ったことでも、後で振り返って、それをどう活かすかによって、投資に”変えられる”ことってあるんです。
実際、僕も「これは失敗だった…」っていうことはいくつもあります(笑)。でも、「これを無駄にしないぞ」という意志があるかどうかが分かれ目かなって。
「これは消費だったな…」ってへこむんじゃなくて、「いや、ここから投資に変えてやる」って行動すること。それができるかどうかが勝負かな、と思いますね。
「失敗は成功の母」逆境から学ぶ思考法
失敗に対する考え方を教えてください
「失敗は失敗じゃない」って思っています。
エジソンが「そんなに失敗して辛くないのか?」って聞かれて、「うまくいかない方法をいっぱい見つけただけだよ」と答えた話、あれ本当に名言だなと思っていて。
僕の場合は、「テスト思考」で考えるようにしています。「これをやったらどうなるかな?」という仮説を立てて試して、うまくいかなかったら「ひとつ検証できた」と捉える。
データ収集の一環だと思えば、失敗も成果なんです。
失敗を前向きに捉えるのは大切ですね。でも、実際には失敗にはリスクもありますが、どこまで許容しているんですか?
僕の場合、判断基準はシンプルで、「死んじゃうかどうか」ぐらいしか見ません。
今このまま経営してたら会社が潰れてしまう、社員の生活に影響が出る、という状況だったらダメですけど。そうじゃないんだったら、ある程度は許容していますね。
すべてのことが、その瞬間に投資になるとは思えない。いや、なる人もいますよ。なる人もいますけど、そうならない人の方が大半だと思うんで、それだったらもう長い目で見た方がいいかなとは思います。
その考え方に至ったきっかけは何だったのでしょう?
これは本当に少しずつ、ですね。元々は全然そういう考え方ではありませんでした。むしろ、失敗したらすぐ引いてしまう側の人間です。
小学校の頃なんですが、補助付き自転車に乗っていたと思うんですね、最初。その後、補助を外すと思うんですが、僕は盛大にこけたんです。この後、普通の子どもだったら、諦めずに乗り続けると思うんですが、僕は3年くらい自転車に近寄らなかったんです。それくらい失敗が嫌いでした。
そうした自分が変わった最初のきっかけは、やはり不登校の頃ですね。不登校といえば、社会的に失敗の象徴ですよね?でも、我が家では家族の絆が深まった人生のターニングポイントだったんです。両親に深く感謝するようになったのも、不登校があったからです。その瞬間は失敗だったかもしれませんが、長い目で見ると、人生の転換点であったという話はよく聞く話ですよね?
しかし、人間は繰り返すものです。失敗は悪いことではない、という認識はあったのですが、社会人になって、社長という重い責任を負うようになった僕は、失敗しないようにと思って経営をしてきたなと思います。失敗を恐れるようになったんです。
でも、多くの方にお会いしてお話を聞いて学ぶうちに、このままではいけないと思うようになりました。多くの学びが僕を変えたと言えます。たとえば自分では成功すると思ったことも、失敗することがありますよね?その時に「なぜダメだったのか?」という理由を考えるようにしています。
もちろん、今でも完璧にできているわけではありません。それでも挑戦してみるんです。まずは反省してみる。何か1つは原因を探し出す。そういう取り組みが自分の成長に繋がっていくんです。最初から何でも上手くいく人なんていません。すごい人でも何回も失敗している。平凡な私ならその数はもっと多いでしょう。そこは失敗を繰り返すしかないと割り切って行動するしかないと思います。
うまくいかないと感じた瞬間、「どう行動するか」が大事なのでしょうか?
そう思います。
失敗だったなと感じたその瞬間に、「やっぱりダメだったから、もうやめておこう」と諦めてしまったら、長い目で見たときに何も残らないんですよね。もしかしたら、それは良い成果にたどり着くための一歩だったかもしれないのに、自分で歩みを止めてしまうことになる。
「後で振り返らないとわからない」っていうのが本当のところで、その一瞬はダメだったって思うかもしれないけど、それが後々振り返ってみたら転換期だったかもしれないし。あの経験があって、あの時に悔しい思いをしたから、今の私がある、そういうこともあるんです。
学びに年齢は関係ない。若い世代から教わる成長のヒント
これまで出会った中で、印象的だったのはどんな方ですか?
特に印象的だったのは、現在の20代の経営者たちですね。
僕がようやく掴んだ感覚を、もうサラッと語っているのを見て、「すげー!」って感動します。
「教わる立場」って、年齢じゃないなって思います。10代の子でも、ふとしたひと言がめちゃくちゃ刺さることがあるんですよ。だから、素直に学ぶという姿勢はずっと持ち続けたいなと思っています。
やはり、学びに年齢は関係ないのですね。
ないですね、本当に。「年下には学ばない」って思っていたら、成長が止まっちゃいます。
だって、年齢って毎年更新されていくし、上の世代はいずれいなくなるんですよ。そうなると、教わる相手がどんどん減っていく(笑)。
しかも最新のビジネスやテクノロジーは、若い世代が一番早くキャッチしている。だから、10代・20代・30代の人たちからどんどん教わっていかないと、本当に置いていかれるなと思っています。
変なプライドを持って学びのチャンスを失ってしまうくらいなら、そんなプライドを持つべきではないと思います。
特に経営者である以上は、誰からでも学ぼうという姿勢が大事なのではないでしょうか。
*****
お話を聞いて印象的だったのは、「転んでもただでは起きない」という姿勢でした。失敗も経験として拾って、あとから投資に変えていく。その視点があるだけで、物事の見え方がまったく違ってくるんだなと感じました。
「失敗してもいい。その先にどうつなげるかが大事」——今まさに何かに迷っている方にも、きっと刺さる考え方があるのではないでしょうか。