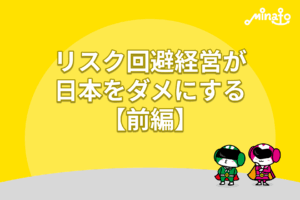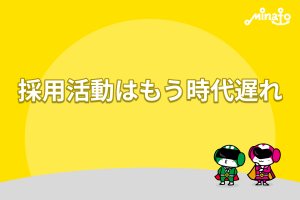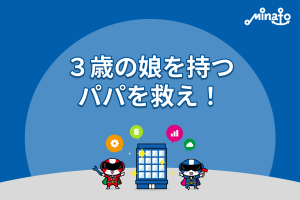COLUMN コラム
経営者の集まりでITの話をする機会があった。
ただ自己紹介をしただけなのに、なぜか「うちはこれまでのやり方でやってきたから」と予防線を張られたのだ。
「これまではこうだったから、弊社では変化する必要がありません」と自己主張をしている。
この手の経営者は、自らの手で自分の首を絞めているようなものだ。
別にIT製品を導入しろと言っているわけではない。
彼らの思考停止ぶりに、強い危機感を覚えろと言いたいのだ。
今回は、この主張がいかに危険であるのか、そして、この主張を行う経営者の特徴について見ていく。
目次
今という時代は常に変化する
まず「これまではこうだったから」という言い訳は、今まで慣れ親しんだやり方を変更することに抵抗を感じているのに過ぎない。
どう考えても、この結論に至る。
市場は常に変化しており、その変化に対応していく必要があるのは当然だ。
電話交換手という職業を、今も専業でやっている者がいるだろうか?
それをメイン事業としている会社など、存在するだろうか?
パソコンが到来する1995年以前と以後で、働き方は激変し、新たな職業も飛躍的に増加した。
エンジニアが民主化されたのも、まさに1995年以降のことである。
市場は常に変わり続けており、10年というスパンで見ても、その変化は非常に大きい。
テレビの世界においても、10年前の表現方法と今の表現方法では大きく異なる。
日々、微々たる変化が積み重なって、やがて大きな変化となるのだ。
今起きている大きな3つの「変化」
強烈なインパクトを与える「AI」
今の時代を見てみよう。
AIが本格的に到来した。
AIは、かつてのパソコンの到来と同じレベルのインパクトを持つ。
これまで効率化が困難だった、より生産的な業務領域にまでITが踏み込んできたのだ。
たとえば、以下のような業務である。
- テンプレートを使えないメール作成
- 会議内容から議事録とタスクを抽出
- 簡単な画像作成
- 簡単なシステム開発
- ユーザーが求める資料の調査
- 簡単なスライド作成
これらの機能は、およそ3か月に一度のペースで進化し、私たちの生活に影響を与え続けている。
国が調査した2024年度のAI使用率を見てみると、日本ではわずか9%しか使用されていないのが現状だ。
世界的に見ると、30%~50%はすでに使用されている。
日経新聞によると、タイが世界トップの使用率で90%を超えているというから驚きである。
AIの使用は、私たちの働き方を大きく変え、インターネットが到来した時と同様の大きなインパクトを与えるだろう(その前に、日本はそもそものパソコン基礎スキルの強化から始める必要がありそうだが・・・)。
日本経済が縮小している現実
他に何があるだろうか?
人口減少がある。
毎年80万人という人口減少が起きているのである。
大きすぎてピンと来ないだろうか。
都道府県で見れば、山梨県が毎年消えるほどのレベルである。
大したことないように思うだろうか。
1つの国が毎年滅んでいるのと同じくらいのインパクトがある。
それくらい80万人というのは大きな数字なのだ。
「2025年問題」「2030年問題」「2055年問題」と、人口減少をきっかけに起きる様々な問題が取り沙汰されている。
近い将来、10人いたら5人は高齢者という社会になるのだ。
先日、日経新聞から出生率が過去最低を記録したとニュースが発表された。
人口が減少するということは、すなわち、顧客がいなくなるということである。
日本経済はますます縮小していく。
それは、日本という国だけで経済を回すことができた時代が終わりを告げることを意味する。
韓国や台湾と同じく、自国だけでは経済を回すことができず、世界経済に取り込まれなければ生き残れない状態になるだろう。
韓国や台湾は最初からその状態であった。
だから試行錯誤して経済発展に挑戦してきた。
日本はぬるま湯に浸かっていた。
韓国や台湾のように世界経済で戦える土壌がない。
すでに世界一安全な後進国なのに、さらに経済の悪化が起きてしまうかもしれない。
客層が外国人になる近未来
まだある。
外国人労働者の存在だ。
日本人の人口が減少している。
そのため、労働力が不足し、日本経済が成り立たなくなりつつある。
だからこそ、外国人を日本に誘致し、労働力を補い、日本経済の崩壊を遅らせようとしているのが実情だ。
顧客層が日本人しかいないという世界から、外国人も含まれる世界へと変貌する。
あらゆる面で日本人とは異なるため、多くの点で見直しが必要となるだろう。
日本人だから受け入れてもらえたことが、外国人からすれば魅力的に思えない、といったことも起こるはずだ。
外国人の文化、宗教、風習、背景などを深く理解し、彼らに適切なアピールを学んでいく必要があるのだ。
ここで、興味深いデータがある。
日本人の人口は毎年80万人ずつ減っている。
一方で、日本国の総人口は毎年50万人ずつ減っている。
もう一度言う。
日本人は80万人ずつ減っているが、日本国の総人口は50万人ずつ減っているのだ。
つまり、人口減少の差額30万人分は、外国人による社会増減で補われているのである。
総務省統計局のデータによると、
- 自然増減は89万人減
- 社会増減は34万人増
- 外国人は34万人増
- 純増減は55万人減
となっている。
データを見る限りでは、2016年から10万人を超える外国人が入国、2022年は約17万人、23年は約24万人、24年は34万人と純増しているのが現実だ。
日本人は減っているのに、外国人ばかりが増えている。
「10人に4人は高齢者の社会が来る」と言われているが、近い将来「10人に6人は外国人」といった社会になる可能性すらある。
このように、簡単に今起きていることを3つ挙げただけでも、放置してはいけない問題ばかりなのだ。
変化を恐れる経営者は死ぬ
では、改めて問おう。
このままで本当に大丈夫か?
まだ「これまではこうだったから」と言い訳する気か?
私たちは「時代」に生きている。
これまでは10年スパンで振り返った時、大きな変化に気づいた。
これからは10年もいらない。
5年あれば十分だ。
たった5年で社会は大きく変貌していることだろう。
そんな時代にあって、変化をしないという選択は、もはやリスクでしかない。
時代に取り残されないために、常に変化が求められる。
変化していかないと、企業として生存できないのだ。
人もまた動物である。
変化は「死」を想起させる。
生存戦略において変化は恐怖である。
しかし、その恐怖を克服し、戦うことこそが経営者の宿命である。
とはいえ、いきなり変化をしろと言われても、人間はすぐに変化できない。
そこで、変化のための1つの考え方をお伝えしよう。
生き残るための簡単な変化術
明日から100%変化することは無理だ。
どんなに天才であろうとも不可能である。
そもそも長続きしない。
長続きさせることが重要なのだ。
身近な例でたとえよう。
「ダイエットしよう!」と意気込んでも、ダイエットに失敗する人が多い。
これはなぜか?
長続きしないからだ。
継続こそ力である。
では、長続きしたいならどうすればいいか?
答えは簡単だ。
超絶シンプルだ。
「ちょっとずつ」変化することだ。
誰でもできる長続きのコツ
前回と比べて20%ずつ変化をするように小さくコツコツとやることだ。
企業で言えば、毎年20%変化を行っていく。
すると、5年経つ頃には、自分でも驚くほど大きな変化となっているはずだ。
大手企業でも10年経つと全然違うビジネスをやっている、ということが多い。
これと同じで私たちも経営者である以上は、毎年20%ずつの改善を心掛けるのがよいのだ。
しかし、「20%」といっても、具体的に何をすればよいのか難しいと感じるかもしれない。
そこで、毎月、毎週、毎日というスパンで前回と違う取り組みをやってみることを強くオススメする。
年次計画書を作られている方は、年、半年、四半期という単位も取り入れよう。
計画書を作られていない方は、まず週単位で取り組んでみよう。
簡単なステップを書き出したので参考にして欲しい。
- やることリストを出す
- 実行する
- やったことを記録する
- 反省する
- 改善ポイントを1つ出す
週単位の場合は、
- 今週やることをリスト化し実行する
- 実行した結果の改善ポイントを1つ出す
- 翌週やることをリスト化する際に、改善ポイントを加味する
といった感じだ。
先週の行動から何を改善したら、もっとよい自分に成長できるかを1つ出すことから取り組むといいだろう。
慣れてきたら、月単位や日単位でもやってみよう。
日単位での取り組み方
月単位は週を月に変更するだけなので、比較的簡単だ。
だが、日単位はスパンが短いので、少しコツがいる。
毎日やる時は日記を付けるといいだろう。
昨日の行動を反省し、何をどう改善すればよかったかを1つ出す。
その1つを今日やる。
そして明日になったらまた反省し、改善ポイントを1つ出す。
これを繰り返す。
たったこれだけで、人は大きく変化する。
改善ポイントは、別に大袈裟なものでなくてもいい。
「ポモドーロができなかったから、しっかり時間管理をやろう!」といった、結構ゆるいものでいい。
日本人は真面目だから、ついつい頑張り過ぎてしまう。
自分に厳しくしてしまい、長続きしないことが多い。
自分に甘くていい。
三日坊主も100回やったら、300日だ。
かなり適当でいい。
適当でもいいから継続することの方が大事なのだということを覚えておこう。
昨日の自分より今日の自分の方が成長する、という状態を作り上げていく。
10年後にいる自分は今の想像をはるかに超えた先の自分であることだろう。
改めてステップを整理しよう。
- やることリストを出す
- 実行する
- やったことを記録する
- 反省する
- 改善ポイントを1つ出す
たったこれだけである。
挑戦してみて欲しい。
さて、ここで1つ言いたいことがある。
「反省」という言葉を後悔するみたいなイメージで捉えている人がいるが、正しくは「行動やあり方を振り返って、その可否を改めて考えること」である。
反省なき行動は同じ失敗を繰り返すことを肝に銘じよう。
最後に
今回のコラムはどうだっただろうか。
読者の皆様にとって、今回のコラムが何か気づきや学びになれば幸いである。
最新情報はスタンドエフエムで投稿している。
IT関連の話題を別角度から見てみたい
ITニュースを簡単に知りたい
IT化やDX化の話題を学びたい
自分の会社が効率化ができるか知りたい
自分の時間を大事にしたい
といった方は是非スタンドエフエムを覗いて欲しい。
それでは、また次回のコラムでお会いしよう。