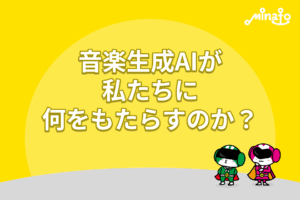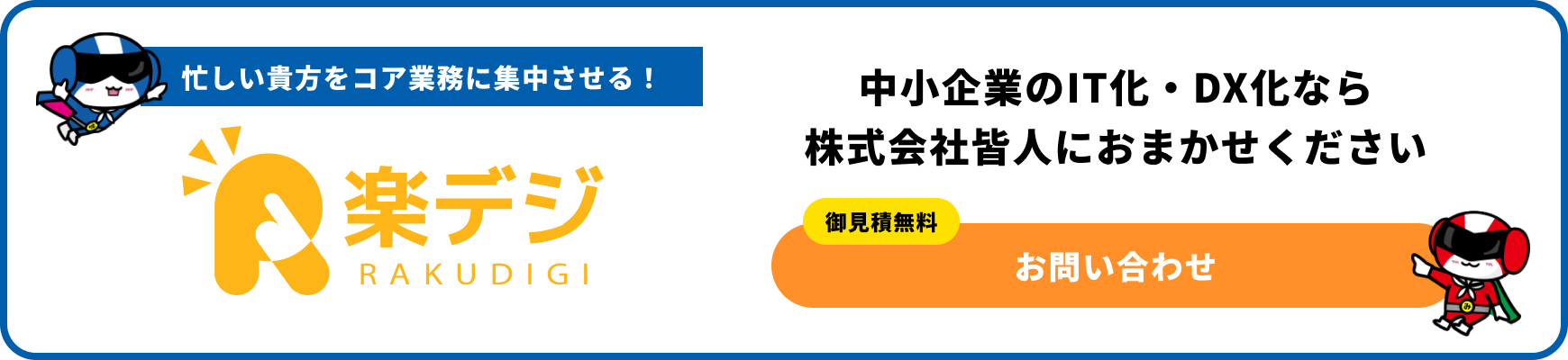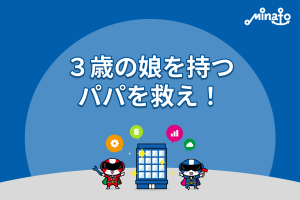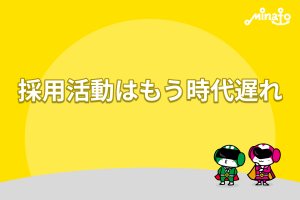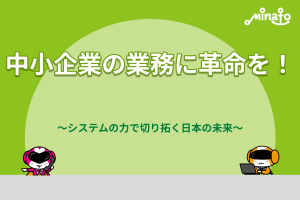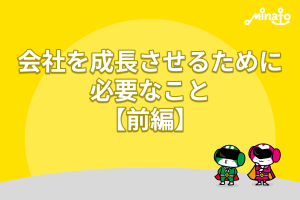COLUMN コラム
先日セミナーを受けた。
何人かの講師が登壇する形式で、いろんなことを教えていただいた。
ただその中で「AIは皆さんの仕事を奪うんです」と危機感を煽ったトークをしている方がいた。
最近この手のテーマは大人気だ。
書籍まで出版されている。
だが、なんとも無責任なことを言う人だなと思ってしまう。
この人が言うには、パーソナルトレーナーは不要になるらしい。
一方で看護師や建築家は残るらしい。
だが、看護師こそITの技術で不要になるだろうし、建築も中国では全自動の試みがなされている。
日本でも今や工場で作ったものを現場でブロックのように組み立てているだけの工法もある。
AIに仕事を奪われてなくてもITに仕事を奪われてしまうのではないか?と思う。
一方で、日本人はどちらかというとコミュニケーションをすごく大事にしたい国民性があるので、パーソナルトレーナーは不要にならないのではないか?と思う。
看護師もこれに当てはまるが、別に病院に行ってコミュニケーションしようと思わない。
もしコミュニケーションをするなら、医者とするだろう。
このように一部だけでも矛盾した部分が見受けられる。
そもそもこういった話は何も最近になって始まったことではない。
そこで、今回は「〇〇は仕事を奪う」について考えてみたい。
そもそも「AIが仕事を奪う」は昔から言われていた
そもそもの話なんだが、「AIが仕事を奪う」という話は1950年代からすでに言われていた。
AIがこの世の中に誕生したのは最近の話だが、1950年代にまで遡る。
今でこそよく聞く「ディープラーニング」も1980年代にその基礎が出来上がっている。
将棋や囲碁の世界にAIが参入したのも2000年より前の話だ。
このように何も今になって突然AIが誕生したのではない。
AIが誕生した頃からAIによって人間は仕事をしなくてもよくなる、と期待されていた。
そのため、映画や小説、漫画などの創作の世界では機械が私たちの代わりに仕事をしてくれている。
私たちの想像では、もう随分昔から私たちは仕事の多くを機械に任せてしまっている。
人が想像できるものは実現できる、とよく聞くが、私たちが夢想した世界の一部がようやく実現しそうになってきているのだ。
「〇〇が仕事を奪う」はAIに限らない
それなのに恐怖している人が多い。
これは何故か?
これは現状維持の人であったり「なくなる」と言われる仕事に従事している人であったりするのではないか。
確かにこういった人は恐怖することになるだろう。
だが、考えてみて欲しい。
何も今に始まった話ではないのだ。
工場のロボット化
コンビニやスーパー、ファミレスなどでロボット導入が始まっています。
企業は人件費の削減をしたいんです。
結果、皆さんの仕事が奪われてしまうんですよ。
別に普通のことだ。
取り立てて騒ぎ立てることではない。
特に大手であればあるほど普通だ。
出資していただいている投資家の期待に応えるためにも上場企業は、常に前進を続ける必要がある。
売上や利益を上げる取り組みを実施するか。
企業内の効率性を向上させたり無駄を省いたりして利益率を向上させる取り組みを実施するか。
企業はボランティアではない。
新しい技術を取り込み、競争社会に勝っていかなければならない。
お客様に喜んでいただき、社会に貢献していかなくてはならない。
そもそも工場のロボット化はよくて、コンビニのロボット化はダメな理由は何か?
ファミレスで人が運んでくるよりロボットが運んでくる方が、料理をダメにするリスクも少ない。
ロボットを入れてダメなら、工場にロボットを導入している企業もダメではないか?
このように思うわけだ。
工場にロボットを導入する前と導入した後では、雇用にも大きく影響が出る。
今まで100人の雇用をしていた工場でロボットを導入して10人で稼働できるようになったとしたら、90人は解雇対象となる。
むしろ90人を採用し続けるなんて無駄である。
4人家族のご家庭で、2人の子どもが独り暮らしをしたのに、4人分のご飯を作るのか?
絶対に作らない。
その時々で最善の選択を行うべきだ。
自動改札機も同じ
電車の切符。
符を切る、と書く。
私が子どもの時はまだ駅員さんに切符を切ってもらっていた。
今は自動改札機がその仕事を代用している。
機械が仕事を奪ったのだ。
東京タワーも人力で作ったと言われている。
スカイツリーはどうか?
機械の力で作っている。
大工が減った理由は、大工の技術やスキル、ノウハウがなくても建築できるようになったからだ。
もちろん様々な理由はあるだろうが、簡単に家を建てる技術が出てきたら、そちらの方が優位になる。
産業革命からずっと続いている
こうした動きは産業革命からずっと続いている。
馬車も車が誕生して駆逐された。
飛脚もそうだ。
今ならメールやチャットで郵送できる。
電話も元々、電話交換手という仕事があった。
今では存在しない。
何なら電話も携帯電話の誕生で固定電話の普及率も低くなった。
NTTも社名を変更するかも、というニュースがあるくらいだ。
電話も進化して、今では顔を見ながら電話できるし、資料を投影しながら話すこともできる。
時代とともに仕事は消えるが、仕事は増える
このように私たちの仕事は、時代や技術とともに消えていっているのだ。
だが、消える仕事もあるが、増える仕事もある。
産業革命以降、仕事がなくなっては生まれ、生まれてはなくなりの連続である。
飛脚も仕事を失った。
だが、郵便という仕事が出てきた。
もしなくなっていく一方であるなら、この世の中は産業革命当時の人口から仕事量が増えないはずだ。
なのに、職業が増えていっているのだ。
こんな仕事もあるんだ、と驚くこともある。
そんな経験、皆さんにもあるだろう。
だからこそ、AIの普及でなくなる仕事もあるだろう。
だが、一方で新しく出てくる仕事もあるのだ。
また、結局プロには負けてしまう。
たとえば画像制作。
みなさんはプロだろうか?
プロの視点からこういう画像がよい、というのがある。
もしAIで作ったとしても、それがよいのかどうかは不明だ。
よいかもしれない。
悪いかもしれない。
この判断は素人では難しいだろう。
所詮は素人作品に過ぎない。
もちろん、技術の進歩によってもっと優れたAIが誕生するかもしれない。
だが、そうなったら、私たちは映画の世界と同じく機械に仕事を任せて、自分たちはもっとコアな業務に集中すればよいのだと思う。
まとめ
AIが来たら、仕事がなくなりますよ!
なんて無責任なのだろうと思う。
今起きていることは95年のパソコン到来と似ている。
その頃、誰もが「パソコンって何?」ってなった。
それから「パソコンが使えるってスゴイね!」って尊敬されるようになり、今では「パソコンが使えないのはヤバいよ」ってなった。
前はホームページを作れるだけで尊敬されたが、今では当たり前になっている。
技術は出たばかりは誰もやっていないが、徐々に当たり前の水準になっていくのだ。
この現象がAIでも起きると思う。
今黎明期で誰もが「AIって何?」ってなっている。
この時にパソコンと同じく学ぼうとしている人は、その後のキャリアに大きく差が出る。
こんな大事な時に「AIで仕事がなくなる」といった恐怖を煽る言葉を伝えるのは、本当にどうかと思う。
危機感や恐怖心を煽って、商品を売りやすくする。
何ともあくだいことだ。
本コラムを読んでいただいたからには、こういった「AIが仕事を奪う」トークをする人に気を付けていただきたい。
今回のコラムが何か気づきや学びになった方はシェアをしていただけると嬉しい。
また次回のコラムでお会いしましょう。