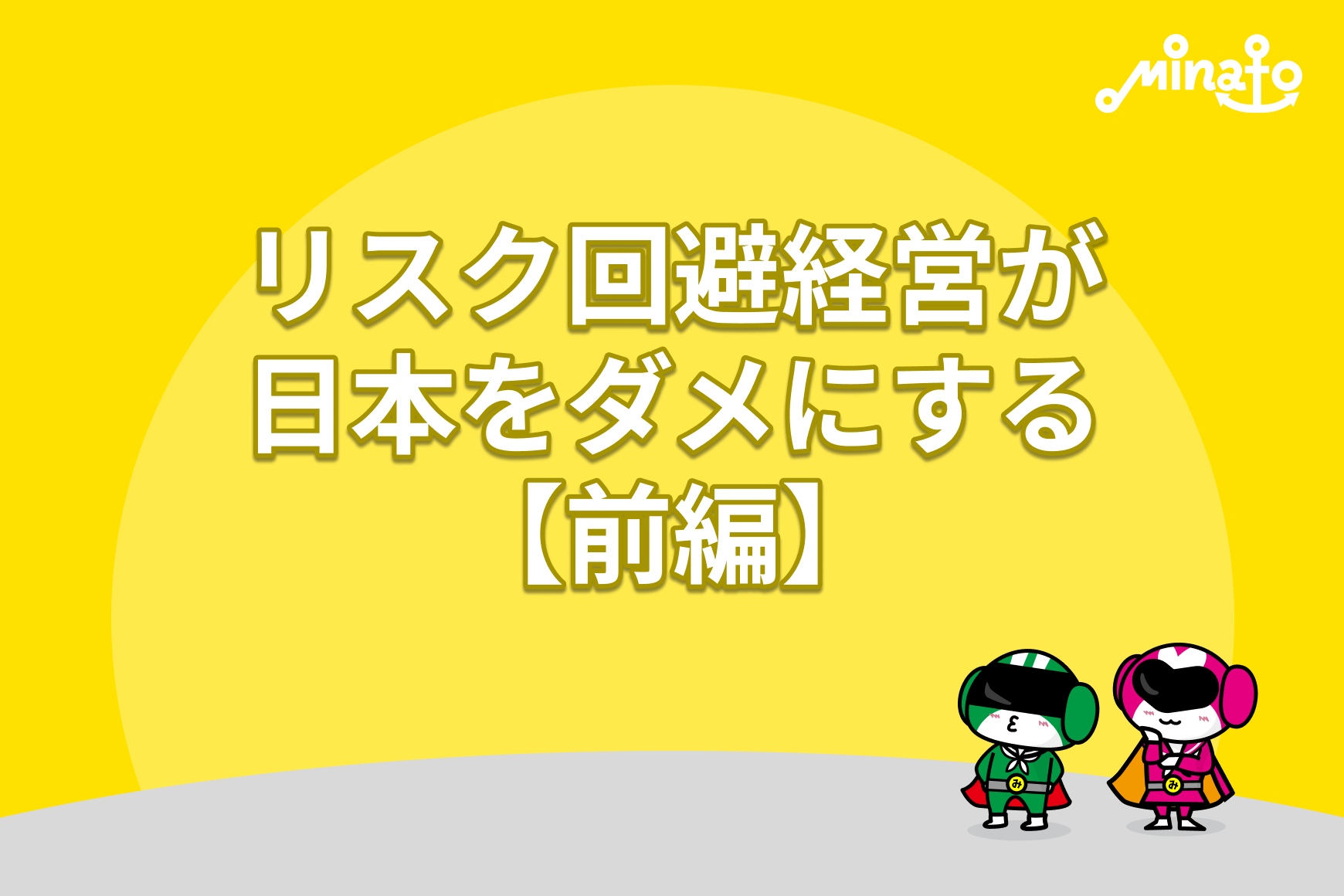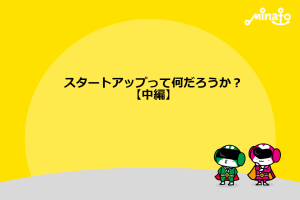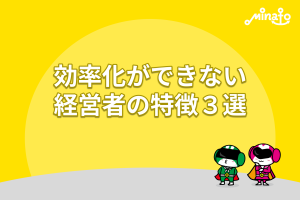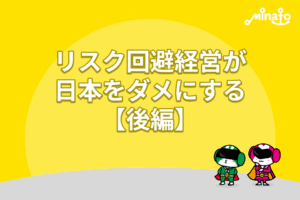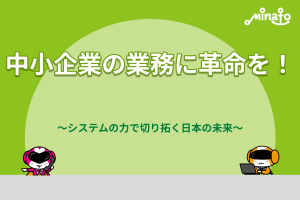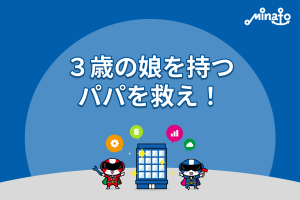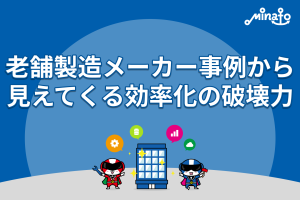COLUMN コラム
長らく「失われた30年」と揶揄される日本経済。
その根底には、日本企業特有の「安全運転」文化が深く根差していると言えるだろう。
内部留保を貯めるだけ貯めて、有効活用しない。
まるでタンス貯金だ。
特にリーマンショックやコロナショックを経て、その傾向はますます強まるばかりである。
もちろん、安定経営は重要である。
内部留保があったからこそ、コロナショックを生き残った企業も多い。
しかし、時にその「安全運転」が、本来生み出すべきイノベーションの芽を摘んでいるのだ。
そして、結果として成長の停滞を招いている現実に私たちは真摯に向き合う必要がある。
今回は、「なぜ、イノベーションが生まれないのか – 経営力に課題はなかったか – 」という論説に共感し、その中から是非伝えたい部分をピックアップしてお伝えする。
もちろん、そのままあなたにお伝えしても意味がないので、論説をベースにしつつ私の言葉でお伝えする。
オリジナルを是非読んでいただきたい。
リンクにしてあるので、上記からダウンロードをお願いしたい(J-STAGEというしっかりしたサイトなので、安心して欲しい)。
目次
停滞と背中合わせの“安全運転”文化
日本は、1980年代には「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と世界に謳われた。
世界は日本の黄金時代を指をくわえてみているだけであった。
日本は強かったのだ。
日本人は優秀だったのだ。
だが、その後のバブル崩壊を経て、長きにわたる経済停滞の中に沈み込んでいる。
かつての競争力を失い、IT化やデジタル化の波の中で、GAFAのようなグローバル企業に大きく差をつけられているのは、紛れもない事実である。
なぜ、日本企業は、当時実現可能な技術力を持ちながらも、iPhoneのような革新的な価値創造ができなかったのか。
そして、インターネットがもたらす膨大なデータの価値を認識し、それをビジネスモデルにまで結びつけることができなかったのか。
その根源的な課題は、技術力そのものよりも、むしろ、その技術力をビジネスモデルにまで結びつける「経営力」にあったのではないかと考える。
イノベーションとは、単なる技術革新に留まらず、技術を育み、市場への出口を創出し、社会を動かすという長いプロセスを経て成就されるものだ。
そのためには、科学技術力だけでなく、それをマネジメントする能力、すなわち企業経営全体に関わる経営力が不可欠となる。
データで見る日本の組織文化とリスクテイク不足
日本企業の経営者が、いかにリスク回避志向が強いかを示す、興味深い実証研究がある。
井上光太郎氏(2015)の「日米企業の経営幹部のリスクテイクの度合い」の比較調査では、日本企業の経営幹部は、米国に比べて楽観度が低く、非常にリスク回避的な姿勢が強いことが報告されている。
この傾向は、日本企業の組織文化が「集団主義」を重視し、「不確実性の回避」が高いという特徴にも起因すると考えられる。
集団主義はもはや呪いレベルである
集団主義とは、自らの所属する組織において調和や同調を重んじる傾向のことを指す。
「沈没船で弱者を先に脱出させるために、何と言えば優先してもらえるか?」という民族性を捉えた話がある。
そこで日本人は、「他の人もやっていますよ」と言うと黙って従うとされている。
他にも行列で黙って並ぶし、フードコートに鞄を置いて注文しに行っても盗まれない。
これらは、集団の調和や同調を重んじることによって得られたメリットである。
だが、イノベーションを起こす際は、こうした調和や同調を重んじる精神は足を引っ張る。
イノベーションとは、常識を打ち破る取り組みである。
そのため、「尖った人材」や「ルールを無視した取り組み」などに対する寛容性が重要になる。
残念なことに日本においては、そういった寛容性は低い。
日本人の根本に根差した集団主義は、自らが属する組織の平均値を取ろうと行動する。
そのため、日本人のパソコンスキルは一向に向上しない。
もはや病気と言っていい。
そんなことではイノベーションなんて起きるはずがないのだ。
リスク回避が過ぎる特徴が経営をダメにする
組織文化の問題も大きいが、経営上において更に影響度が高いと言えば、リスク回避傾向が高いことだ。
石橋を叩きに叩いて、結局渡らない。
そんな経営が日本の至る所で見られるのだ。
蟻川靖浩氏ら(2016)の研究では、他国と比較して、日本の経営者のリスクテイクの低さが、企業の付加価値創出を示すROA(総資産利益率)やROE(自己資本利益率)の低さ、つまり収益性の低さに明確に関係していることが検証されている。
日本企業のROAは0.090%、ROEは7.010%となっている。
では、諸外国はどうかというと、たとえばアメリカだとROA 0.140%、ROE 15.930%となっている。
アメリカ以外の先進国と比較しても、日本の方が低い水準にある。
これは、リスクを恐れて積極的な投資や挑戦を控えることが、結果的に企業の成長機会を逃し、収益性の伸び悩みにつながっていることを如実に物語っている。
たった数パーセントの違いでしかないが、その対象となる金額が大きければ大きいほど効果は大きい。
つまり、100円なら大したことないが、1億円の4パーセントとなると大きな数字となる。
1億円なんて規模ではない。
もっと大きい。
となると、その破壊力は絶大だ。
それだけ日本と諸外国を比較した時に、大きな差が発生しているのだ。
内部留保を貯めるだけ貯めて活用しない日本企業
企業には潤沢な内部留保があるにも関わらず、革新活動への資源投入に結びつかない「結合不全」が起こっているという指摘もある。
これはまさに「不確実性の回避」、すなわち「リスク回避」からくる行動に他ならない。
確かにバブル崩壊、オイルショック、リーマンショック、コロナショックと金融危機を経験してきた。
そのため、内部留保を貯めて企業の体力を確保したい気持ちは分かる。
しかし、その姿勢は保守的だ。
世界市場はどんどん進展しているのに、日本企業は停滞を選んでいる。
停滞は退化である。
世界は進化しているのだから、世界経済で負けるのは当たり前である。
イノベーションは研究開発投資から始まり、事業化を経て市場導入を成功させるまでには、多くの変数と不確実性が伴う。
世界経済という競争の場で生き残っていくために、経営者に求められる最も重要な資質は、リスクが絡む案件においても、決断し、実行することなのである。
最後に
今回のコラムはどうだっただろうか。
読者の皆様にとって、今回のコラムが何か気づきや学びになれば幸いである。
少し量が多くなりそうなので、前編・後編に分けていく。
次回は、日本型マネジメントを未来へアップデートするための「攻め」の意思決定術についてお伝えする。
最新情報はスタンドエフエムで投稿している。
IT関連の話題を別角度から見てみたい
ITニュースを簡単に知りたい
IT化やDX化の話題を学びたい
自分の会社が効率化ができるか知りたい
自分の時間を大事にしたい
といった方は是非スタンドエフエムを覗いて欲しい。
それでは、また次回のコラムでお会いしよう。