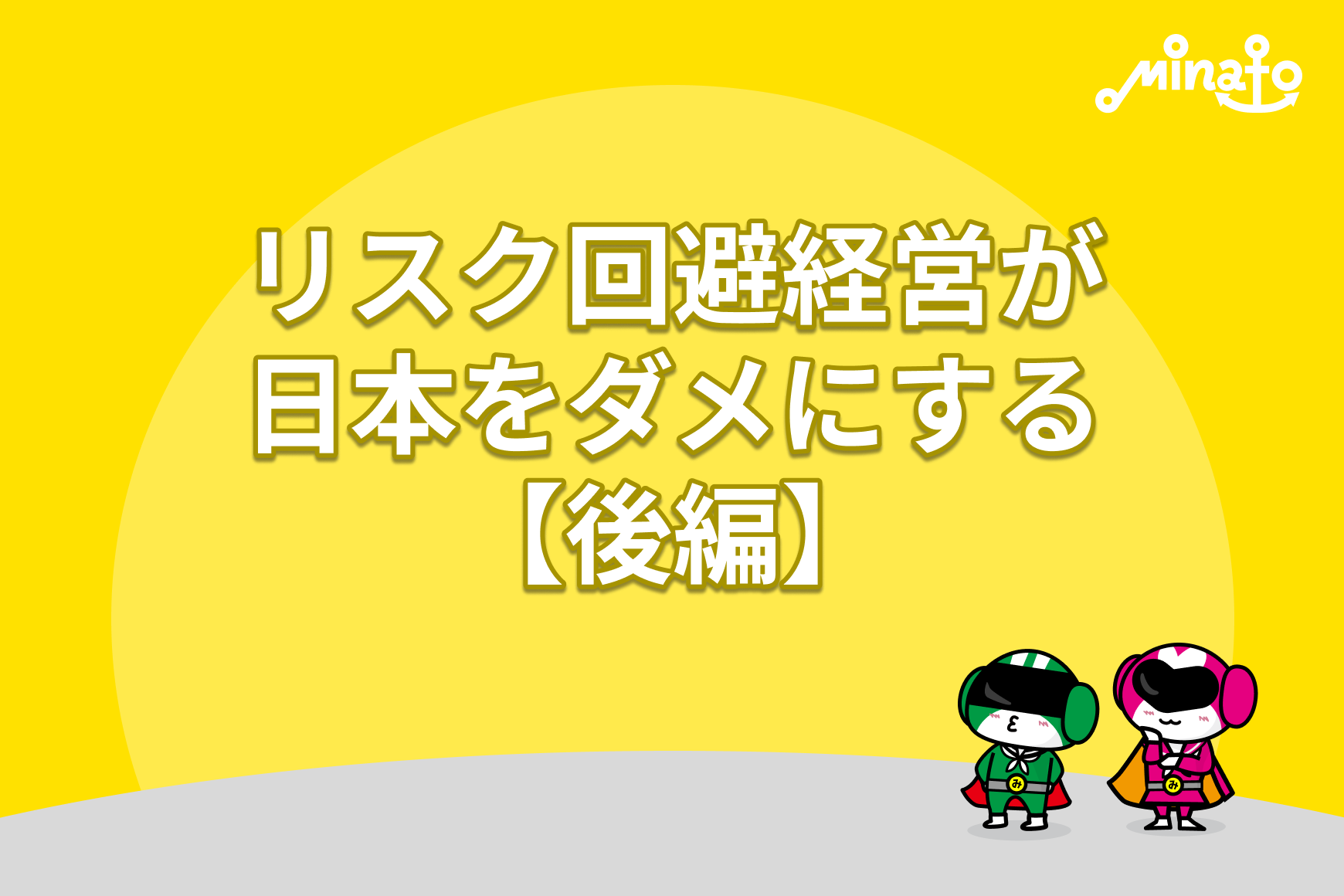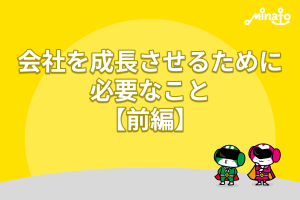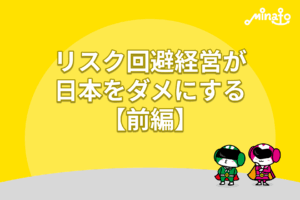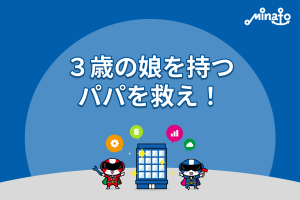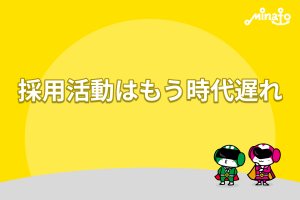COLUMN コラム
前回(リスク回避経営が日本をダメにする【前編】)では、イノベーションが起きない理由として2つを紹介した。
その2つとは、日本人の特徴である集団主義とリスク回避傾向である。
今回は、これらの問題を如何に解決していくべきかを迫っていきたい。
なお、前回と今回のコラムは「なぜ、イノベーションが生まれないのか – 経営力に課題はなかったか – 」という論説をベースにしている。
ベースにしつつ、私の考えを付け加えてお伝えしている。
是非オリジナルも読んでいただきたい(J-STAGEというしっかりしたサイトなので、安心して欲しい)。
目次
リスクとリターンを分ける「攻め」の意思決定術
さて、それでは本題に入ろう。
いかにしてこの「リスク回避」の呪縛から脱却し、「攻め」の意思決定を実現すべきか。
鍵となるのは、経営者の「経営力」のアップデートである。
経済産業省は、2019年に「日本企業における価値創造マネジメントに関する行動指針」を策定し、経営者にイノベーションに向き合う心構えを提示している。
これは、イノベーション実現に必要な考え方や施策を示すものだが、私たちに必要なのは、この指針を絵に描いた餅に終わらせないための具体的な行動だ。
2000年代以降、日本の名目労働生産性は長期にわたり停滞し、付加価値の向上がほとんど果たせなかった。
その大きな要因の一つが、IT化に不可欠な「情報化資産投資」や「人的資本形成」といった「無形資産投資」への消極的な姿勢である。
米国や欧州諸国が活発な無形資産投資を行っていた時期に、日本企業は守りの投資に終始し、新たな価値創造のための「攻め」の投資を怠ってきたのである。
つまり、日本はコスト削減にしか興味のないのに対して、世界は顧客満足度・競争優位性獲得・新規顧客の獲得など価値創造に投資したということである。
IT化の時代に今流行のDXのしようと取り組んできたことが分かる。
DXという言葉がなかった時代からデジタルに適用する組織に作り替えてきたのだ。
目先のことしか興味がなく、アナログ組織のままで、人材教育もしない日本では世界に太刀打ちできないのも納得である。
本来、TFP(全要素生産性)の上昇には無形資産投資が波及効果を持つとされている。
情報化資産、革新的資産(研究開発、著作権など)、経済的競争力(ブランド資産、人的資本形成など)といった無形資産への積極的な投資こそが、付加価値を生み出し、企業の成長を牽引する原動力となる。
経営者は、「科学の本質的動向」を把握し、「社会のニーズの変化」を嗅ぎ取り、「自社の蓄積された技術」を熟知した上で、技術開発を「どの方向、どの分野にシフト、強化していくべきか」という経営判断を行わなければならない。
自社の強み・弱み・知識・技能・人材などを見極め、イノベーションに向けて、ありとあらゆるリソース(資源や人材、技術技能など)を集結する経営力が重要だ。
具体的な事例からみる挑戦的経営
ケーススタディ:GAFA の大胆投資、国内スタートアップの挑戦
GAFA(Google, Apple, Facebook, Amazon)に代表されるグローバル企業は、まさに「攻め」の意思決定と大胆な投資によって、世界市場を席巻してきた。
正直言って、GAFAが誕生した頃は本当にどこにでもある企業だった。
まさかここまで大きな企業になるなんて誰も想像していなかっただろう。
そんな彼らは、常に変化する市場のニーズを捉え、リスクを恐れずに新たな技術やビジネスモデルに巨額の投資を行い、破壊的イノベーションを次々と生み出している。
その挑戦はまだ小さな企業だった頃から続いているのだ。
彼らが小さな企業だった頃、限られたリソースの中で、既存の枠組みにとらわれない革新的なアイデアとスピード感を持って、新たな挑戦を続けた。
彼らの多くは、大企業のような潤沢な内部留保や組織体制を持たずとも、失敗を恐れず、むしろ失敗から学び、次へと繋げるレジリエンス(回復力)を強みとしている。
その飽くなき挑戦が今の彼らを生み出したと言っても過言ではない。
日本企業が学ぶべきは、GAFAのような大規模な投資だけではない。
失敗を恐れない「挑戦の精神」と、迅速な意思決定プロセスこそが、停滞を打破し、イノベーションを創出するための重要なヒントとなるはずだ。
既存の組織文化を変革し、「尖った人材」を活かし、オープンイノベーションを積極的に推進することで、新たなエコシステムを構築していくことが、今後の日本企業には不可欠となるだろう。
結論:経営者と投資家が共有すべき“許容できる失敗”の設計図
日本経済の停滞を乗り越え、再び成長軌道に乗るためには、「リスク回避」からの脱却は避けて通れない命題である。
そのためには、経営者の意識改革が何よりも重要となる。
データが示すように、リスクを過度に恐れる姿勢は、結果的に企業の成長を阻害し、収益性の低下を招く。
「許容できる失敗」の設計図を明確に描き、経営者と投資家がそれを共有すること。
そして、失敗から学び、次なる挑戦へと繋げる文化を組織全体で醸成することが、今、日本企業に求められている。
ITへの投資も忘れてはならない。
すぐにDXをしたがるが、そもそもDXができる土壌がない。
経営者自身がIT音痴だ。
そんな状態でアナログ組織をデジタル組織に変更することなんて無理だ。
まずはIT投資と人材教育を行い、DXの下地を作るべきである。
そういった投資もまたリスクであり、このリスクを取れるかどうかが日本企業の成長を決める要素にもなる。
私たちは、過去の成功体験や慣習に囚われることなく、未来を見据えた「攻め」の意思決定へと舵を切るべき時を迎えている。
そして、それは、経営者一人の力で成し遂げられるものではない。
従業員、株主、そして社会全体が、日本企業の新たな挑戦を後押しし、失敗を恐れずに前進できる環境を共に作り上げていくことが、豊かな未来を築くための第一歩となるだろう。
未来を切り拓くために、今こそ「日本型マネジメント」をアップデートし、「リスク回避」の壁を打ち破る時が来ているのである。
今を逃せば、日本はますます世界に置いていかれ、修復不可能な国と成り下がってしまうだろう。
今こそ日本企業の経営者は立ち上がらなければならない。
最後に
今回のコラムはどうだっただろうか。
2回に分けてお伝えしたが、読者の皆様にとって、今回のコラムが何か気づきや学びになれば幸いである。
最新情報はスタンドエフエムで投稿している。
IT関連の話題を別角度から見てみたい
ITニュースを簡単に知りたい
IT化やDX化の話題を学びたい
自分の会社が効率化ができるか知りたい
自分の時間を大事にしたい
といった方は是非スタンドエフエムを覗いて欲しい。
それでは、また次回のコラムでお会いしよう。