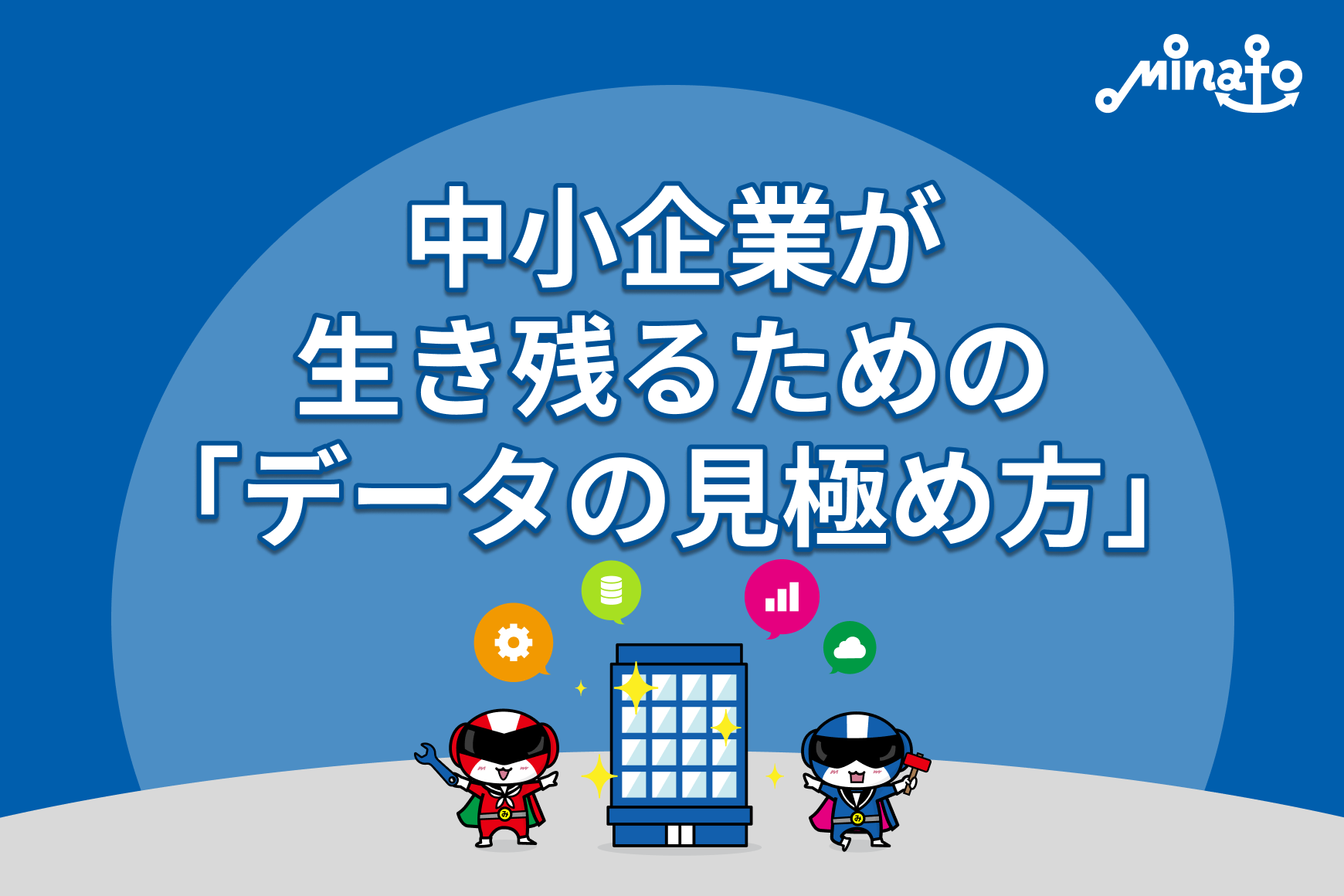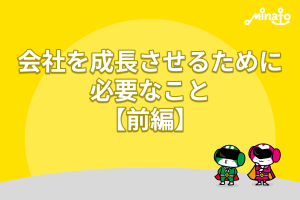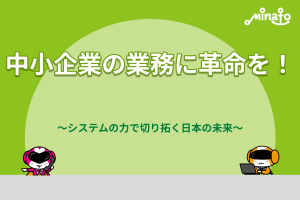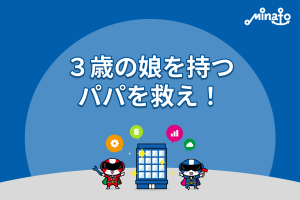COLUMN コラム
DX(デジタルトランスフォーメーション)を行うなら、データが絶対に必要である。
データなきDXは存在しない。
この本質を理解していない方が、あまりにも多いことに私は常々驚かされる。
そのため、私としては、「データドリブン経営」という言葉の方が、DXの本質に近しいと感じている。
だが、IT業界の「あるある」とでも言うべきなのか、なんというか、事あるごとに大袈裟に騒ぎ立てる風潮には辟易させられる。
「これからはデータドリブン経営だ!」
「データを活用しない勘でやっていた旧時代の経営から脱却すべきだ!」
――そんな声が、号令かのように日本のビジネス界に響き渡っている。
そして、そのデータを見るために新しいツールの導入を推進するIT企業が後を絶たず、その姿を見るたびに私はため息が出る。
言われるがままに導入して、本当に大丈夫なのか?
本当に、貴社の経営は守られるのか?
企業の生命線ともいえる貴重なキャッシュをドブに捨てる行為ではないのか?
今回のコラムでは、普段は「データ化しろ!」と口を酸っぱくして言っている私が、敢えて「データ経営の落とし穴」について深く語っていきたい。
目次
なぜ今、データ経営か?
なぜ、今これほどまでに「データ経営」が叫ばれるのか?
それは、DXの本質を理解すれば明確だ。
DXとは、データを集め、それを分析し、市場や顧客を深く理解することで、「選ばれる企業」になるためにどう努力すべきかを判断し、実行する取り組みである。
そして、そのデータは、今後来ることが確定しているAI時代において、AIを活用する際にも非常に重要な情報源となる。
AIはデータがなければ学習できないのだからだ。
これまでの経営は、社長やベテランが蓄積した経験や実体験から得られる「勘」に大きく頼ってきた。
確かに、経験豊富な「勘」は強力な武器となることもあっただろう。
企業の差別化にも貢献してきただろう。
だが、商品ライフサイクルが3年と短くなった今、その「勘」もどんどん時代についていけない状況になっている。
社長一人であればまだ良いかもしれないが、チームで組織を運用している場合、社長一人にかかる判断の負担は想像以上に大きい。
さらに、時代の変化が激しい今、これまで蓄積した経験からの「勘」が外れることも多くなった。
特に今、AIの普及と発展が凄まじい。
これまで経験や体験で蓄積した「勘」は、AIを活用することでカバーできるようになってきている。
強みが薄まる世の中になったのだ。
そんな世の中になりつつある今、これまでの経験が本当に役に立つだろうか?
私たち経営者は、自らのアップグレードの頻度を加速させなければならないが、時間は有限であり、人間のスペックは毎年年齢と共に低下する傾向にある。
そのため、いつまでも社長が第一線で頑張り続けること自体が、もはや間違いなのである。
これが「勘」の限界だ。
また、人間という不確かな要素に頼る場合、組織はその人間に依存する。
つまり、依存状態にあればあるほど、その依存先が何らかの理由で消えた瞬間、組織はあっという間に崩壊する。
この限界と制約を突破する手段として、IT化があり、DXという取り組みがあるのだ。
IT化は情報を資産化し、その資産化した情報を元に経営を加速させることがDXの本質なのだ。
こうした対策によって組織は「独り立ち」することが可能になる。
実際にデータ経営を実施して大きく拡大した企業に、私がよく例に出す企業がある。
その企業とはワークマンだ。
ワークマンは、なんとExcel1つでデータ経営を実現し、売上を約3倍にまで引き上げたのだ。
600億円からの引き上げである。
100万、200万というレベルではない。
これは相当難しい偉業だ。
だが、それをデータ経営で見事に実現した。
中小企業もまた、これまでの「勘」に従った経営ではなく、データを元にした経営に移行すべき、と断言できる。
データは確たる「証拠」を示してはいない
データ経営を実施する。
これは、これからの時代、間違いなく絶対に行うべきことだ。
故に、IT化を実施し、DXに取り組むべきである。
だが、である。
ここで、どうしても注意すべきことがある。
実は、データに依存しすぎるのもまたダメだということだ。
データ経営においてデータは命である。
しかし、そのデータは100%信頼できる情報であるのか? と問われると、そうではない。
データは「傾向」が分かるだけで、必ずしも「実態」を正確に示しているわけではないのだ。
たとえば、 「日本のDXを推進している企業の割合が8割を超えた」という調査レポートがある一方で、 「日本企業の実に9割はDXに関心がない」という調査レポートもある。
真逆だ。
前者だと8割は実施済みで、後者だと1割しかDXをやっていないことになる。
なぜ、これほどまでに大きな乖離があるのだろうか?
それは、「どこで」「誰に」「いつ」「どのような方式で聞いたのか?」といった調査の前提条件が異なっているからに他ならない。
これらの条件が明確であれば、そのデータが示す「傾向」ははっきりするだろう。
私の感覚としては、後者の方(DXに関心がない企業が9割)が実態に近いと感じる。
大手企業をはじめ、ある程度の資金的な余裕がある企業であれば、確かに8割の企業がDXに取り組んでいるのかもしれない(ただのIT化をDXと呼んでいるケースが多いが…)。
このようにデータとは、対象や実施方法、調査した場所などによって「バラつき」が発生する。
国民調査でも全国民にアンケートを取っているわけではない。
一部の国民に調査したに過ぎない。
地域もバラバラだろう。都市部なのか?地方なのか?都市部でも東京と大阪でも大きく違うだろう。
このようにデータは「ブレるもの」であり、あくまで「傾向を掴むもの」であるという認識を、常に持っておく必要がある。
そもそもビッグデータを中小企業は用意できない
他にも、データ経営における中小企業ならではの弱点がある。
データは「傾向」を掴むものである。
ということは、データは多ければ多いほど、その傾向の精度は高まる。
では、大手企業のような「ビッグデータ」を中小企業は用意できるだろうか?
GoogleやAmazon、Netflixといった巨大企業が持つ、膨大かつ多種多様なデータのことを「ビッグデータ」という。
そんな天文学的な量のデータを用意しろ、と言われて用意できるのは大手企業くらいだ。
中小企業にそんな膨大なデータを集めることなんて、現実的にできない。
ということは、私たちは「限られたデータ」を活用するしかない、ということになる。
そして、その限られたデータでは、データの「傾向」も誤っている可能性がある。
例えば、「寿司とステーキ、どちらが好きか?」という質問に、
100件の回答ではステーキが優勢だが、
1000件の回答では寿司が優勢になるかもしれない。
もしかしたら、1万件の調査をすると、再びステーキが優勢になるかもしれない。
このようにデータ量によって「見え方」は大きく変わってくる。
何時に聞いたか?といった調査の時間帯も問題だろう。
一部の情報だけで全体を判断してしまうことで、誤った判断をしてしまうリスクが常につきまとう。
データ分析ツールの見かけ上の数字に惑わされ、顧客の感情や市場の動きといった、数字では測れない本質的な部分を見落としてしまうこともあるだろう。
「データに裏付けられているから安心である」という風に妄信する行為は、極めて危険なのだ。
データは「妄信」するな。「利用」せよ
では、データを信じてしまうと痛い目に遭うのではないか?と不安に思う方もいるだろう。
それはそれで間違っている。
私が言いたいのは、データを「妄信するな」ということなのだ。
データを盲目的に信じ切ってしまうことが問題なのである。
「勘」に頼り切った状態から、ある程度のロジカルで共有できる「資産」にすべきなのだ。
それこそが、社長の最も重要な仕事である。
だからこそ、データ経営には真剣に取り組むべきなのだ。
そこで、ここからは、データから「失敗」を引き起こさないための、データを活用する際の決定的なポイントをお伝えしよう。
1:データは「傾向」を示す羅針盤として割り切れ
データは「傾向」が見える。
たとえば、「この時期に、この価格帯の商品が、あの地域でよく売れる傾向がある」といった具合だ。
これ自体は価値のある情報だ。
しかし、それがあなたの会社にそのまま当てはまる保証はどこにもない。
データが示す傾向を鵜呑みにせず、あくまで「仮説を立てるためのヒント」として捉えるのだ。
2:仮説を立てたら、必ず「小さくテストする」ことを徹底せよ
次は、仮説と実行である。
データから「この傾向があるなら、きっとこうすればうまくいくはずだ!」という仮説を作ることができる。
だが、ここで注意したいのは、すぐに全面展開してしまうことだ。
ついつい中小企業は、「えいや」と全力投球してしまう。
だが、限られたリソースの中小企業にとって、それは致命傷になりかねない。
そうではない。
仮説なので、絶対ではないのだ。
必ず「小さくテストすること」が大事だ。
たとえば新商品の開発においても、いきなり開発してしまうとダメだった時のダメージが大きい。
「この時期に、この価格帯の商品が、あの地域でよく売れる傾向がある」
という仮説がたったなら、一度広告で試してみるなどして反応を確かめてみる。
反応があって初めて商品開発に着手する。
だが、ここでも大々的に売り出してはいけない。
まだテストだ。
限定的な数だけ生産し、テスト販売する。
そこでも問題なかった場合、更に範囲を広げたり個数を増やしたりする。
こうやって段階的にやってみるのだ。
この小さなテストの段階もデータ収集は怠ってはならない。
ここで得られるデータこそが、最もリアルで生きた情報となる。
日本人は「答え」を求めがちだが、データは「参考情報」と割り切って考えるべきなのだ。
3:テストでコケたら、再チャレンジまたは撤退
テストをやってみた。
だが、残念ながら失敗した。
これはよくあることだろう。
この時、もしあなたが「小さく」テストを始めていれば、ダメージは最小限で済む。
まずはデータを見直して、何がダメだったか再検討する。
新しいマーケティング施策であれば、一部の媒体や期間を限定して試してみる。
ウェブサイトのリニューアルであれば、A/Bテストで小さな改善を繰り返し、顧客の反応を測る。
商品名にあるのではないか?と思えば、変えてみる。
ロゴも疑ってみる。
このようにして徹底的に対策案を考えるのだ。
そして、再チャレンジもよいだろう。
だが、場合によっては「完全撤退」も視野に入れるべきだ。
絶対にその事業でなければならないわけではない。
潔く撤退し、別事業でチャレンジする。
これもまた企業として、経営者として、正しい在り方である。
即座に修正・撤退できる「スモールスタート」を構築せよ
だからこそ、「即座に修正・撤退できる『スモールスタート』を構築せよ」という鉄則を肝に銘じるべきだ。
やはり「いきなりフルベットは死ぬ」のだ。
テストの結果が、あなたがデータから導き出した仮説や期待していた傾向と違った場合、あるいは思ったような成果が出なかった場合、どうするだろうか?
「まだテストが不十分だった」
「もう少し続ければきっとうまくいく」
と、意地になって追加投資をしていないか?
限られたリソースの中小企業だからこそ、リスク分散の徹底が命綱となる。
小さく始めて、もし失敗しても大きな痛手にならない範囲で、検証と改善を繰り返すPDCAサイクルを徹底するのだ。
テストの結果が芳しくなければ、速やかに方針を修正するか、あるいは潔く撤退する勇気を持つこと。
この「スモールスタート」で始め、柔軟に方向転換できる体制こそが、変化の激しい現代を生き抜くための鍵となる。
勘で経営していることが多い中小企業にとって、データを中心とした経営手法は慣れないだろう。
世間的にも「データドリブン経営こそが正義」と言われて、「そうなんだー」と鵜呑みにしてしまう経営者も多いかもしれない。
しかし、データには多くの落とし穴がある。
ータを妄信してしまうのは、非常に危険極まりない行為である。
その危険性を十分に理解しなければならない。
その上で、データが示す「傾向」を元に「仮説」を立て、「小さなテスト」で検証し、「スモールスタート」で軌道修正する。
このサイクルを愚直に回すことで、データはあなたのビジネスを確かな成功へと導く、強力な羅針盤となるだろう。
データは妄信するものではなく、賢く「利用」するものである。
今回のコラムが、あなたの経営におけるヒントになったら、これ以上にない喜びである。
最後に
今回のコラムはどうだっただろうか。
読者の皆様にとって、今回のコラムが何か気づきや学びになれば幸いである。
最新情報はスタンドエフエムで投稿している。
IT関連の話題を別角度から見てみたい
ITニュースを簡単に知りたい
IT化やDX化の話題を学びたい
自分の会社が効率化ができるか知りたい
自分の時間を大事にしたい
といった方は是非スタンドエフエムを覗いて欲しい。
それでは、また次回のコラムでお会いしよう。