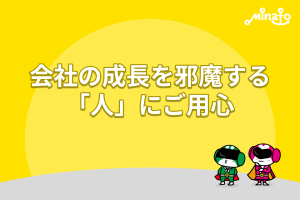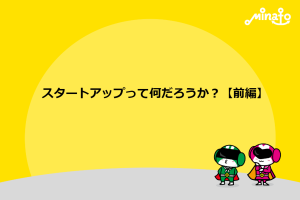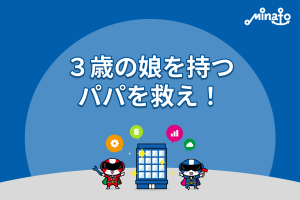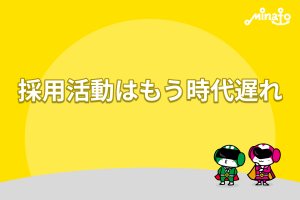COLUMN コラム
目次
その「社員教育」、本当に成果が出ているか?
「社員を育てるためには教育が必要である」。
多くの企業がそう考え、教育研修やOJTに力を入れている。
しかし、本当にその教育は社員の成長に繋がり、明確な成果を生み出しているだろうか?
私には、成果のない教育ばかりが先行し、貴重な時間と資金を無駄にしているケースが少なくないように見えるのだ。
実は、外部の教育に頼るよりも、自社内でできることの方が社員の成長にはるかに重要である。
会社経営者、社内教育で悩んでいる方、人事担当者の方は、ぜひ最後まで読み、貴社の教育のあり方を見直すきっかけにしてほしい。
その教育、本当に必要か?成果ゼロは「最悪のパターン」
もし営業部の教育を行うとしたら、その最終的な成果は「営業成績の向上」であるはずだ。
コミュニケーション術、ドキュメント作成術、アンガーマネジメントなど、何を学んだとしても、最終的に営業成績に変化がなければ、その教育は全く意味がないと言わざるを得ない。
確かに本人の意欲や姿勢も大切だが、それ以上に「成果が出ない」という事実そのものが最大の問題である(そういった意味では、近年乱立する「講座ビジネス」の中にも、成果の出ないものが多すぎると感じている)。
10人が受講して成果がゼロ。
こんな悲惨な状況は、残念ながら決して珍しくない。
「教育プログラムの質が悪いのか?」と考えるかもしれないが、それは本質ではない。
そもそも、教育プログラムを受けても何も変化がないこと自体が最悪なのだ。
どんなに手を替え品を替え試しても同じ結果なら、一体どうすれば成果を出せるのだろうか?
成果を出すために「言語化」が鍵となる
ここで一度振り返ってほしいのだが、「できる人」と「できない人」の違いを、あなたは具体的に言語化できているだろうか?
実はここに、大きなポイントがあるのだ。
多くの企業では、この「違い」を言語化することを忘れがちである。
そもそも、適切なスタートラインに立っていない人にいくら教育を施しても、それは無意味な努力に終わってしまう。
まずは、「スタートラインに立つ」こと。
そのために、「言語化」が極めて重要になるのだ。
営業で言えば、「営業成績が良い人」と「営業成績が悪い人」にはどんな違いがあるのかを、徹底的にチェックするということである。
では、具体的にどのようにしてその違いを言語化すればよいのだろうか?
「違い」を言語化するための実践手順
具体的な手順を3つのステップで紹介する。
ステップ1:徹底的に比較する
最初のステップは、できる人とできない人の行動を徹底的に比較することだ。
たとえば、第一声のテンション、表情、声のトーン、話し方、話す内容、身振り手振り、など、あらゆる要素を詳細に観察し、リストアップしていく。
完璧を目指しすぎると次のステップに進めなくなるので、ある程度リストアップできたら、次のステップに移るべきだ。
ステップ2:項目別に重要度をつける
リストアップした項目を、一度にすべて他の社員に適用させるのは困難である。
そこで、1回につき3つか5つずつ教えられるように、重要度をつけていく。
ここでも厳密な優先順位付けにこだわりすぎず、ある程度感覚的に「最初にやった方がいいかな」「次にこれを試そう」といった形で選んで構わない。
もし選びにくければ、くじ引きで決めるのも良いだろう。
大切なのは、一気に大量の項目を押し付けないことだ。
30個も50個も一度にやれと言われても、人はなかなか実行できない。
ステップ3:徐々に適用する
いよいよ実践である。
ステップ2で優先順位をつけた「営業成績が良い人の特徴」を、徐々に実践させていく。
フィードバックを受けながら試行錯誤を繰り返す中で、営業ノウハウを蓄積させていくのだ。
一気に大きな変化は期待できないから、長い目で見て判断することが重要である。
これは、単に社員を育てるだけでなく、組織全体の営業ノウハウを蓄積していくプロセスだと捉えるべきだ。
そして、もし全てのリストを適用しても変化が見られない場合は、迷わずステップ1から再チャレンジすることを忘れてはならない。
「言語化」による「仕組み化」が組織を飛躍させる
多くの人は、個人の才能や能力値で成果が決まると思い込みがちだ。
しかし、その優劣を超えるのが「仕組み化」である。
明確なルールがあり、それに従って進めれば必ず一定の成果を上げられる方程式があれば、たとえ特別に優秀でなくても、安定した結果を出すことができる。
優秀な人は「型」を持っているものだ。
彼らが「なんとなくやっているように見える」としても、実は「同じ流れを繰り返し」実践していることがほとんどである。
だからこそ、成果にブレが少ないのだ。
一方で、毎回ゼロから構築しようとする人は、パターン化ができず、非効率で成果も安定しない。
失敗の原因も分からず、改善方法も見当がつかないといった状況に陥りがちである。
たった一つ、「優秀な人がやっている型」を徹底的に真似させる。
この「言語化」と「模倣」こそが、組織内の人のレベルを底上げする最大のポイントなのだ。
教育よりも「模倣」が効果的な理由
改めて「教育」について考えてみよう。
教育は、施すべきタイミングが決まっている。
基礎ができていない状態では、どんなに質の高いインプットも意味がない。
例えば、パソコン操作が苦手な人にいきなりプログラミングを教えても、それは無理な話だ。
まずパソコンに慣れてもらう必要がある。
このように、「スタートラインに立っているか」どうかが非常に重要なのだ。
そして残念ながら、多くの社員は、教えたい内容のスタートラインに立っていないことが多いのが現実である。
であるならば、まずはスタートラインに立ってもらうことから始めるべきだ。
そのためには、徹底したテンプレートを守らせ、フィードバックを受けながら改善する。
この繰り返しこそが、社員を徐々に成長させる最も確実な方法なのだ。
この取り組みは、確かに手間がかかる。
だからこそ、他の企業はなかなか実行しない。
しかし、やれば最強の育成方法であると断言できる。
先ほど挙げた3つのステップを、ぜひ一度試してみてほしい。
最後に
今回のコラムはどうだっただろうか。
今回のコラムが何か気づきや学びになれば幸いである。
武道では「守破離」という言葉がある。
簡単に言うと、最初は「型を守る」ことから始め、次第に「型を破って発展させ」、そして、「型から離れてオリジナルの型を作る」ということだ。
多くの研修やOJTでは、「破」や「離」を教えようとしているように思う。
それでは、身につかないのも納得である。
研修をしているから問題ない、ではなく、しっかり成果をチェックする癖も大事だ。
最新情報はスタンドエフエムで投稿している。
IT関連の話題を別角度から見てみたい
ITニュースを簡単に知りたい
IT化やDX化の話題を学びたい
自分の会社が効率化ができるか知りたい
自分の時間を大事にしたい
といった方は是非スタンドエフエムを覗いて欲しい。
それではまた次回のコラムでお会いしましょう。