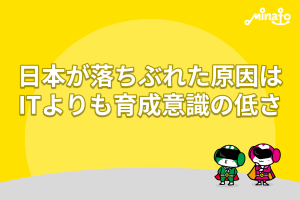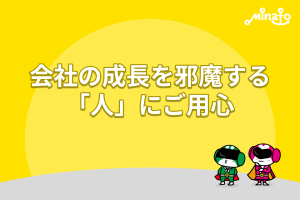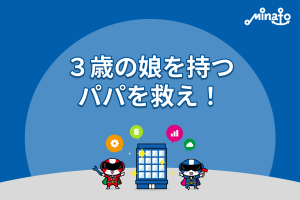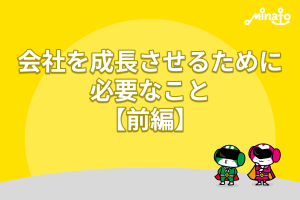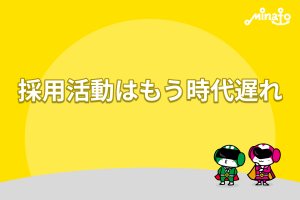COLUMN コラム
先日、「採用しなくても強い会社へ」というコラムを書いた。
そこでは、省人化によって組織を再設計し、採用に依存しない盤石な組織を構築できると力説した。
だが、実はそのコラムで意図的に伏せていた、省人化を推進する上で避けては通れない「落とし穴」がある。
省人化を行うことで、多くの社員が「自分の仕事がなくなってしまうのではないか?」と不安を感じてしまうのだ。
これまで自分が担ってきた業務が、ある日を境にがらりと変わる。
あるいは、これまで自分だけが知っていたノウハウや情報が、会社全体で共有化され、誰にでもできる形に「見える化」されてしまう。
まるで自分が会社にとって無価値であるかのように感じてしまう社員もいるだろう。
長年培ってきた専門性が否定されたかのような喪失感を覚える者もいるかもしれない。
今までの努力は何だったのかと、絶望にも似たモチベーションの低下につながる人もいるはずだ。
会社側から特に明確なビジョンを示すことなく、「効率化のため」「人件費削減のため」といったドライな理由だけで省人化を進めれば、社員は会社に対する不信感を募らせてしまうことだろう。
この負の感情は、驚くほど速く組織全体に伝播し、結果として組織の士気は地の底まで下がってしまうこととなる。
パフォーマンスの低下は避けられず、最悪の場合、最も優秀な人材から順番に会社を去っていくという、目も当てられないシナリオを招きかねないのだ。
そこで、今回のコラムでは、省人化を実行する際に、企業がどのような点に細心の注意を払い、社員の心を掴むべきかを考察していこう。
あくまでも「仕組み」であって、主役は「人」
省人化は、業務プロセスの最適化を行うことで業務工数や必要人数を削減することができる取り組みのことである。
よく耳にする言葉とするならば、まさに「生産性の向上」に他ならないだろう。
確かに省人化は生産性を高める。
これは揺るぎない事実だ。
しかし、あくまでも「仕組み」であることを忘れてはならない。
業務を実行するためのルールを作るだけなのだ。
そのルールを実行し、運用するのは、感情を持った「人」である。
社員の心が離れてしまっては、どんなに効率的な業務フローを設計しても、組織は機能不全に陥ってしまう。
そして、最終的には組織の崩壊につながってしまうのだ。
だからこそ、省人化を実行する際は、社員のエンゲージメントをいかに維持し、そして向上させるのかといった視点が、最も重要であり、必要不可欠なのだ。
両立のカギは「参加感」と「成長実感」
では、省人化と社員のエンゲージメントという、一見すると相反する要素を両立させるためには、一体何が必要だろうか?
それは、社員に「参加感」と「成長実感」を与えることである。
この2つがあるかないかで、結果は天と地ほどに違うのだ。
まず「参加感」とは何を示しているか?
省人化を行う際のプロセスに、現場の社員を積極的に巻き込んで参加させていることが極めて重要である。
業務の具体的な内容は、やはり現場が最もよく知っている。
ちろん、現場の凝り固まった常識だけではブレイクスルーできないので、現場任せではダメだ。
だが、業務を理解していない外部の人間が「あーだこーだ」と口出ししても、決して最適解を導くことはできないのだ。
となると、どの業務を自動化するのか、どのように効率化するのか、といったことを現場の社員も交えて徹底的に議論し、共に考え、一緒に決定していくプロセスが、「会社を自分も変えていっている」という計り知れない「参加感」につながる。
意思決定を行う権限にない人もいるかもしれない。
そういった場合でも、意見を述べ、フィードバックを実行できる権限を彼らに与えることはできるはずだ。
このように「自分たちの手で会社を変えている」という参加感をいかにして持ってもらうかが、社員一人ひとりの主体性を引き出し、モチベーションの低下を根本から防ぐために極めて大事なのだ。
次に成長実感だが、これは、社員一人ひとりが、自らのスキル向上やキャリア発展を実感しているかどうかということである。
そのまんま過ぎて、少々分かりにくいかもしれないので、もう少し解説しよう。
省人化によって浮いた余力、つまり「時間」や「人的リソース」を、決して人件費削減のためだけに使ってはならない。
そのような目的で省人化を行うと、人の心は必ず離れてしまう。
だからこそ、人件費削減を唯一の目的とした省人化は、絶対に避けるべきだ。
では、なぜ省人化が必要なのか?
その目的を深く考えるべきである。
- 顧客のため
- 社会のため
- 社員一人ひとりのため
その本質的な目的を明確に言語化することから始めるべきだ。
そして、その言語化ができたら、浮いた余力を何に使うかを真剣に検討する。
その検討の中で、社員一人ひとりの「新しい挑戦」や「スキル向上」に積極的に割り当てていくのだ。
これが、社員の「成長実感」につながる確かな種となる。
たとえば、自動化によって業務量が減った社員には、より高度な分析業務を任せたり、新しいプロジェクトのリーダーを経験させたりすることができる。
生成AIの導入を勧めることで資料作成や情報収集の時間を削減し、その分を戦略立案や顧客開拓、フォロー活動など、人間にしかできない創造的な業務に力を入れることも可能になる。
このように、社員は「自分の仕事がなくなる」という危機感を覚えるのではなく、「より価値の高い仕事ができるようになった」という実感を得るようになる。
そして、それが正当に給与に反映されたら、彼らのモチベーションは完璧な状態になるだろう。
採用に頼らない強い組織の未来とは
省人化とエンゲージメントを両立させる組織設計は、人材不足に悩む未来の日本企業にとって、まさに生命線ともいえる最重要戦略である。
この2つの要素が相乗効果を生み出すことで、組織は計り知れない強力なメリットを享受できる。
1つ目は、格段に高まる組織の柔軟性だ。
考えてみて欲しいのだが、少数精鋭でしっかり結果を出せる業務体制をライバル企業が持っていたら、それはどれほどの脅威となるだろうか?
そのような体制を有する組織は、市場の変化や外部環境の変動に対して、驚くほど迅速に対応できる強みを持つ。
大手企業が10年も経つと全く違うビジネスをやっていることは今や当然のことだ。
これは中小企業にもまた強く求められるようになったことである。
こうした事業転換や新規事業への参入も、人材確保というボトルネックに悩まされることなく、スムーズに行うことができる盤石な組織を手に入れることができるのだ。
2つ目は、変化対応力が飛躍的に向上することだ。
社員が常に学び、新しいスキルを習得し、自ら業務改善に参画することで、組織全体が「変化を恐れない」「変化を楽しむ」という、極めて前向きな文化を持つようになる。
これは予測不能な現代において、企業が生き残り、持続的に成長し続けるために最も重要な要素と言える。
この2つの大きすぎるメリットは、採用コストや教育コストを削減し、少数精鋭で高い生産性を実現する組織を生み出すこととなる。
そして、社員は自らの成長と会社の発展を実感しながら、モチベーション高く働く。
これこそが、人材不足という逆境を力強く跳ね返し、競争力を高める、日本の中小企業に必要な「採用に頼らない強い組織」の未来像である。
もしみなさんの会社が、終わりのない採用活動に疲弊しているのなら、ぜひこの「省人化とエンゲージメントを両立させる組織設計」に本気で挑戦してみて欲しい。
きっとみなさんの会社の未来、社員の未来、そして顧客の未来を明るく切り開く確かな一歩となるはずだ。
最後に
今回のコラムはどうだっただろうか。
読者の皆様にとって、今回のコラムが何か気づきや学びになれば幸いである。
最新情報はスタンドエフエムで投稿している。
IT関連の話題を別角度から見てみたい
ITニュースを簡単に知りたい
IT化やDX化の話題を学びたい
自分の会社が効率化ができるか知りたい
自分の時間を大事にしたい
といった方は是非スタンドエフエムを覗いて欲しい。
それでは、また次回のコラムでお会いしよう。