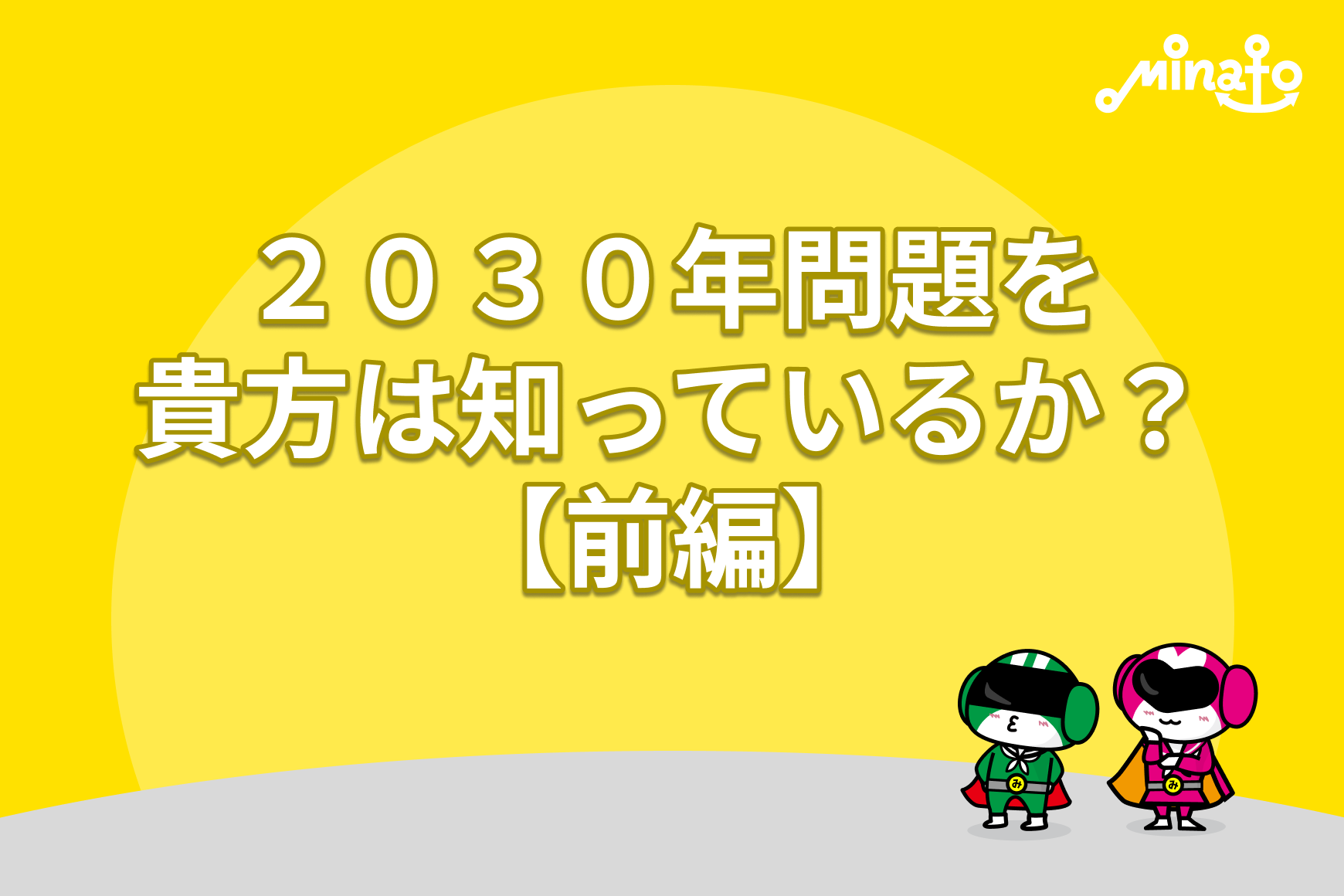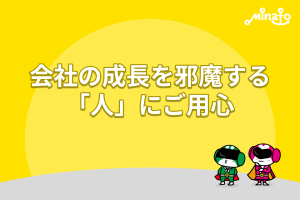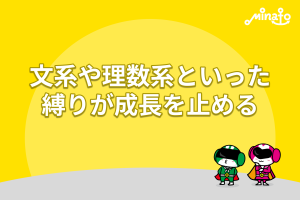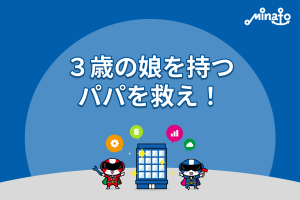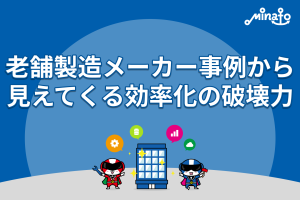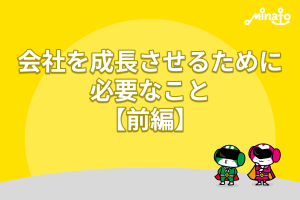COLUMN コラム
2030年。
それは輝かしい未来が待っている、ばかりではない。
世界的に先進国の抱える大きな課題の1つに、少子高齢化という問題がある。
日本も同じで、今人口問題が非常に大きな問題となっている。
はずだが・・・。
どうにも問題意識が薄いようにも思う。
そこで、今回は改めて人口減少問題がどう影響するのかを見ていきたい。
何十万人も毎年消えている
ますは総務省統計局が出しているデータを見てみよう(人口推計(2023年(令和5年)10月1日現在))。
国の出している統計では、12年連続で減少していることが報告されている。
23年:59万5000人
22年:55万6000人
21年:64万4000人
20年:40万9000人
19年:19万3000人
18年:17万人
17年:12万3000人
過去3年のデータだけでもすごいことになっている。
たった3年で150万以上も減った計算になる。
次にこちらも見てみたい。
今度は同じ総務省だが、住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数の調査である。
この中の2頁を見ていただきたい。
平成18年ごろから順調に人口が下がっているが、特筆すべきは令和に入って以降だ。
24(令和6)年:86万1237人
23(令和5)年:80万0523人
22(令和4)年:61万9140人
21(令和3)年:42万8617人
20(令和2)年:50万5046人
19(平成31)年:43万3239人
18(平成30)年:37万4055人
17(平成29)年:30万8084人
1つ目と2つ目でデータが違うが、これは外国人の流入を含むかどうかである。
上は含み、下は純粋に日本人のみで計算した数値である。
下のデータだと、この3年で230万人ほどの人口が減ったことになる。
コロナ禍によるダメージもあるだろうが、それによって爆発的に拡大したとは思えない。
また、コロナ禍で倍増したとしても、毎年40万人ほどはいなくなっているのには変わりない。
80万人も減ったと言われてもよく分からないと思うし、私もそうだ。
そこで、80万人とはどれくらいの規模か調べてみた。
都道府県の人口ランキングで、41位佐賀県と42位山梨県がちょうどそれくらいの人口だ。
和歌山:92万2584人
佐賀県:81万1442人
山梨県:80万9974人
もう少しで和歌山の人口分が1年で減るところだった。
お分かりだろうか?
1年で都道府県1つ分は減っていっているのだ。
ちなみに、過去5年間で減った人口は321万4563人となり、人口ランキング10位の静岡県に迫る人口減である(静岡県:363万3202人、11位が茨城件で286万人)。
終わらない人口減少
2030年を契機に人口減少による様々な影響が発生し始める。
それは2040年問題や2055年問題と普及していく。
そこで、各問題について少し見ていきたい。
専門家ではないので、専門的な知識というよりも表面的な情報で申し訳ないが、それぞれどういったものかを軽くでも知っておく方がよいだろう。
2030年問題
少子高齢化による影響が各所に顕在化するタイミングである。
団塊の世代が80代前半、団塊ジュニア世代が50代後半になると言われている。
高齢者の割合が三分の一を占めることが予想され(今は四分の一)、経済の維持・人口の維持・税収の維持に課題を感じ始める時期である。
医療や社会保障に問題が発生するので、働き手への税金はますます増加していくことになると予想される。
また、企業としても深刻な課題である労働力の確保が更に難しくなる。
今でも十分に難しい採用課題が更に深刻になり、サービス品質の低下や人件費の高騰、その他経費の高騰などが考えられ、業績悪化に直接的に関係していくと考えられている。
2040年問題
団塊ジュニア世代がとうとう高齢者の仲間入りするタイミング。
2030年で問題になった課題が更に進み、悪化する時期である。
たとえば以下のようなことが考えられている。
- 医療・介護問題
- 社会保障のひっ迫
- 市場規模の縮小
- 財政悪化
- インフラ設備の老朽化(建物や橋、道路、水道、ガス、公園、公共トイレなどのあらゆるインフラ設備)
- 市区町村の存続
税収に課題があるが、税収を確保できるほどの人口はおらず、市場も縮小しているので税収を増やそうとすればするほど破綻していくという悪循環が目に見える。
この時期になると、今でも問題になっている市区町村の存続が難しくなって、廃止・統合される市区町村が出てくるだろう。
また、インフラ設備の修繕にもトラブルが発生し始めるだろう。
「ポツンと一軒家」というテレビ番組で出てくるような道が全然珍しくなくなっていくのだろうか。
もしそうなったら、ますます荒廃した未来になってしまいそうだ。
2055年問題
15年も飛んだなーっていう感じで、2040年を過ぎれば少しは落ち着けるのかな?って思った方もいるかもしれない。
だが、楽観視はNGである。
もう十分深刻なダメージを2040年までで受けている。
未来は全然明るくない。
もう止めてくれ!って私の心は叫んでいる。
だが、ここで止まってはいけない。
2055年問題を書けとキーボードが轟き叫んでいるのだ。
さて、2050年は自然災害が酷くなる、と予想されていて、2055年は「超」高齢化社会を迎える時期と考えられている。
魔人英雄伝ワタルもドラゴンボールも「超」が付くとワクワクするが、高齢化社会に「超」が付くとおっかない。
では、超高齢化社会とはどのような社会だろうか?
なんと3人に1人は高齢者で、4人に1人は後期高齢者になるそうだ。
現役世代が1.3人で高齢者1人を支えることになるそうだ。
1960年は11人、1980年は7人で支えていた。
2024年である今は2人で1人を支え、2055年には1.3人。
無理ゲーである。
まだある。
15歳未満の子どもの数は総人口の8%に減少。
1975年は24%だったが、2024年には11%。
それが1ケタ台。
10人いたら3人は絶対高齢者の社会で、どうビジネスをするのか?
若者の割合なんて高齢者よりも低い。
ビジネスが絶望的になる。
そんな未来が実現するのが2055年である。
まとめ~今から早めの対策を!~
2055年まであと30年あるから大丈夫と思っている方もいるだろう。
甘い。
甘すぎる。
アメリカのドーナツやチョコのように甘い。
私は今年39歳である。
30年なんて一瞬だった。
先週結婚して
先々週大学卒業して
先月高校卒業して
半年前に生まれた
位の勢いで人生が進んでいる。
30年は一瞬なのだ。
もう絶望のように感じる未来だが、私たち経営者は明るい未来を社会に、社員に、顧客に見せ続けなければならない。
夢を提供し続けなければならない。
それが企業家の使命である。
では、2030年、2040年、2055年を乗り切るために何をすべきかを次回考察していきたい。