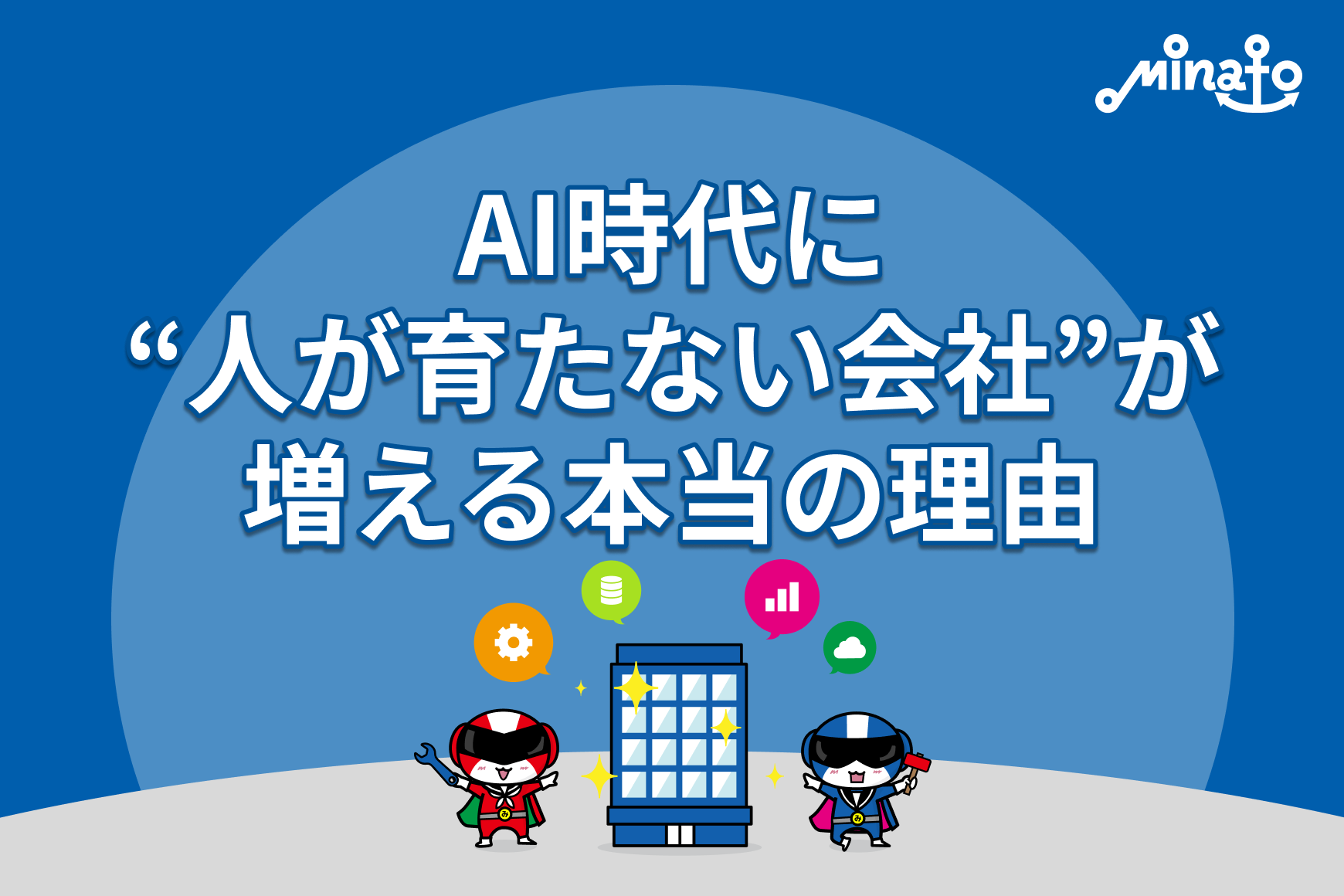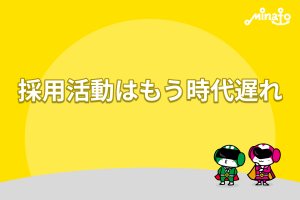COLUMN コラム
生成AIの進化は目覚ましい。
ChatGPTやClaude、Copilotといった生成AIは、わずか数年で驚異的な進化を遂げた。
少し前まではできなかったことが、たった数ヶ月でできるようになった。
その進歩の早さにエンジニアでもある私も驚きを隠せない。
会社業務に注目してみても今や、企画書、議事録、顧客対応、デザインラフ、さらにはソースコードまで“AIが書ける”時代に突入した。
こうなると、経営者の中には
「もう人材は必要ないのではないか」
「人は最低限でいい」
と考える人もいるだろう。
確かに現場に目線を向けると、AIが仕事の手間を省いている。
そのため、これまで重視されてきたスキルや経験が軽視されつつあるようにも感じている。
しかし、私はここであえて問いかけたい。
「AIが人材を殺す」のではない。
人材を殺すのは、AIに過剰な期待をした“人間側”の設計ミスである。
そこで、今回はAI時代において人を育てるとはどういうことかを見ていきたい。
目次
AI時代の人材像はこれまでと大きく変わる
AI依存は組織の無能化につながる
生成AIは確かに優秀である。
ともすれば人よりも優秀だ。
少なくとも私よりも賢い。
多くのテストに合格するだろう。
しかも、早い。
これまで何時間とかかっていた作業をたった数分で完結できる。
だが、ここで考えてみて欲しい。
そのAIの出力結果は何を元にしているだろうか?
何でもそうだが、出力を求めるならば入力を行う必要がある。
AIにおいては、明確な指示が必要である。
そして、出力結果に対する適切な判断基準が必要となり、場合によっては改めて指示を行う必要がある。
指示と判断は誰が行っているのだろうか?
そう、人間である。
AIは確かに便利だ。
だが、AIは「考える道具」ではない。
あくまでも「人間が考えた結果を形にする道具」である。
巷では、AIが仕事を奪うと言っている輩がいる。
では、AIが勝手に判断して仕事をするというのだろうか?
映画のマトリックスを見すぎだ。
実に面白い。
現実にはまだ程遠い話だ。
そんな世の中はまだ来ない。
あくまでも現時点においては、人がAIを使って効率的に業務を行うことができるが故に解雇が発生するに過ぎない。
だが、安心して欲しい。
日本においては従業員のセーフティがバッチリだ!
だから、解雇は起きにくい。
というか、そんなもんで解雇が起きるなら、弊社のサービスは10人で毎日8時間かかっていた作業を1人で10分でできるようにしたことがある。
こんなもんでよければいくらでも実現できるので、別に生成AIの到来で仕事がなくなるわけではなく、IT化していない日本企業がIT化しただけで巻き起こることであるので、特別騒ぎだてるようなことでもない。
無責任である。
話が逸れた。
話を戻すと、AIは「人間が考えた結果を出力するだけの道具である」ため、企業として採るべきはAIを活用するための適切な判断力とコミュニケーション能力を持った人材の育成である。
それにもかかわらず「AIさえあれば人は不要である」という思い込みをしている経営者が多い。
その考えは極論である。
生成AIの底力を過信することは、会社を倒産させる危険性すらある。
つまり、AIに依存する体質の組織では、組織自体が無能化していく。
AI時代の人材教育とは
生成AIを活用する時、重要になるのは指示命令である。
確かに適当な指示でも今の生成AIは十分に解釈してくれるだろう。
だが、その出力結果が本当に適切かどうかは別だ。
その指示する力と判断力はAIを活用する上で非常に重要なビジネス力となる。
たとえばエンジニアである私は、ソースコードをAIを活用して作ってもらうことがある。
その時そのソースコードが正しいかどうかの判断を必ず行っており、適宜修正を行っている。
何のために、誰に向けて、何を行うのか?
といった視点でAIに依頼することがないと粗悪な結果しか出力されないだろう。
AI時代における人材教育はただAIを使えるようになればよいだけでは済まない。
AIというツールを使える土台作りこそが必要不可欠な要素となるだろう。
どういった人材を育成すべきか?
土台と言っても不透明なので、人材育成において最低限持つべき根本となる要素を3つ提示したい。
どれも当たり前のことであるので、改めて意識していただきたい。
1:人の感情を汲み取れる人
EQとも言える。
AIはシステムである。
人間はバグだらけの欠陥品である。
たとえば、5前まで「もう買わない」と言っていた商品を、次の瞬間に買っているなんてことはザラにある。
それくらいバグだらけだ。
人は感情で生きている。
だからこそ、人の感情を汲み取り寄り添える力こそが重要となる。
人の気持ちに寄り添うことはAIでも疑似的に行うことができる
だが、それはあくまでも「それっぽく」感情を理解しているように見せかけているだけだ。
本当の意味で人に寄り添えるのはやはり人だけなのだ。
2:好奇心がある人
好奇心はあらゆるものの原動力となる。
この好奇心をいくつになっても持ち続けることができるのか?が人生を豊かにするかどうかを決定づけると言ってもいい。
それくらい重要である。
この好奇心は仕事上においても非常に大きな効果を発揮する。
新しいことへの興味関心、より効果的に業務を遂行する方法の探求、顧客や業界へのリサーチなどなど挙げ始めたらキリがないだろう。
そして、AI活用においても重要である。
情報が多すぎる時代においては、「答えを導き出す力」よりも「問いを立てる力」の方が重要となる。
この問いを作り続けるかどうかが好奇心である。
子どもの頃を思い出して欲しい。
私たちは親に「なぜなぜ攻撃」をしたはずだ。
その「なぜなぜ攻撃」を一切怒らないし面倒くさがらないAIに、いつでも何度でも行うことができる。
3:構造的な理解ができる人
物事をふわっと理解して何となくやったらできる天才はいる。
そういうのはもう人種が違う。
参考にならない。
無視でOK。
必要なのは、業務を棚卸できるかどうかである。
つまり、多くの人に求められるのは、業務を棚卸しして、要素分解し、筋道を立てて考える力だ。
AIを活用しようとしても曖昧な質問では、その出力結果も曖昧になる。
指示を的確に行うことで、より精度の高い結果を入手することができるようになる。
情報収集装置として活用することができるようになる。
ちなみに、このように構造的に物事を捉えられる人は、業務の仕組み化やシステム開発の現場でも、非常に高い成果を出すことができる。
最後に:AIがあるから大丈夫ではない
今回のコラムはどうだっただろうか。
「AIがあるから他は不要」と豪語する人がいる。
だが、それは組織の弱体化を招く思考だ。
確かにAIは業務を効率化する。
でも、それは「今の自分たちが業務を理解している」からこそ成り立っている。
もし今後、業務を知らない人たちばかりの組織になったら――
その時、AIを使いこなせるだろうか?
そんなはずがない。
AIはあくまでもツール。
使いこなすには、業務理解・ITリテラシー・人間力が必要不可欠だ。
楽して簡単に儲けたいと思うのは経営者の性かもしれない。
だが、現実には「楽して儲ける」なんて都合のいい話は存在しない。
経営者としての立場にある以上は、組織をどう導くか、その責任と向き合わなければならない。
さて、今回のコラムが何か気づきや学びになれば幸いである。
最新情報はスタンドエフエムで投稿している。
IT関連の話題を別角度から見てみたい
ITニュースを簡単に知りたい
IT化やDX化の話題を学びたい
自分の会社が効率化ができるか知りたい
自分の時間を大事にしたい
といった方は是非スタンドエフエムを覗いて欲しい。
それではまた次回のコラムでお会いしましょう。