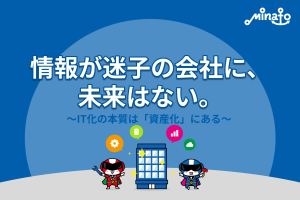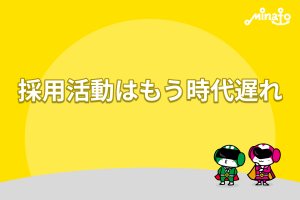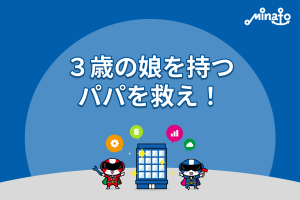COLUMN コラム
目次
DX時代に「内製化」は選択すべきか?
DX化を内製化した方がいいという記事を拝読したので、私の意見を述べておこうと思う。
結論から言うと、2つある。
- DXは内製化しても外注化してもよい
- IT化のことを指しているので、IT化であれば外注化した方がいい
記事によると、DXは内製化した方がいいということだ。
なるほど、とは思う。
確かに自分たちでビッグデータを活用して、顧客体験価値を向上させて、競争優位性を獲得できるなら別に内製化もいいだろうと思う。
しかし、記事を読み進んて行くと、どうやらDX化とIT化の区別がついていないように見受けられた。
全く違うものを同じものとして論じてしまうと、本質を誤ってしまいかねない。
IT化とDX化の違い
世の中で言われているDX化は、IT化であることが大半である。
そうなると、IT化を内製化すべきか?という話に発展する。
そもそもIT化とDX化とは、どのように違うのだろうか?
DX化は、デジタル技術とビッグデータの活用を前提として、ビジネスモデルやサービスなどを変革することで顧客体験価値を向上させ、企業としての価値を向上させる取り組みのことである。
IT化は、デジタル技術を活用することで業務フローや手順を効率的にしたりアナログ業務を削減したりすることを指す。
つまり、DX化とは、ビッグデータの活用ができればExcelを使って実行することができるのである。
実例としてワークマンを挙げることができる。
ワークマンは商品価値や顧客体験価値、ニーズの掘り起こしなどをデータから発見し、低迷していた売上を約3倍まで増加しV字回復された。
一方で、IT化は様々な種類があり、多種多様である。
電子化(デジタル化)、効率化や自動化、システム化などがIT化に含まれる。
また、IT化を行ったからといって、必ずしも生産性が向上するわけではなく、逆に非効率になってしまうこともある。
たとえば紙を電子にしたのに、なぜか印刷してチェックして、また別のサービスに手入力している、といった電子化の弊害をよく耳にする。
業務量が何故か2倍以上になった、とお聞きした。
このように電子化(デジタル化)したのに、効率が悪化したという事例は多い。
また、システム化も同じで業務効率が悪化したり失敗したりする事例が少なくない。
そもそもIT業界で言う「システム化」とは、「自社専用のツールやシステムを開発すること」であるが、日本語に置き換えると「仕組み化」になる。
仕組み化とは、業務フローや流れを均一にして、いつ誰がやっても同じ結果を得るようにすることである。
この仕組み化を行っていないまま、システム開発を行ってしまうと、「こんなはずじゃなかったのに」と後悔することになる。
さて、IT化とDX化の違いについて説明したが、話を戻そう。
内製化するメリットは何だろうか?
開発を内製化するメリットとは何か
内製化することで得られるメリットは、いくつかある。
- 自分たちで思い通りに行うことができることだ。
- 自社の社員なので、命令もできる。
- 失敗しても追加費用もないように見える。
- いつも社内にいるので、コミュニケーションもやりやすい。
- 企業文化を理解している社員がやってくれる。
まとめると、
自分たちでコミュニケーションができなくても何とかなるし、都合のいい人材を社内にいれておけば、失敗リスクを減らせるからいいよね!
ということである。
かなり後ろ向きなメリットである。
記事に書いてあるメリットでは、3つ紹介されていた。
- ノウハウやナレッジを社内に蓄積できる
- システムのブラックボックス化を防止できる
- 開発コストの削減
これらのメリットにも意見を述べたい。
開発コストは削減できない
簡単なものから言うと、開発コストだ。
明らかに増える。
社員として採用することになるので、人件費として計上することになる。
エンジニアはコストが高い職種である。
しかも、チームで動くことになるので複数人必要だ。
できるエンジニアを用意した上でチーム開発をするなら、月間少なくても100万以上かかる(2名体制)。
年間1200万円の費用が毎年発生する。
開発スピードを増やすために人員を増やせば、その分費用が毎月かかる。
業務委託だと更にかかる。
1人100万とか普通だ。
このように開発コストは削減にならない。
ちなみに、上記はシステム開発領域で論じているが、DX領域で重要となるデータエンジニアを社内で用意するなら、1人あたり月100万円以上の給与を用意できないと土台に乗らない。
エンジニアは非常に高価な人材であるのだ。
ブラックボックス化は回避不可能
なぜ回避できると思うんだろうか?
社内で対応できないから外注したのであって、メンテナンスもカスタマイズも外注するのが当たり前である。
名刺や封筒でも同じだ。
システム開発だけ「ブラックボックス」という言葉でラップして、問題視する傾向が強い。
「外注する際の労力がかかるのは面倒だし、自由にカスタマイズできないのがダメだ」と言う人もいる。
しかし、社内に用意しても社内の人材に依頼する労力は同じだし、システム開発である以上、仕様というものが存在し、必ずしも自由にカスタマイズできるわけではない。
どうも粘土のように思っている人が多いのだが、住宅と一緒と思っていただけると分かりやすい。
一度トイレの場所を1階に設置した後に、「やっぱ2階に設置してくれ」って言われたら大工事が発生する。
日曜大工レベルでは絶対無理である。
なぜかできると思う人が多い。
また、社内で開発してもブラックボックス化するのは避けられない。
必ずブラックボックス化する。
というのも、エンジニアが作ったものを他の人が理解できないからだ。
なので、内製化してもしなくてもブラックボックス化は起こるし、コミュニケーションの労力は発生するし、自由にできるわけではないのだ。
ノウハウやナレッジが蓄積できる
これは本件に限らず重要な要素ではあるが、本件に限って言うなら、システム開発におけるノウハウやナレッジを蓄積して、どうするんだろうか?
自分の業務内容を理解していないまま毎日を過ごしている人が意外に多い。
そのため、エンジニアに依頼が来ても何がしたいのかよく分からないまま、狙いも分からないまま開発して、使われない機能が誕生する、ということはよくある。
こういうことを何回繰り返しても、ナレッジもノウハウも蓄積できない。
業務に関係ないことだし、IT企業であっても大企業であっても、こうした領域のノウハウやナレッジは共有されない。
DXの領域に限って話しても、別に顧客体験価値が向上して信用度や競争優位性を確保できるのであれば外注化してもいいだろう。
何をしたから、こういう結果になった
という事例を獲得していけば、自然とそれがノウハウやナレッジになる。
外注化したら得ることができない、というわけではないのだ。
まとめ~内製化は大手の戦略と心がける~
DXにしろシステム開発にしろ内製化は、大手の戦略である。
維持費だけでも大きなコストであるし、採用費用も多額になる。
また、こちら側に確たるノウハウがなければ採用も難しい。
適当に採用して失敗した、ということになりかねない。
そういうことは、大手だから行える戦略なのだ。
また、中小企業の戦略として尖がった方がよい、とよく耳にする。
専門性を持ち、強みを発揮する。地域戦略を大事にする。
これが中小企業の戦略としてよく語られる。
ITだのDXだのに内製するコストを使うのであれば、他の部分に投資した方が合理的である。
外部のプロを思う存分活用して、自分たちは自分たちのことに集中する。
これが中小企業の戦略であるし、また、経済産業省が出しているガバナンスコードにもDXの戦略として紹介されていることでもある。
また、これは持論であるが、日本企業はDXと色気づくよりもまずは徹底した効率化やデジタル人材の育成に投資すべきである。