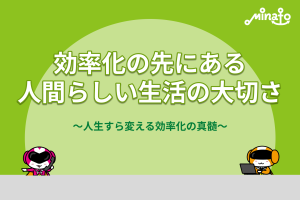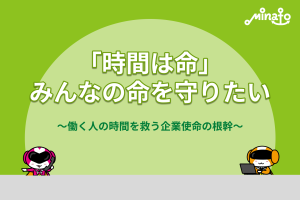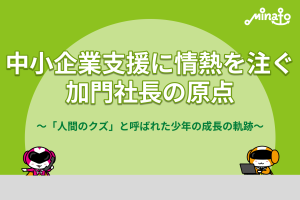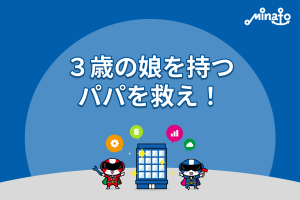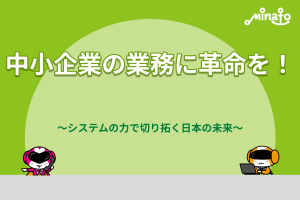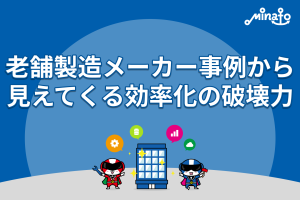COLUMN コラム
「DXの本質は人を幸せにすること」──株式会社皆人の加門和幸社長は、IT化やDXを「道具」と捉え、その先にある人間中心の価値創造を重視しています。技術を通じて、どのように人々の仕事や生活を豊かにできるのか。これからの時代に必要な人材育成とは何か。加門社長にじっくりとお話を伺いました。
多くの企業がDXに失敗する理由とは?
なぜ多くの企業がIT化やDXに失敗してしまうのでしょうか?
DXが失敗する最大の理由は、手段と目的を履き違えているからです。よく勘違いされるのですが、DXやIT化は目的ではありません。あくまで手段、道具なのです。
会社は社会のため、お客様のためにあります。社会に貢献したい、お客様の笑顔をもっと増やしたい、そういう思いがあるから会社を経営しているんです。IT化もDXも、その思いを効率よく実現するためのツールにすぎません。
つまり、DXの本質は技術を使って人々の生活や仕事をより豊かにすること。お客様の笑顔を増やしたいという思いを、効率的に実現するための手段なんです。
だからこそ、何のために、どういう未来を実現したいのかを明確に持った上でIT化することが大切です。その視点がないから失敗するんだと思います。
IT化やDXは「道具」ということですが、具体的に教えていただけますか?
ツールそのものではなく、それを使う人のスキルや考え方が重要である、ということです。
包丁を例に取りましょう。包丁は人を傷つける道具にもなれば、人を幸せにする料理を作る道具にもなります。また、ミシュラン一つ星のシェフと私が同じ包丁を持っても、作れる料理は全然違いますよね。
鉛筆だって、画家に持たせれば人を感動させる絵が描けるけれど、私が持てばただの文字しか書けません。Excelも同じで、使い方を知っている人と知らない人では、できることが全然違います。
つまり、道具は同じでも、使う人によって全く違う結果が生まれるのです。IT化やDXも全く同じで、その道具をどう使うかをデザインして、チームや組織で管理し合ったり、効率を上げたりするために使うものだと思っています。
DXが実現する「お客様を特別扱いする未来」
IT化やDXを正しく活用すると、どのような未来が実現できるのでしょうか?
お客様一人ひとりを特別扱いできる未来です。
例えばホテルに宿泊した際、「昨年は7月にお越しいただきましたね。今年は春ですが、こんなおすすめがありますよ」と言われたら嬉しくないですか?
保育園でも同じです。子どもの情報をちゃんと引き継いでいれば、先生が変わっても「この子はアレルギーがあって、でも蝶々を追いかけるのが好きで……」と、一から説明しなくても共有できます。
さらに、成長記録がデータとして残っていれば、卒業時に「1年生の時はこんなに幼かったのに、成長しましたね」って言えるんです。保護者の方にとってみれば、これほど感動的なことはないでしょう?
これがITの力で、情報の一元化によってできるDXなんです。お客様に「この会社じゃないとダメ」って思ってもらえる状況を作れるんです。
情報を一元化して共有することで、サービスの価値が上がるのですね。
まさに、その通りです。
情報の属人化は、会社の損失につながります。属人化とは、本来会社の資産であるべき情報が、個人に紐づいてしまっている状態のことです。
例えば、引き継ぎの時に「この資料あったような気がするんだけど、どこに行ったかな……」となると、大問題ですよね?
情報は会社にとっての資産なので、本来会社が保有すべきものなんです。
1人が知り得た情報を一元管理することで、誰もがその情報にアクセスできます。そうすれば、一人ひとりのお客様に適した接客ができて、特別感を感じてもらえるんです。それが情報の属人化をなくすことの本当の意味であり、取り組むべき理由だと考えています。
世界的に遅れている日本のIT事情
IT化が遅れている日本企業が抱える最大の問題は、何だとお考えですか?
先ほどDXやIT化が進まない最大の理由は、手段と目的を履き違えているからだとお伝えしました。
これは日本企業がIT化やDXに取り組もうとした時に目的を考えずに、キャッチーな言葉だけを聞いて取り入れようとした結果から判断できます。
酷な言い方をすると、「ファッション」のように捉えている経営者が多いように思います。
一方で、IT化が世界的に遅れていると言われている日本企業が抱える問題という視点で考えると、別の問題があります。
たとえば、近くの企業がやっていないから大丈夫と思ってしまうことや日本国内で経済が回るがゆえの安心感なども問題です。
でも、最大の問題は何か?根本的な問題は何か?と聞かれると、人材教育への投資不足です。「なんでわざわざ教育せなあかんねん」というような考えが根底にあるので、世界と比較して、日本企業の人材投資比率が低いんですよ。
日本は職人の国なので、「背中を見て学べ」という文化が根付いています。しかし、今の時代はそれだけじゃ通用しません。特にITリテラシーの教育は急務なのに、そこに投資していないのです。1995年以降ネット社会が当たり前になってきた頃から日本の没落は始まりました。それまでは世界が日本に勝てないと思っていた。だから、人材教育に多くの時間とお金を使ったわけです。対して日本は逆に教育にお金を使わなくなった。その結果が「失われた30年」となったわけです。
実際、どの程度深刻な状況なんでしょうか?
2つの調査結果から深刻さをお伝えできます。
1つはスイスのIMDという研究機関が出しているレポートです。
そのレポートで日本のデジタルスキルは67か国中67位と評価されています。
大変失礼な話ではありますが、バーレーンやイラン、南アフリカなどの日本よりもランクが低いと思いがちな国々にさえパソコン操作で負けているのが日本です。
もう1つは帝国データバンクの調査結果です。
その調査で、生成AIを企業として活用しているのは、たった17%であると報告されているんです。残りの83%は「使える人がいない」と言っています。これって「どうして自転車乗らないの?」「乗れる人がいないから」と言ってるのと同じことです。「練習したらいいのに!」ってなりますよね。
しかし、日本人は卒業後の学習に消極的です。大学卒業したらもう学びは終わり、みたいな風潮がありますよね。
アメリカでは60代でMBA取る人も珍しくないし、ヨーロッパでは生涯学習が文化として根付いています。一方、日本では大学卒業=学習終了みたいな雰囲気なんです。
だから、今でもパソコンを「使ったことがない」という人が6割もいます。本気で教育に投資すれば、一気に業績が変わると思いますよ。
人に余白を作り、幸せを生み出す「楽デジ」
その中で、御社の「楽デジ」はどのような役割を果たすのですか?
「楽デジ」は、人に余白を作って幸せにするためのサービスです。具体的には、クリエイティブじゃない定型業務を効率化します。生成AIがクリエイティブな業務を効率化するのと組み合わせれば、全方位の効率化も可能です。
ポイントは「余白」です。例えば、時間がない時に「今日は2時間かけて、フランス料理を作ろう」とはなりませんよね。
でも、2時間の余白があって、今日が子どもの誕生日や、旦那さんの昇進記念日だったら、フランス料理に挑戦する気になると思います。この「できる」「できない」を左右するのが時間、つまり余白なんです。
業務を効率化して、時間を短縮する以上の価値がありますね。
はい。余白があれば、新しい知見を得られるし、お客様への提案も充実するし、自己研鑽だってできます。効率化って、単に時間を短縮することじゃないんです。より価値のある仕事に時間を使うための手段なんです。
IT化とDX化を正しく組み合わせることで、人がもっと創造的に、もっと人間らしく働ける未来を作る。それが私たちの目指している世界です。
***
加門社長との対話を通じて見えてきたのは、テクノロジーの本質は「人を幸せにする道具」だということです。DXやAIは冷たい機械的なイメージがありますが、その先には人間の温かみと幸せが広がっています。
そのためにも、まず人材教育とITリテラシーの向上、そして、何のために会社があるのか、誰を幸せにしたいのかという原点に立ち返ることが大切です。
技術の進化は止められません。しかし、その技術をどう使うかは、私たち人間次第。加門社長の言葉には、技術と人間が調和する未来への道筋が示されていました。