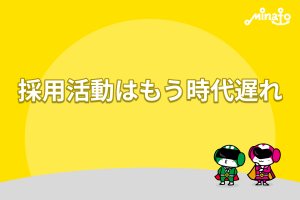COLUMN コラム
正体不明の「DX人材」
とにかくIT関連の用語は、言葉遊びが過ぎる。
意味不明だし、「で?」って思うような言葉の羅列である。
その1つに「DX人材」という言葉がある。
多くの企業が経済産業省の出している文書を読み解き、独自の見解を出している。
一読させていただいたが、本当に各社苦労されているなと思う。
それほど言葉遊びで実態を捉えていないように思うのだ。
以下経済産業省の出しているページを共有したい。
こちらは、DXを推進する上でのスキルや人材要件を取りまとめた資料となる。
時間がない方は概要編でよいと思うが、時間があれば一度本編を一読していただきたい。
とはいえ、最初のツッコミポイントである。
「デジタルスキル」と言っておいてDX推進におけるスキル要件や人材要件とは、全然違うことを指している。
詐欺レベルだ。
イメージだと、缶コーヒーを渡されて飲んでみたらコーンポタージュだったくらいの詐欺レベルだ。
デジタルスキルというと、ExcelやWordなどのOffice製品の活用スキルも含まれる。
しかし、ここではDXに焦点を当てているので、デジタルスキル云々は最早できて当然であるべきである。
よって「デジタルスキル標準」という表現自体が誤りであり、先行き不安を覚えるタイトルなのだ。
このタイトルだけでコラムを1つ書き終えてしまえそうだが、中身に入っていきたい。
DXリテラシーとは何か?
DX人材の前に、社員の誰もが持っておくべきものとして、DXリテラシーを挙げている。
DXリテラシーとは、「全てのビジネスパーソンが身につけるべき能力やスキルを定義」と記載されている。
ここでは紹介しないが、17頁から紹介されているので是非読んで欲しい。
本当に必要なの?
これって世界的な企業で働く人が全員持っているの?
と目を疑いたくなるようなスキル・能力ばかりである。
逆にこれらのスキルや能力を全て保有している人がいれば、それは「超人」である。
全ては不要だと私は考えるし、人には向き不向きもある。
日本人が大好きな経営者と言えば、スティーブ・ジョブズだ。
彼は欠点まみれの経営者であったことでも有名だ。
人は補い合うからこそチーム・組織として力を発揮する。
全員が超人である必要性はない。
また、知らない言葉に接した時は主体的に自ら調べることで情報収集して、業務に活用することを求めているが、それは経営者として求められる要素だと思う。
一般的な従業員に求めるのは酷な話であるし、それができる人たちで組織が構成されているなら、今頃日本は世界を牛耳っている。
評価基準に入れるなどして対策するなどして工夫が必要で、その工夫をしてもなかなか難しいのが現実だろう。
簡単にまとめると、DXリテラシーは絵に描いた餅である、ということである。
だが、これらの中で会社に必要な人材の要件をピックアップしておいて、該当する人しか採用しないという活用方法はよいと思う。
DX推進人材について
大きく分けると5つの人材がいる。
ビジネスアーキテクト、デザイナー、データサイエンティスト、ソフトウェアエンジニア、サイバーセキュリティ。
言いたいことだらけだ。
中小企業にこういった人材を揃えるのがいかに難しいか分かっているのかと憤りを覚える。
平成24年と古いデータだが、日本にある企業は171万社と言われている。
さて、従業員数4名以下はどれくらいの比率だろうか?
約6割である。
この時点でDXは終了する。
5名揃わない。
10名以上の従業員がいる企業の総数は42万社である。
つまり、9名以下の従業員がいる企業の総数は残りの129万社ということになる。
10名以下だとマルチタスク上等で、攻め攻めの企業が多い。
DXに必要な5名を揃えるなんて無理だ。
つまり、日本において129万社はDXなんて不可能であると言っているようなものなのだ。
何とお粗末か。
この時点で話をする必要性は全くなくなる。
が、もう少し頑張ろうと思う。
ここで挙げられている5つの定義の中で不要なものが3つある。
デザイナー、ソフトウェアエンジニア、サイバーセキュリティである。
サイバーセキュリティはDX関係なく、今後のビジネスにおいて必要不可欠な存在であるので、外してよいし、社内で用意する必要性もない。
デザイナーも同じで、DXの成功事例としてアマゾンがよく登場するが、AWSや宇宙事業にデザイナーが役立っているように思えない。
ソフトウェアエンジニアも同様である。
私もソフトウェアエンジニアであるが、私はDXに向けた取り組みを実施できるが、DXはできない。
それにエンジニアは「ソフトウェア」だけではない。
スマホやカメラ、車などは「ハードウェア」エンジニアの領分であり、AIは「AI」エンジニアの領分である。
このようにエンジニアは複数の領域を持っていて、それぞれが得意としていることも違う。
我々は原則的にDXに役立つ仕組みや機器の開発を行うことはできても、DXそれ自体に効果的な人材ではない。
ちなみに、データサイエンティストもエンジニアの1つだ。
このように見ていくと、ビジネスアーキテクトとデータサイエンティストのみが残る。
ビジネスアーキテクトなんて聞きなれない言葉にするから分かりにくいので、馴染みある言葉に置き換えよう。
100%合っているわけではないが、プロジェクトマネージャーと言い換えてよいのではないだろうか。
つまり、指揮決定権を持ち、組織や事業を動かせる人材のことである。
社長や役員、部長といった人がこの立ち位置になることが多いと思う。
すると、大変だ。
指揮者とデータサイエンティストしか残っていない。
これでDXができるのだろうか?
答えはNOである。
DXに必要な人材とは?
DXは、会社の組織や事業、運営方法などを変革するかどうかが大事である。
そのため、意思決定者とデータサイエンティストの2つが残り、あとの3つは不要と説明した。
では、DXに必要な人材とは、どういった人材だろうか?
意外に思われるかもしれないが、営業のできるマーティング担当者である。
マーケティングというと、やれインスタだ、やれYouTubeだ、やれネット広告だと1つのことしかできない人が多い。
そういった人のことではない。
「営業ができる」マーケティング担当者である。
つまり、営業担当者としても動ける人で結果も出せる人でないとマーケティングができない。
マーケティングと聞くとカッコいいので、最近人気だ。
だが、営業もしたことのない人がお客さんの気持ちを理解できるだろうか。
ここで言う営業とは、お客さんに不要なものを買わせるような悪質な営業ではない。
お客さんの気持ちに寄り添い、本当にその人のことを考えて、必要なものを提供できる営業のことである。
そんな人いるの?って思うかもしれないが、そういった人でないとしっかりとしたマーケティングはできない。
お客様の気持ちや社会の動向を理解する必要があるDXには、営業のできるマーケティング担当者が必要不可欠である。
まとめ~DXはDXとしてアピールしないもの~
最後にまとめていきたい。
私の見解だが、日本におけるDX状況において成功事例と言われるものは、ただのIT化である。
DX化の事例は本当に一握りしかなく、DX化したと思っていないことの方が多いように思う。
だからこそ、DX化の成功事例として表に出てこないのだ。
たとえばDX化の成功事例としてよく紹介されるのがアマゾンである。
本屋のECサイトから始まり小売店業に変換し、アレクサというIoTを開発して提供している。
今ではAWSというデータセンターとしての事業や宇宙事業も手掛けている。
しかし、これをアマゾンはDXの成功事例として大々的に打ち出していないのだ。
DXとは、DXであると大々的に打ち出してアピールするようなものではないのかもしれない。
つまり、DXはやろうとすることではなく、企業として生存するためには自然と行うものではないかと考えるのだ。
このように考えると、DXはしようしようと思えば思うほど遠ざかってしまうかもしれない。
私たちは企業として、お客様にどんなことをしたら喜んでいただけるか、社会貢献ができるのか、選ばれ続けるのかを考え、社会の波に乗れるように常日頃から学び続ける必要があるのではないだろうか。
遠回りのように思えて、そうした努力が案外近道かもしれない。