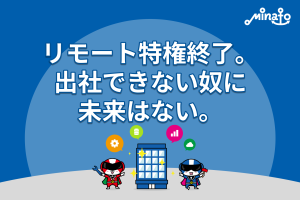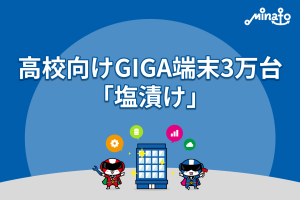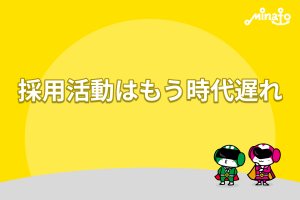COLUMN コラム
正直、DX化はそもそも失敗しかしないだろう。
カレーを作りたいのに、渡されたレシピはチャーハン。
いくら作ってもチャーハンしかできない。
それが今の日本だ。
日本におけるDX化の事例は全てIT化である、と言っても過言ではない。
そんな状況ではあるが、DXの前提となるデジタル技術の活用はIT化を指し示している。
せめてIT化は成功したいものだが、失敗する企業が多い。
では、なぜ失敗するのだろうか?
今回のコラムでは、IT導入に失敗する3つの原因を見ていきたい。
パソコンが苦手な人が多い
今回3つの原因を挙げていくが、その中で一番影響を与える原因が「ITリテラシーの低さ」である。
DXだなんだの言っている場合ではない。
そもそもIT化すらできていないのだ。
パソコンが苦手だから、ITサービスを導入した時に拒否反応が起きる。
面白いくらいに起きる。
未知の物質を触る人のように恐れる。
それでも何とか触って覚えようとする人はよい。
そういう人はいずれ不慣れでも業務を行うことができるようになるだろう。
問題は、学習しようとしない人である。
そういった人は自分が分からないから、操作できる人に業務を依頼する。
その人も業務を抱えているのに、自己中心的なものの考えで依頼する。
折角システム化して共有や検索を容易にしようとしたのに、パソコン音痴のせいで逆に業務量や業務時間が増えてしまう。
これこそ「老害」と言わず何というのか。
そして、そういう人に限って発言力がある。
役職者であったり古株であったりする。
自身の影響力を利用して、自分が使えないから元に戻そうと騒ぎ立て、断念することになるのだ。
不慣れでも学ぼうとする前向きの姿勢があればよい。
だが、何故かそういう人に限って学ぼうという姿勢ではなく、廃止しようという労力と時間に自分の命を燃やす。
何とも見苦しい限りだ。
他責思考が強力な「老害」を生む
学ぼうとしない人は他責思考であることが多い。
だが、システム導入を失敗に導こうとする人だけではない。
少し年齢を重ねると新しい技術についていけない自分に言い訳をするようになる。
「若くないから」と。
「若い人ならできる」というのは、他責思考であると気付くべきである。
自分の限界を勝手に線引きして、努力しないでよい理由を作るとともに「若い人ならできるでしょ?」という責任転嫁を行っているのだ。
その責任転嫁の結果、若い人は不慣れでも頑張って努力して身に付けているだけである。
もし自分がやっていれば、そのスキルを身に付けていたのは自分かもしれない。
考えてみよう。
自分も若かったのだ。
90年代は何歳で、2000年代は何歳で、2010年代は何歳だったか?
その頃の自分は今「若いんだからできるよね?」と言っている人の年齢ではないか?
私も10代、20代の時はあった。
もうすぐ40代に入る。
常に自分をアップデートしてきたとしたら、「若いんだから」という言い訳を口にするだろうか?
80代でもネットをバリバリ使い倒している人もいる。
その人たちが特殊ではないのだ。
私たちが学ぶのを辞めたのがいけなかったのだ。
私たちは常に学び続ける必要があるのだ。
いつかは「老害」になるとしても、影響力の少ない「老害」、他の部分でよい影響を与えることのできる「老害」を目指すべきである。
ちなみに、任せた結果、導入したシステムを使えなくて文句を言って廃止させるよう動く、のは果たして任せた人として責任ある行動だろうか?
この点も今一度考えてみたい。
業務への理解不足が失敗を作る
2つ目の原因としては、業務への理解不足である。
意外に思うだろうが、人は自分の業務を理解していない。
そんなバカなと思うだろう。
だが、これが現実である。
2つの根拠がある。
1つ目は、弊社が業務瞬殺ツールを開発しようとお客様の業務をヒアリングする時に、お客様の言っている内容が二転三転ならまだしも五転六転七転八転することすら平気であるからだ。
しかも、言っている担当者が変わると、更に変わる。
複数人が会議に出ると、もう収拾がつかない。
全員同じことを言っているのに、全然違うことにしか聞こえない。
逆もある。
全員違うことを言っているのに、全然同じことにしか聞こえない。
AとAは一緒ですか?
いいえ、AとAは違います。
哲学の問題かな?って思う。
だが、これが普通だ。
2つ目は、引継ぎ問題である。
弊社の業務瞬殺ツールを導入されると、引継ぎは簡単になる。
何故ならそのツールを渡して使い方を教えるだけだからだ。
1日あれば余裕だ。
弊社ツールを導入されていない場合は、一般的に引継ぎはビッグイベントだ。
そして、多くは業務品質の低下を招く。
口伝が如何に難しいか。
北斗神拳はよく一子相伝でもったなって思う。
話が逸れた。
100%業務の引継ぎができたと胸を張って言える人は少ないだろう。
普通100%業務の引継ぎができたなら、業績が下がることはない。
もし下がったとしたら、それは業務を引き継いだ人の責任ではなく、引継ぎをした人の責任である。
だが、その人も業務を100%理解していないのだ。
だから、引継ぎができない。
これが業務を理解していない根拠なのだ。
このような状態でシステムを導入したらどうなるか?
当然失敗する。
- 「なんか違う」
- 「逆に仕事が増えた」
- 「あれ、この場合は対応できない」
といったことが起きるからだ。
整理できていないのだから当たり前である。
たとえば服が大量にあるとする。
どれだけの枚数あるのか、どういったアイテムがあるのか、それぞれどう管理するのが適切か、など把握せずに収納ボックスを3つ買う。
さぁ、整理できるだろうか?
答えはノーである。
もしかしたら夏物しか入らないかもしれない。
もしかしたら部屋の押し入れに入らないかもしれない。
ちゃんと把握することがファーストステップである。
では、業務上では、何が必要か?
それこそ「仕組み化」である。
「テンプレート化」と言ってもいい。
再現性のある状態を作り上げることが重要である。
この仕組み化ができていれば、誰でもその業務を実行することができる。
この状態だからこそIT導入時に、どのサービスを入れたら効果的かを判断できるのだ。
「とりあえず入れよう」では失敗するのは当たり前である。
だが、ここでまた注意点である。
日本人あるあるなのだが、「私の仕事は私しかできない」という状態を維持したいのだ。
自分の価値を高めたいから協力的にならない。
引継ぎもそうだ。
実はこのプライドを守る行為が足を引っ張る。
そのため、仕組み化が遅れる。
そんなに優秀なら超大手企業にヘッドハンティングされるだろう。
そうではないなら、それが答えだ。
まとめ
1つ目はITリテラシーの低さ、2つ目は業務理解の不足を挙げた。
スイスのIMDという研究機関がある。
この研究機関が年に1度出しているレポートがあるが、日本のITリテラシーは63か国中の62位である。
とにかく低い。
これは笑って済まされる問題ではない。
今すぐパソコン・アレルギーを解消すべく「治療」すべきだ。
まずはこの対策から実行すべきなのだが、まだ最後の1つが終わっていない。
次回、最後の1つについて考察していきたい。
1回で終わると思っていたが、思いのほか3000字に近くなってしまった。
もし何か気づきや学びになった方は是非シェアをしていただけると嬉しい。
次回、後編でお会いしましょう。