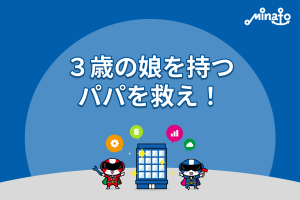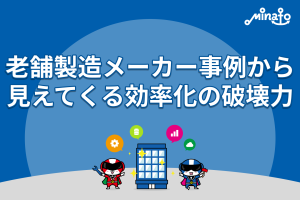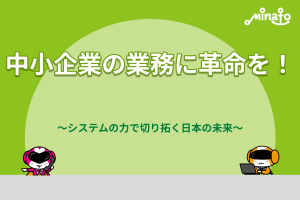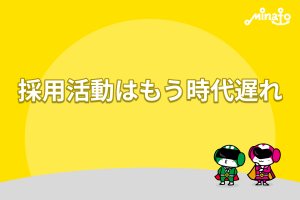COLUMN コラム
近年、M&Aのニーズが高まっている。
だが、M&Aを意識するもののなかなか希望条件で取引できることは少ない。
そこで、今回はM&Aにおいても仕組み化が重要である理由について語っていこうと思う。
本気でM&Aをやりたいなら、仕組み化を絶対に意識しなければならないのだ。
目次
M&Aが注目されている背景
M&Aは企業の成長を促進させる手法として注目されている。
たとえばある事業を行いたいが、その事業を成長させるのに5年かかる。
であれば、すでに成長させている企業を買収してスタートダッシュを切りたいと考えるのはビジネスにおいて至極当たり前のことだ。
今商品ライフサイクルは3年と言われている。
ちまちま成長させていては間に合わないのだ。
注目されている背景に高齢化社会の問題も
また、高齢化や後継者不在の問題も大きい。
一昔前は「身売り」と捉える人が多かった。
倒産するのと「身売り」して継続する二択であれば、後者を選ぶだろう。
未だにM&Aを身売りと考えている人が日本に多いという問題はあるものの、現実的な選択肢として考えられてきているのは素晴らしいことだと思う。
会社を経営する立場にある者としてゴール設定を行うべきである
海外では、経営者のゴール設定を行うべきであるというのが常識である。
IPOなのかM&Aなのか。
それとも、細く長く続けるのか。
こうした考え方によって力の入れ方や戦略が変わっていく。
たとえば細く長くやるつもりなら、別に仕組み化なんて不要だ。
社長の属人化100%でもいいだろう。
だが、IPOやM&Aをゴールにするなら、その考えは今すぐに捨てるべきなのだ。
仕組み化こそ最低限の条件だからだ。
では、M&Aにおいて仕組み化が必要とされる理由について見ていこう。
M&Aにおいて仕組み化が必要な理由
買い手が重視するのは「再現性」
買い手が最も重視するのは、「この会社は自分たちでも回せるのか?」という点だ。
つまり、事業の「再現性」だ。
経営者が変わった途端に売上が落ちてしまうケースはよく見聞きする。
買い手にとって「会社を引き継ぐ」ということは、「ビジネスモデルを買う」ことに他ならない。
属人化された事業に魅力を持たないのだ。
逆の立場になった時に想像すると分かりやすい。
全くやったことがない事業を担当することになったとして、しっかりやり切れる自信があるだろうか?
再現性がないということは、リスクが高いと認識される要因となるのだ。
属人化された会社だとロックリスクが高くなる
それでは、そうした企業を売却する場合、どのようなリスクを背負う必要があるだろうか?
それは「ロック」である。
音楽のジャンルではない。
属人化された組織をちゃんと動けるようにするまで、我々経営者の身動きをロックすることで安全性を担保しようとするのだ。
3年~5年くらいはロックされる。
このロックが長ければ長いほど我々は身動きできない。
全く嬉しくない。
属人化は双方にとってリスクでしかないのだ。
属人化とは、どういう状態か
とはいったものの、なかなか属人化のイメージがわかない人もいるだろう。
たとえば
- この業務は山田さんしか知りません
- このお客さん対応は鈴木さんしかできません
- あの資料の場所は高橋さんしか知りません
みたいな状態だ。
つまり、属人化とは、特定の人しか把握しておらず、その人が不在になると運用できなくなってしまう状態のことである。
中小企業では社長に依存するケースが多い。
こうした社長依存型の事業モデルで、社長が不在になれば一気に事業が成り立たなくなるのは火を見るよりも明らかだ。
このように、どんなに素晴らしい製品やサービスがあったとしても、人に依存している時点で企業価値が大きく低下するのだ。
仕組み化が企業価値を向上させる
逆に仕組みが整備されている企業であれば、再現性が担保されるため企業価値が高まる。
誰がやっても同じ成果を得ることができることが大事だ。
引継ぎ後の混乱を最小限に抑えることができる仕組み化があるだけで、「高く評価される」会社となるのだ。
別に売却目線でなくても、あなたの会社が一体どのくらいの価値なのかを知ることはよいことだ。
もう少し生活に置き換えると、同じ年齢同じキャリアでも給与が全く違う場合がある。
これはその人の価値が反映されているからだ。
今我々がどのくらいの価値なのかを把握することによって、成長を促すこともできる。
今日から始めるべき仕組み化3ステップ
では、どのようにして仕組み化を整えていくべきだろうか。
ここからは3つの方法をお伝えしよう。
1:業務を棚卸する
2:業務プロセスを見える化する
3:誰がやっても同じ成果になる仕組みを整える
この3つで実行するとよいだろう。
ステップ1:業務を棚卸する
今組織において業務の把握を行ってみて欲しい。
意外と業務の把握ができていないことが多い。
「誰が・何を・どのようにして」業務を遂行しているのかを書き出してみよう。
同じ業務なのに人によって違うということもある。
驚くほど属人化していることが分かるだろう。
ステップ2:業務プロセスを見える化する
ステップ1で明らかになった業務プロセスを明示的に書き出していこう。
フロー図にしていくことで流れを把握することができる。
中小企業では諸条件がある場合がある。
たとえば
- このお客さんは特別にこのようにする
- この季節は普段と違って、このようにする
といった特別条件があることが多い。
これらの条件ももれなく書き出していくことが大事だ。
ステップ3:誰がやっても同じ成果になる仕組みを整える
そして、誰がやっても同じ成果になるよう仕組みを整える。
先に諸条件を見てきた。
この機会に減らせるように取り組んでみよう。
できる限り小さなステップで、誰でもできるようにするのがポイントだ。
「経験がなくても業務を回すことができる」という状態にすることが理想的である。
そのためにフィードバックを受けながら、徐々に実行するのがよいだろう。
人材不足時代の仕組み化とは
ここまでの取り組みでほぼ完了である。
だが、今後人材不足時代がやってくる。
そうなった時に人に頼ることができない。
人に依存した状態では、仕組みを整えても属人化に近しい状態になるし、ビジネスを拡大できない。
そこで、省人化に取り組む必要性がある。
その省人化こそが最強の仕組み化だ。
1人の人間が10人の人間に匹敵する動きをすることができる。
そんな環境を整えることができれば、たった10人で100人規模の会社と同じことができるようになる。
そんな未来を作ることができるのが「省人化」なのだ。
会社のバトンを渡せる環境を作ることも社長の仕事
社長の仕事は多岐に渡る。
その1つが会社という組織を奇麗に整備することである。
賃貸でも汚い部屋をそのまま引き渡そうとすると、敷金から引かれて場合によっては請求されることがある。
これと同じく会社も整備されていないと価値なしと判断されて、買い手がつかない。
仕組み化は、会社に「未来」を与える行為だ。
その未来は社会や従業員への貢献につながる。
本当に会社のことを考えているならば、明日から仕組み化を始めてみてはいかがだろうか。
最後に
今回のコラムはどうだっただろうか。
M&Aというと、会社を売るので「裏切り」であると思う方が多い。
実際はそうではない。
より会社を高みに登らせる選択肢でもあるし、存続させるための手段でもある。
この事実をしっかり受け止めていただきたい。
今回のコラムが何か気づきや学びになれば幸いである。
最新情報はスタンドエフエムで投稿している。
IT関連の話題を別角度から見てみたい
ITニュースを簡単に知りたい
IT化やDX化の話題を学びたい
自分の会社が効率化ができるか知りたい
自分の時間を大事にしたい
といった方は是非スタンドエフエムを覗いて欲しい。
それではまた次回のコラムでお会いしましょう。